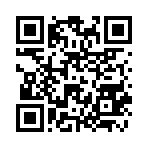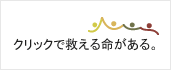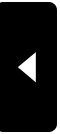テレビ報道を見ても
この動画を見ても
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191007-00010011-houdoukvq-soci
教師間のイジメなんて、
信じたくない気持ちと
あり得るかな?!
と、思いが、交錯しました。
実は、私の体験談を言いますと、
京都府巡査から滋賀県高校教師に転職した
昭和40年代は、
教員の縁故採用は、当然視されてました。
これも、イジメです。
私も、
京都府は、京都府警に遠慮して受験しませんでしたが、
夜間大学を卒業して
数府県受験しましたが、唯一採用して下さったのが、
滋賀県教育委員会、のみでした。
新任校に赴任して、
まず、古い教師に言われたのが、
あんたは、元ポリ公! らしいけど、
社会科で、何を教えんねん?! でした。
私は、
日本国憲法の前文通りの精神で、
教えます。と、答えたのが、
が、まず洗礼デシタ。
その後、懇親会の酒席で、
年配の教師が、こう言いました。
君は、高校生の情報を、警察に売らへんやろな?!
との言葉。
私は、反論しました。
公務員の守秘義務は、
警察でもずっと、ずっと叩きこまれて来た!!!
今も、鮮烈に覚えています。
当時は、教職員組合も強く、
庇ってくれる仲間も居ました。
兵庫県神戸市立小学校での
教師間のイジメも
徹底真相解明をし、
校長・教頭の責任追及、
教育委員会の責任追及、
そして、
加害側教師の責任追及、
そして、
イジメ行為に苦しんだ
若い教師が、立ち直って、
復職して、
イジメの無い学校造り、
子ども達が、喜んで学校に通える
学校運営に、寄与される事を
深く、深く、希望する
そして、組合も活発に成って、
教職員の世界が、ブラック産業化
しない事を願う、元教師の願いです。m(__)m
この動画を見ても
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191007-00010011-houdoukvq-soci
教師間のイジメなんて、
信じたくない気持ちと
あり得るかな?!
と、思いが、交錯しました。
実は、私の体験談を言いますと、
京都府巡査から滋賀県高校教師に転職した
昭和40年代は、
教員の縁故採用は、当然視されてました。
これも、イジメです。
私も、
京都府は、京都府警に遠慮して受験しませんでしたが、
夜間大学を卒業して
数府県受験しましたが、唯一採用して下さったのが、
滋賀県教育委員会、のみでした。
新任校に赴任して、
まず、古い教師に言われたのが、
あんたは、元ポリ公! らしいけど、
社会科で、何を教えんねん?! でした。
私は、
日本国憲法の前文通りの精神で、
教えます。と、答えたのが、
が、まず洗礼デシタ。
その後、懇親会の酒席で、
年配の教師が、こう言いました。
君は、高校生の情報を、警察に売らへんやろな?!
との言葉。
私は、反論しました。
公務員の守秘義務は、
警察でもずっと、ずっと叩きこまれて来た!!!
今も、鮮烈に覚えています。
当時は、教職員組合も強く、
庇ってくれる仲間も居ました。
兵庫県神戸市立小学校での
教師間のイジメも
徹底真相解明をし、
校長・教頭の責任追及、
教育委員会の責任追及、
そして、
加害側教師の責任追及、
そして、
イジメ行為に苦しんだ
若い教師が、立ち直って、
復職して、
イジメの無い学校造り、
子ども達が、喜んで学校に通える
学校運営に、寄与される事を
深く、深く、希望する
そして、組合も活発に成って、
教職員の世界が、ブラック産業化
しない事を願う、元教師の願いです。m(__)m
明日から
消費税が、8%から10%に成ります。
今、しきりと、
軽減税率がどうだとか?!
キャッシュレスがどうだとか?!
ペイペイ、がどうだとか?!
テレビ局は、しきりと報じていますが、
根本的には、
消費税は、所得の低い人から、
税を徴収する、
所得の高い人から順に、税を徴収する
累進課税制に、逆行する税制では、
ないでしょうか・・・?!
れいわ新選組代表の山本太郎氏
が、その点を訴えておられます。
の動画 です。
https://www.youtube.com/watch?v=MmV9jslUjoI
今、政府でも、国会議員でも、
税金の重さを感じているのだろうか?
という輩が多く居ます。
労働組合も弱く、
これから長い人生、どう生きていく?!
結婚もままならず
少子化が一層進行し
これからの日本、どうなるのだろう?!
山本太郎氏の指摘が、正しいか、どうか?
今まで、さんざん、欺瞞政治家、いや政治屋を
見続けて来た私・・・、
眉に唾付けつつも、
れいわ新選組のお訴えに
耳を傾け、勉強したい私です。m(__)m
消費税が、8%から10%に成ります。
今、しきりと、
軽減税率がどうだとか?!
キャッシュレスがどうだとか?!
ペイペイ、がどうだとか?!
テレビ局は、しきりと報じていますが、
根本的には、
消費税は、所得の低い人から、
税を徴収する、
所得の高い人から順に、税を徴収する
累進課税制に、逆行する税制では、
ないでしょうか・・・?!
れいわ新選組代表の山本太郎氏
が、その点を訴えておられます。
の動画 です。
https://www.youtube.com/watch?v=MmV9jslUjoI
今、政府でも、国会議員でも、
税金の重さを感じているのだろうか?
という輩が多く居ます。
街には、、非正規雇用の若者が増え、
労働者としての人権も守られず、労働組合も弱く、
これから長い人生、どう生きていく?!
結婚もままならず
少子化が一層進行し
これからの日本、どうなるのだろう?!
山本太郎氏の指摘が、正しいか、どうか?
今まで、さんざん、欺瞞政治家、いや政治屋を
見続けて来た私・・・、
眉に唾付けつつも、
れいわ新選組のお訴えに
耳を傾け、勉強したい私です。m(__)m
昨日の昼前に、我が家に、ジャ~ンと、電話がかかって来て、
いずこのメディアからからの
機械的な音声の、
私自身の選挙行動への質問ラッシュでした。
70歳以上は、一括りの扱いに不満 を持ちつつ、
を持ちつつ、
★ 投票には行く!
★ 投票先に困って居る?!
と、ダイヤル番号を押して、お答えしました。
私の答えたことも、
世論調査の結果として、
何処かで公表されると思いますが、
★ 投票には行く! だけど、投票先に困って居る?!
と言う事について、
マイ主張の一部を、申し述べたい!
と思います。
新興の政党には、一時、希望を持ちかけたのですが、
現政権が仕掛けた
共謀罪 や
平和法制 が、公認の“踏み絵”みたいな扱い、にはガッカリしましたし、
今、思うことは
日本国憲法の前文の精神を大切にし、
誠実に、恒久平和を希求し、
国際平和主義で、世界と協調し、行動し続ける国・日本です。
常々、日本は
圧倒的大多数の、
いずこのメディアからからの
機械的な音声の、
私自身の選挙行動への質問ラッシュでした。
70歳以上は、一括りの扱いに不満
 を持ちつつ、
を持ちつつ、★ 投票には行く!
★ 投票先に困って居る?!
と、ダイヤル番号を押して、お答えしました。
私の答えたことも、
世論調査の結果として、
何処かで公表されると思いますが、
★ 投票には行く! だけど、投票先に困って居る?!
と言う事について、
マイ主張の一部を、申し述べたい!
と思います。
新興の政党には、一時、希望を持ちかけたのですが、
現政権が仕掛けた
共謀罪 や
平和法制 が、公認の“踏み絵”みたいな扱い、にはガッカリしましたし、
今、思うことは
日本国憲法の前文の精神を大切にし、
誠実に、恒久平和を希求し、
国際平和主義で、世界と協調し、行動し続ける国・日本です。
常々、日本は
圧倒的大多数の、
真面目な庶民の日々の営為でもってる国だ!!!
と思って居ますが、
戦前の治安維持法下のような日本にしたくない!!!
と、青春期、京都府巡査だった私は、
警察権力に“過度”に期待されることは
お辛いことだろう・・・??!!
と思い、
警察権力の行使には、
厳正中立、
権力行使には、害される“法益”を防ぎ排除するための
最小限の行使が許される、という
権力行使比例の原則があるんだ・・・!!!
そして、
安保法制、積極的平和主義の名の下で、
自衛隊員も“戦死者”が出て来ないか?!
と、心配して居ます。
警察にも、自衛隊にも、労働組合は無いし、
親を安心させたい真面目な青年が、
誓約書で「危険」を覚悟しつつ、日々の勤務をされてます。
そんな警察官や自衛隊員に対して
お金持ち世襲政治家が、注文をつける、今の日本・・・!!!
怒りと共に、
国民の負託に応える、
政党勢力よ、出でよ・・・!!!!!
今は、選挙権を持たない
子どもたちに“迷惑”を掛けない
日本国と日本社会の伝承を!!!
と切望する、老爺です。m(_ _)m
気持ち良く、投票できる
国民の負託に応える、政党勢力よ、出でよ・・・!!!!!
と、切望し希求する、
戦争の影を少し知ってる老爺で御座います。
(>_<)m(_ _)m(T_T)(>_<)
と思って居ますが、
戦前の治安維持法下のような日本にしたくない!!!
と、青春期、京都府巡査だった私は、
警察権力に“過度”に期待されることは
お辛いことだろう・・・??!!
と思い、
警察権力の行使には、
厳正中立、
権力行使には、害される“法益”を防ぎ排除するための
最小限の行使が許される、という
権力行使比例の原則があるんだ・・・!!!
そして、
安保法制、積極的平和主義の名の下で、
自衛隊員も“戦死者”が出て来ないか?!
と、心配して居ます。
警察にも、自衛隊にも、労働組合は無いし、
親を安心させたい真面目な青年が、
誓約書で「危険」を覚悟しつつ、日々の勤務をされてます。
そんな警察官や自衛隊員に対して
お金持ち世襲政治家が、注文をつける、今の日本・・・!!!
怒りと共に、
国民の負託に応える、
政党勢力よ、出でよ・・・!!!!!
今は、選挙権を持たない
子どもたちに“迷惑”を掛けない
日本国と日本社会の伝承を!!!
と切望する、老爺です。m(_ _)m
気持ち良く、投票できる
国民の負託に応える、政党勢力よ、出でよ・・・!!!!!
と、切望し希求する、
戦争の影を少し知ってる老爺で御座います。
(>_<)m(_ _)m(T_T)(>_<)
世界のあちらこちらで、
ポピュリズムと言われる政治手法が、
勢力を増して来ています。
それと、民主政治は、どう対抗するのだろうか?!
ネットで調べて、このサイトに着きました。
http://www.hino.meisei-u.ac.jp/nihonbun/lecture/062.html
私たちは、目先の小気味よい呼びかけに反応しがちです。
ですが、それが、どういう結果に繋がって来たか・・・?!
この文で、学び、考えさせて頂きたい!!
たいと思います。
読みやすくする為に、
文中の文字に色も付けさせて頂きました。
【民主主義とポピュリズム・・・明星大学教授 服部 裕】
民主主義における政治リーダーのあり方
「決められない政治」あるいは「ぶれる政治家」などというように、昨今の日本では、国政を預かる既成政党の政治に対する批判が高まっている。所謂政治不信であるが、民主主義の場合、極度の政治不信は往々にしてポピュリズムを引き起こすことがある。それは、国民大衆が国難にあっても決断できない既成政治を見限り、より単純明快な主張を掲げる所謂「強いリーダー」を待望する社会心理に支えられるのが一般的である。
昨今の日本の政治状況で言えば、大阪市長や東京都知事に対するリーダー待望論が、その代表的な事例である。「物事を決められない政党政治」にはもはや何も期待できないので、より決断力と実行力があるように見える地方自治体の首長に大きな期待が寄せられるという図式である。実際に、領土問題が取りざたされている小さな島をある地方自治体が購入するとか、全職員に入れ墨の有無を問う調査を実施したりとかという行政手法が示すとおり、そのトップダウン式のやり方は、政府内、与党内そして国会と合議を重ねて物事を決定する国政のやり方に比べて、かなり歯切れの良い「強いリーダー」のイメージを演出していると言える。
では、なぜ地方自治体の首長はより強力なリーダーシップのパフォーマンスを演出しやすいのだろうか。その答えは、中央政府と地方自治における権力の委任形態の違いにあると考えられる。簡単に言えば、地方自治体の首長が住民の直接投票によって選出されて行政府を構築するのとは異なり、中央政府の長つまり内閣総理大臣とそれが任命する諸大臣は国民が直接選出することができないということである。後者が議院内閣制に基づく一方で、前者は言わば「大統領制」に近い権力委任の形態を取っているのである。したがって、政策実現の成否はともかくも、アメリカの「大統領」に近い首長は行政の執行権(予算や人事、さらには専決処分権等々)と議会決議に対する拒否権および事実上の法案請求権を握っているのに反して、内閣総理大臣はまずは閣議(その背後には行政専門職としての官僚が目付役として存在する)、そして与党の合意なくしては、議案の一つも国会に上程することができない。本来、原理的には大統領(首長)の権限と議会の権限が分立し拮抗しあう「大統領制(=二元代表制)」の方が、民意が一元的に委任される「議院内閣制(=一元代表制)」より、国民からの権力の委任は曖昧なはずなのに、上述のように首長が強い行政権を所有するため、見た目の政治的リーダーシップは地方の首長の方がより強く見えるのである。
つまり、昨今の内閣総理大臣のリーダーシップ欠如は、実は戦後の民主主義国家としての日本の政治構造そのものに由来していると考えなければならない。現在の野田総理大臣のみならず、戦後の歴代総理は党派の別なくみな多かれ少なかれ調整型のリーダーであり、強力なトップダウンなど誰一人実行できなかったと言える。(比較的明確なリーダーシップを発揮しようとした田中角栄のような総理大臣は、道半ばで失脚の憂き目を見ている。弱い党内基盤にも拘らず長期政権を実現した小泉首相だけが、例外的に国民の人気を支えに強力なリーダーシップを発揮したポピュリスト的首相だったが、その政治力は「郵政民営化」だけに限定されていた。)
しかし、大統領的な性格を有する首長と雖も、みながみな大阪市長や東京都知事のように強面のリーダーとはなりえない。強いリーダー像を演出するには、もちろん並外れて強烈なキャラクターが必要であろうが、キャラクターだけで政治的リーダーシップを発揮できる訳でもないからである。マックス・ヴェーバーが民主制下の「政治家」を「デマゴーグ(民衆煽動家)」という言葉で定義したように(『職業としての政治家』)、言葉で闘う政治リーダーにとっては、攻撃的かつ打たれ強い性格は必須アイテムである。しかし、そうした煽動家としての強い性格だけでは、強いリーダーにはなれない。強い個性は政治行動を持続させるための基盤でこそあれ、政策を実現するための決定的な資質あるいは政治能力ではない。ヴェーバーが使用した「デマゴーグ」という定義は政治家の性格を言い当てただけではなく、民主主義における政治リーダーに求められる必須の資質と能力を明らかにしていると理解しなければならないのである。それは、「デマゴギー」つまり政治的言説によって民衆を煽動する力(よく言えば、民意を結集する力)こそが、民主主義社会のリーダーに不可欠な資質だということを意味している。
民主主義とポピュリズムの境目
以上のように考えると、民主主義とは言葉巧みな政治家による民衆の「言論操作」あるいは「言論的搾取」のようにも見える。基本的にはそのとおりである。民主政治の構築と執行という局面における政治家と国民大衆との関係、および両者間の手続のあり方に関して見れば、「民主主義」と「ポピュリズム」に本質的な違いはない。
しかし、それにも拘らず、政策実現の局面では両者の間には天と地ほどの違いが生ずる可能性がある。民衆が政治リーダーらの言葉を信じて権力を委任した結果、図らずも大多数の民衆に不幸がもたらされたとき、人々はそれを「ポピュリズム」と呼ぶことに疑問を持たないだろう。つまり、民主主義とは主権者である国民の幸福を追求する方法論であるから、民意として選択した権力者およびその政策が自らの不幸につながったとき、国民はそれをもはや健全な民主主義と認めたくないからである。そのような状況のとき、主権者としての責任を負おうとしない民衆は「政治家に騙された」と嘆き、(自らが招いた)ポピュリズムの責任をポピュリストである政治リーダーたちに転嫁しようとするはずである。
果たして、そのような責任転嫁に妥当性はあるのだろうか。結果を見るまで、それが健全な民主主義なのか、あるいは誤った判断としてのポピュリズムなのかが分からないというのは、いかにも無責任な話である。国民自らに自由な判断が許されている政治社会体制であるならば、結果を見てから民主主義とポピュリズムを区別する態度はいかにも愚民的態度であると言わざるをえない。
民主主義とポピュリズムの間に、手続的に決定的な違いがないことはすでに述べた。違いは政治的な結果であるが、 民主主義における最終的な結果責任は、実は政治家にではなく、主権者である国民に存するのだ。つまりポピュリズムは、偏に主権者である国民自身の間違った判断がもたらす政治状況であると言える。君主制や階級社会における非民主的な政治状況であるなら、民衆は権力者に騙されたと呪詛する(あるいは、それが高ずれば革命を起こす)しかないかもしれないが、言論の自由に基づく普通選挙を基盤にした民主主義体制においては、民主主義を貫くもポピュリズムに堕するも、専ら私たち国民の判断に委ねられているということである。
独裁を招いた究極のポピュリズム
以上、民主主義とポピュリズムとの類縁性および本質的な相違について、いささか抽象的に述べてきた。以下は今日の日本社会のポピュリズム的状況をより明確に把握するために、歴史的事例を挙げて改めてポピュリズムの本質について考えてみよう。
人類史上典型的かつ最大のポピュリズムは、アドルフ・ヒトラーに独裁権を与えたドイツ国民の政治判断に拠るものだった。ヒトラーは1933年1月に権力を奪取すると、自らが仕掛けた世界大戦に敗北する1945年5月までの12年間、ドイツを名実ともに独裁支配することになる。それは、結果的には暴力と武力にものを言わせる独裁であったが、政権および独裁権奪取までの経緯が、実は極めて民主的な手続を踏んでいたという事実は、あまり知られていない。
ドイツにおける普通選挙の導入は意外と早く、19世紀後半のドイツ帝国時代にさかのぼる。もちろん、不完全とは言え民主的な政治が実現するのは1919年以降のワイマール共和国時代であるが、ヒトラー率いるナチ党(国家社会主義ドイツ労働者党)が登場するのは、まさにそのワイマール共和政期であった。ナチ党は当初、武力に頼るクーデターを企てたが、それが完全に失敗すると、(恒常的に国民から一定の支持を得ていた左翼勢力に対抗するために潜在的な暴力性を維持しながらも)地道な政党活動によって国民の支持を獲得することを目指すようになる。
しかし、1928年5月の総選挙までは得票率2%台と低迷し、国民の支持を広げることはまったくできなかった。そうしたなか、1929年の世界的な金融恐慌が、ヒトラーに大きな好機をもたらした。 金融恐慌後の1930年9月に実施された総選挙で、ナチ党は一挙に18.3%の支持を獲得したのである。ちなみに、当時のドイツの政治状況は小党乱立にあった。28年5月の選挙結果を受けて樹立された政府は、左翼のSPD(社会民主党、158議席)と保守派のDVP(ドイツ人民党、45議席)、有産階級を支持母体とするZentrum(中央党、62議席)、DDP(ドイツ民主党、25議席)ならびにBVP(バイエルン人民党、16議席)による大連立政権であった。それ以外にも十をこえる小党乱立の政治的混乱状況のなかで、ヒトラーは政権公約を「失業問題解消」と先の世界大戦の敗戦で「喪失した民族の誇りの回復」の二点に絞ることによって、単純明快な選挙キャンペーンを展開した。また、分かりやすい選挙公約と共に力を入れたのが、「強いリーダー」をアピールするための大々的なイメージ戦略であった。
ヒトラーは金融恐慌による不況に対して「何もできない」既成保守政党の無力ぶりを批判すると共に、左翼勢力の脅威を煽る一方で、自分なら「強いリーダー」として「強いドイツ」を復活することができると、さまざまな広報メディアを駆使して単純明快な言葉を使って訴えた。その結果が1930年の総選挙での躍進であり、さらには32年7月の総選挙での37.2%の得票であった。この選挙で比較第一党となることによって、ヒトラーは政権奪取を現実のものにしたのである。
1932年11月の選挙でも、ナチ党は33.0%を獲得し比較第一党の立場を守ったが、同時に左翼勢力も社会民主党20.4%(28年は29.8%)、共産党16.8%(28年は10.6%)というように相変わらず高い得票率を維持していた。つまり、ワイマール共和政末期は、資本家等の有産階級を支持母体とする中央党以外の中小の保守政党と、政権に関与してきた左翼勢力の社会民主党から一部の支持を奪ったナチ党と左翼勢力が拮抗する政治状況であったと言える。こうした政治的混沌にあってナチ党の33%の得票率は無視できない勢力であるという事実と、共産主義の脅威は相変わらず存在するという恐怖感が、中央党を初めとする保守政党をナチ党との連立に走らせたのである。
以上、非常に複雑かつ微妙な政治勢力の分布状況について述べてきたが、いずれにしても大衆の心を掴んだのは、既成政党にない「強いリーダーシップ」を表現したナチ党だった。たった四年の間に、得票率を2%台半ばから30%を上回る数字に押し上げた事実は、国民のナチ党への熱狂的な支持が生じたことを意味している。つまり、ここで改めて強調したいのは、さまざまな政治状況が複雑に絡み合ったとは言え、その後独裁体制を構築したヒトラーのナチ党は実は民主的な選挙によって権力を奪取したという事実である。そして、その背景には有権者のポピュリズム的熱狂があったことを忘れてはならない。
ヒトラー独裁を可能にしたもう一つの要因も、実は民主的な手続に基づいていた。1933年1月に合法的に宰相に就任したヒトラーは、早くも同じ年の3月には議会に所謂「全権委任法」を上程し、合法的な手続に基づいて可決成立させたのである。「全権委任法」とは、政府に四年間の期限付きながら、議会の承認なしにすべての行政執行権を与えるというものである。つまり、時限付きとは言え、政府、つまりはヒトラーに独裁権を付与するという法律である。ヒトラーはこの独裁法案を三分の二以上の賛成を得て可決させた、つまり民主的な議会において合法的に独裁権を獲得したのである。その背景には、33年3月の選挙において、ナチ党が43.9%の得票率を得た事実がある。絶対過半数こそ獲得できなかったものの、議会において「独裁権」を要求するのに十分な国民の支持だったということである。(「全権委任法」可決後、ヒトラーは合法的に議会の停止や労働組合の禁止等々の政策を実施することで民主主義を廃止し、自らの死まで時限を切らずに究極の独裁体制を敷いた。)
.
民主主義とポピュリズムの狭間にある民意
以上見てきたとおり、ヒトラーの独裁は民意に基づく民主的な手続によって現実のものとなってしまった。この歴史的事実は、民主国家に生きる私たちにとって極めて大きな教訓である。つまり、ファシズムやそれに類する全体主義的体制は、必ずしも民衆を抑圧する暴力装置だけがもたらすものではないということである。言い換えれば、私たちの自由を制限するファシズム的体制は、実は国民自身の自由な判断、つまり民主的な選挙によってもたらされる可能性が大いにあるということである。結果として社会の構成員である個々人の自由と平等なる権利、つまり基本的人権を侵犯する政治権力を、国民自らが進んで選択する政治状況こそがポピュリズムの本質なのである。
思えば、所謂バブル経済崩壊後の日本の調整型統治形態の行き詰まりのなか、党内の支持基盤に拠ることなく、国民の熱狂的な支持だけに権力の正統性を求めた小泉首相は、近代日本の政治史上初の「大統領型」ポピュリストだったと言える。単純明快な「劇場型ワンフレーズ・ポリティクス」は、ポピュリストに共通する政治手法でもある。しかし、ポピュリストの登場が即ちポピュリズムの台頭を意味する、と考えるのは拙速である。民主主義とポピュリズムの境目は、直接国民に訴えかけるポピュリストの政策が、広く国内外の社会の福祉に寄与するものか否かの狭間にあり、それを判断するのは国民自身であるということなのだ。一つだけ確実に言えることは、ヒトラーの場合がそうだったように、ポピュリストが仕掛ける「熱狂」は国民にとって冷静な判断を誤らせる大きな危険要素であるということである。先のフランス大統領選挙の第一回投票でフランス国民戦線のマリーヌ・ルペン党首が、経済不況と失業問題の元凶を移民に押し付けて、国民の偏狭なナショナリズムを煽ることによって18%という高い得票率を得たことを、フランスや他の欧州諸国の政治学者たちはポピュリズムの台頭と看做している(5月8日付け朝日新聞参照)。近代民主主義の発祥の地でありながら、ナチズムという究極かつ最悪のポピュリズムを経験したヨーロッパの専門家はさすがに慧眼である。裏を返せば、民主主義には常にポピュリズムの危険性が潜んでいるということなのである。
私たちが自分たちの幸福のためにより良質の民主主義を実現するか、あるいは自らと他者の自由と平等なる権利を奪うポピュリズムに陥るかは、偏に私たちに付与されている権力委任権、つまり選挙で如何なる民意を形成するかにかかっている。「決断する政治」を標榜する「強い政治リーダー」の歯切れのよい政治姿勢と独善的な政策が、本当に私たちの民主主義を育むものなのか、それとも民主主義を破壊する排他的なポピュリズムにすぎないのかを判断する責任が、主権者である私たち自身に委ねられていることだけは確かである。願わくは、私たち主権者が「愚民」に堕することのないように。
ポピュリズムと言われる政治手法が、
勢力を増して来ています。
それと、民主政治は、どう対抗するのだろうか?!
ネットで調べて、このサイトに着きました。
http://www.hino.meisei-u.ac.jp/nihonbun/lecture/062.html
私たちは、目先の小気味よい呼びかけに反応しがちです。
ですが、それが、どういう結果に繋がって来たか・・・?!
この文で、学び、考えさせて頂きたい!!
たいと思います。
読みやすくする為に、
文中の文字に色も付けさせて頂きました。
【民主主義とポピュリズム・・・明星大学教授 服部 裕】
民主主義における政治リーダーのあり方
「決められない政治」あるいは「ぶれる政治家」などというように、昨今の日本では、国政を預かる既成政党の政治に対する批判が高まっている。所謂政治不信であるが、民主主義の場合、極度の政治不信は往々にしてポピュリズムを引き起こすことがある。それは、国民大衆が国難にあっても決断できない既成政治を見限り、より単純明快な主張を掲げる所謂「強いリーダー」を待望する社会心理に支えられるのが一般的である。
昨今の日本の政治状況で言えば、大阪市長や東京都知事に対するリーダー待望論が、その代表的な事例である。「物事を決められない政党政治」にはもはや何も期待できないので、より決断力と実行力があるように見える地方自治体の首長に大きな期待が寄せられるという図式である。実際に、領土問題が取りざたされている小さな島をある地方自治体が購入するとか、全職員に入れ墨の有無を問う調査を実施したりとかという行政手法が示すとおり、そのトップダウン式のやり方は、政府内、与党内そして国会と合議を重ねて物事を決定する国政のやり方に比べて、かなり歯切れの良い「強いリーダー」のイメージを演出していると言える。
では、なぜ地方自治体の首長はより強力なリーダーシップのパフォーマンスを演出しやすいのだろうか。その答えは、中央政府と地方自治における権力の委任形態の違いにあると考えられる。簡単に言えば、地方自治体の首長が住民の直接投票によって選出されて行政府を構築するのとは異なり、中央政府の長つまり内閣総理大臣とそれが任命する諸大臣は国民が直接選出することができないということである。後者が議院内閣制に基づく一方で、前者は言わば「大統領制」に近い権力委任の形態を取っているのである。したがって、政策実現の成否はともかくも、アメリカの「大統領」に近い首長は行政の執行権(予算や人事、さらには専決処分権等々)と議会決議に対する拒否権および事実上の法案請求権を握っているのに反して、内閣総理大臣はまずは閣議(その背後には行政専門職としての官僚が目付役として存在する)、そして与党の合意なくしては、議案の一つも国会に上程することができない。本来、原理的には大統領(首長)の権限と議会の権限が分立し拮抗しあう「大統領制(=二元代表制)」の方が、民意が一元的に委任される「議院内閣制(=一元代表制)」より、国民からの権力の委任は曖昧なはずなのに、上述のように首長が強い行政権を所有するため、見た目の政治的リーダーシップは地方の首長の方がより強く見えるのである。
つまり、昨今の内閣総理大臣のリーダーシップ欠如は、実は戦後の民主主義国家としての日本の政治構造そのものに由来していると考えなければならない。現在の野田総理大臣のみならず、戦後の歴代総理は党派の別なくみな多かれ少なかれ調整型のリーダーであり、強力なトップダウンなど誰一人実行できなかったと言える。(比較的明確なリーダーシップを発揮しようとした田中角栄のような総理大臣は、道半ばで失脚の憂き目を見ている。弱い党内基盤にも拘らず長期政権を実現した小泉首相だけが、例外的に国民の人気を支えに強力なリーダーシップを発揮したポピュリスト的首相だったが、その政治力は「郵政民営化」だけに限定されていた。)
しかし、大統領的な性格を有する首長と雖も、みながみな大阪市長や東京都知事のように強面のリーダーとはなりえない。強いリーダー像を演出するには、もちろん並外れて強烈なキャラクターが必要であろうが、キャラクターだけで政治的リーダーシップを発揮できる訳でもないからである。マックス・ヴェーバーが民主制下の「政治家」を「デマゴーグ(民衆煽動家)」という言葉で定義したように(『職業としての政治家』)、言葉で闘う政治リーダーにとっては、攻撃的かつ打たれ強い性格は必須アイテムである。しかし、そうした煽動家としての強い性格だけでは、強いリーダーにはなれない。強い個性は政治行動を持続させるための基盤でこそあれ、政策を実現するための決定的な資質あるいは政治能力ではない。ヴェーバーが使用した「デマゴーグ」という定義は政治家の性格を言い当てただけではなく、民主主義における政治リーダーに求められる必須の資質と能力を明らかにしていると理解しなければならないのである。それは、「デマゴギー」つまり政治的言説によって民衆を煽動する力(よく言えば、民意を結集する力)こそが、民主主義社会のリーダーに不可欠な資質だということを意味している。
民主主義とポピュリズムの境目
以上のように考えると、民主主義とは言葉巧みな政治家による民衆の「言論操作」あるいは「言論的搾取」のようにも見える。基本的にはそのとおりである。民主政治の構築と執行という局面における政治家と国民大衆との関係、および両者間の手続のあり方に関して見れば、「民主主義」と「ポピュリズム」に本質的な違いはない。
しかし、それにも拘らず、政策実現の局面では両者の間には天と地ほどの違いが生ずる可能性がある。民衆が政治リーダーらの言葉を信じて権力を委任した結果、図らずも大多数の民衆に不幸がもたらされたとき、人々はそれを「ポピュリズム」と呼ぶことに疑問を持たないだろう。つまり、民主主義とは主権者である国民の幸福を追求する方法論であるから、民意として選択した権力者およびその政策が自らの不幸につながったとき、国民はそれをもはや健全な民主主義と認めたくないからである。そのような状況のとき、主権者としての責任を負おうとしない民衆は「政治家に騙された」と嘆き、(自らが招いた)ポピュリズムの責任をポピュリストである政治リーダーたちに転嫁しようとするはずである。
果たして、そのような責任転嫁に妥当性はあるのだろうか。結果を見るまで、それが健全な民主主義なのか、あるいは誤った判断としてのポピュリズムなのかが分からないというのは、いかにも無責任な話である。国民自らに自由な判断が許されている政治社会体制であるならば、結果を見てから民主主義とポピュリズムを区別する態度はいかにも愚民的態度であると言わざるをえない。
民主主義とポピュリズムの間に、手続的に決定的な違いがないことはすでに述べた。違いは政治的な結果であるが、 民主主義における最終的な結果責任は、実は政治家にではなく、主権者である国民に存するのだ。つまりポピュリズムは、偏に主権者である国民自身の間違った判断がもたらす政治状況であると言える。君主制や階級社会における非民主的な政治状況であるなら、民衆は権力者に騙されたと呪詛する(あるいは、それが高ずれば革命を起こす)しかないかもしれないが、言論の自由に基づく普通選挙を基盤にした民主主義体制においては、民主主義を貫くもポピュリズムに堕するも、専ら私たち国民の判断に委ねられているということである。
独裁を招いた究極のポピュリズム
以上、民主主義とポピュリズムとの類縁性および本質的な相違について、いささか抽象的に述べてきた。以下は今日の日本社会のポピュリズム的状況をより明確に把握するために、歴史的事例を挙げて改めてポピュリズムの本質について考えてみよう。
人類史上典型的かつ最大のポピュリズムは、アドルフ・ヒトラーに独裁権を与えたドイツ国民の政治判断に拠るものだった。ヒトラーは1933年1月に権力を奪取すると、自らが仕掛けた世界大戦に敗北する1945年5月までの12年間、ドイツを名実ともに独裁支配することになる。それは、結果的には暴力と武力にものを言わせる独裁であったが、政権および独裁権奪取までの経緯が、実は極めて民主的な手続を踏んでいたという事実は、あまり知られていない。
ドイツにおける普通選挙の導入は意外と早く、19世紀後半のドイツ帝国時代にさかのぼる。もちろん、不完全とは言え民主的な政治が実現するのは1919年以降のワイマール共和国時代であるが、ヒトラー率いるナチ党(国家社会主義ドイツ労働者党)が登場するのは、まさにそのワイマール共和政期であった。ナチ党は当初、武力に頼るクーデターを企てたが、それが完全に失敗すると、(恒常的に国民から一定の支持を得ていた左翼勢力に対抗するために潜在的な暴力性を維持しながらも)地道な政党活動によって国民の支持を獲得することを目指すようになる。
しかし、1928年5月の総選挙までは得票率2%台と低迷し、国民の支持を広げることはまったくできなかった。そうしたなか、1929年の世界的な金融恐慌が、ヒトラーに大きな好機をもたらした。 金融恐慌後の1930年9月に実施された総選挙で、ナチ党は一挙に18.3%の支持を獲得したのである。ちなみに、当時のドイツの政治状況は小党乱立にあった。28年5月の選挙結果を受けて樹立された政府は、左翼のSPD(社会民主党、158議席)と保守派のDVP(ドイツ人民党、45議席)、有産階級を支持母体とするZentrum(中央党、62議席)、DDP(ドイツ民主党、25議席)ならびにBVP(バイエルン人民党、16議席)による大連立政権であった。それ以外にも十をこえる小党乱立の政治的混乱状況のなかで、ヒトラーは政権公約を「失業問題解消」と先の世界大戦の敗戦で「喪失した民族の誇りの回復」の二点に絞ることによって、単純明快な選挙キャンペーンを展開した。また、分かりやすい選挙公約と共に力を入れたのが、「強いリーダー」をアピールするための大々的なイメージ戦略であった。
ヒトラーは金融恐慌による不況に対して「何もできない」既成保守政党の無力ぶりを批判すると共に、左翼勢力の脅威を煽る一方で、自分なら「強いリーダー」として「強いドイツ」を復活することができると、さまざまな広報メディアを駆使して単純明快な言葉を使って訴えた。その結果が1930年の総選挙での躍進であり、さらには32年7月の総選挙での37.2%の得票であった。この選挙で比較第一党となることによって、ヒトラーは政権奪取を現実のものにしたのである。
1932年11月の選挙でも、ナチ党は33.0%を獲得し比較第一党の立場を守ったが、同時に左翼勢力も社会民主党20.4%(28年は29.8%)、共産党16.8%(28年は10.6%)というように相変わらず高い得票率を維持していた。つまり、ワイマール共和政末期は、資本家等の有産階級を支持母体とする中央党以外の中小の保守政党と、政権に関与してきた左翼勢力の社会民主党から一部の支持を奪ったナチ党と左翼勢力が拮抗する政治状況であったと言える。こうした政治的混沌にあってナチ党の33%の得票率は無視できない勢力であるという事実と、共産主義の脅威は相変わらず存在するという恐怖感が、中央党を初めとする保守政党をナチ党との連立に走らせたのである。
以上、非常に複雑かつ微妙な政治勢力の分布状況について述べてきたが、いずれにしても大衆の心を掴んだのは、既成政党にない「強いリーダーシップ」を表現したナチ党だった。たった四年の間に、得票率を2%台半ばから30%を上回る数字に押し上げた事実は、国民のナチ党への熱狂的な支持が生じたことを意味している。つまり、ここで改めて強調したいのは、さまざまな政治状況が複雑に絡み合ったとは言え、その後独裁体制を構築したヒトラーのナチ党は実は民主的な選挙によって権力を奪取したという事実である。そして、その背景には有権者のポピュリズム的熱狂があったことを忘れてはならない。
ヒトラー独裁を可能にしたもう一つの要因も、実は民主的な手続に基づいていた。1933年1月に合法的に宰相に就任したヒトラーは、早くも同じ年の3月には議会に所謂「全権委任法」を上程し、合法的な手続に基づいて可決成立させたのである。「全権委任法」とは、政府に四年間の期限付きながら、議会の承認なしにすべての行政執行権を与えるというものである。つまり、時限付きとは言え、政府、つまりはヒトラーに独裁権を付与するという法律である。ヒトラーはこの独裁法案を三分の二以上の賛成を得て可決させた、つまり民主的な議会において合法的に独裁権を獲得したのである。その背景には、33年3月の選挙において、ナチ党が43.9%の得票率を得た事実がある。絶対過半数こそ獲得できなかったものの、議会において「独裁権」を要求するのに十分な国民の支持だったということである。(「全権委任法」可決後、ヒトラーは合法的に議会の停止や労働組合の禁止等々の政策を実施することで民主主義を廃止し、自らの死まで時限を切らずに究極の独裁体制を敷いた。)
.
民主主義とポピュリズムの狭間にある民意
以上見てきたとおり、ヒトラーの独裁は民意に基づく民主的な手続によって現実のものとなってしまった。この歴史的事実は、民主国家に生きる私たちにとって極めて大きな教訓である。つまり、ファシズムやそれに類する全体主義的体制は、必ずしも民衆を抑圧する暴力装置だけがもたらすものではないということである。言い換えれば、私たちの自由を制限するファシズム的体制は、実は国民自身の自由な判断、つまり民主的な選挙によってもたらされる可能性が大いにあるということである。結果として社会の構成員である個々人の自由と平等なる権利、つまり基本的人権を侵犯する政治権力を、国民自らが進んで選択する政治状況こそがポピュリズムの本質なのである。
思えば、所謂バブル経済崩壊後の日本の調整型統治形態の行き詰まりのなか、党内の支持基盤に拠ることなく、国民の熱狂的な支持だけに権力の正統性を求めた小泉首相は、近代日本の政治史上初の「大統領型」ポピュリストだったと言える。単純明快な「劇場型ワンフレーズ・ポリティクス」は、ポピュリストに共通する政治手法でもある。しかし、ポピュリストの登場が即ちポピュリズムの台頭を意味する、と考えるのは拙速である。民主主義とポピュリズムの境目は、直接国民に訴えかけるポピュリストの政策が、広く国内外の社会の福祉に寄与するものか否かの狭間にあり、それを判断するのは国民自身であるということなのだ。一つだけ確実に言えることは、ヒトラーの場合がそうだったように、ポピュリストが仕掛ける「熱狂」は国民にとって冷静な判断を誤らせる大きな危険要素であるということである。先のフランス大統領選挙の第一回投票でフランス国民戦線のマリーヌ・ルペン党首が、経済不況と失業問題の元凶を移民に押し付けて、国民の偏狭なナショナリズムを煽ることによって18%という高い得票率を得たことを、フランスや他の欧州諸国の政治学者たちはポピュリズムの台頭と看做している(5月8日付け朝日新聞参照)。近代民主主義の発祥の地でありながら、ナチズムという究極かつ最悪のポピュリズムを経験したヨーロッパの専門家はさすがに慧眼である。裏を返せば、民主主義には常にポピュリズムの危険性が潜んでいるということなのである。
私たちが自分たちの幸福のためにより良質の民主主義を実現するか、あるいは自らと他者の自由と平等なる権利を奪うポピュリズムに陥るかは、偏に私たちに付与されている権力委任権、つまり選挙で如何なる民意を形成するかにかかっている。「決断する政治」を標榜する「強い政治リーダー」の歯切れのよい政治姿勢と独善的な政策が、本当に私たちの民主主義を育むものなのか、それとも民主主義を破壊する排他的なポピュリズムにすぎないのかを判断する責任が、主権者である私たち自身に委ねられていることだけは確かである。願わくは、私たち主権者が「愚民」に堕することのないように。
実は、友人が、私の家のポストに
いつも、入れといて下さる「通信紙」
ヒューマン人権ネットワーク八幡NEWS
に載っていた
作家で活動家の 雨宮処凛さんをご紹介します。
※ 人材バンクネット HP です。
http://mainichi.jp/articles/20150804/mog/00m/040/003000c
雨宮さんは、今年、33歳。
今の若い人たちが、抱えている、悩みや混迷を
勉強したくて、UP します。
40歳年下の若い人の置かれている状況・・・
私の子ども時代は、戦後の混乱と復興、
思春期・青年期は
高度経済成長期で、
5年先の見通しが見えて、
希望の持てた社会だったように思います。
今は、どうか・・・?!
雨宮処凛さんの思いを読んで、
今の日本社会の問題点を、学んで行きたいです。m(_ _)m
失われた20年インタビュー
作家・雨宮処凛さん・・・
格差が、同じ日本で言葉が通じないくらい広がった
2015年8月4日
作家の雨宮処凛さん=東京都千代田区で2015年7月16日、内藤絵美撮影
フリーターとして働いた苦しい経験から非正規労働の救いのない状況、貧困を訴え続けている作家の雨宮処凛さん。「同じ日本に住んでいて言葉が通じないぐらいに格差が広がってきている。生活意識も何もかも全部違って、格差の上位の人と下の人たちで、一つも共感できるところがないふうになっている。そういう社会ってちょっと怖い」と話す。【聞き手・尾村洋介/デジタル報道センター】
【徹底総括】失われた20年 変容する日本の雇用はどこへ .
<失われた20年>ジャーナリスト小林美希さんインタビュー「非正規を全体に広げたのは大きな誤りだった」 .
<失われた20年>大田弘子・元経済担当相インタビュー「政治がメッセージ作れず、遠のいた構造改革」 .
<失われた20年>藤井裕久・元財務相インタビュー「恵まれない人に目を向けるのが政治の責任」 .
<座談会>失われた20年に学生たちは何を思う? .
−−雨宮さんがフリーターになったいきさつを教えてください。
雨宮さん 美大に進学したくて1993年に東京に出てきて、美大専門の予備校に行きました。バブル崩壊は何となく知ってたけど、東京に出た時はまだジュリアナ・ブームのような感じで、すごいバブルっぽい雰囲気がありました。94年に進学を諦めたんですが、その時に「就職氷河期」といわれていて、どうしたら就職できるかわからないし、まあアルバイトを始めようと思いました。実際に始めると、時給はどんどん下がっていって、バイト先でも「すごく悪い時にフリーターになったね」って言われましたね。
−−当面の仕事のような意識だったのでしょうか。
雨宮さん 最初はそんな感じでしたけど、始めて半年ぐらいたったら、もう、これ絶対逃れられないんだなっていうのに気づきましたね。95年ぐらいの時、自分の周りの友達と、「うちらは親が死んだらホームレスだよね」「野垂れ死にだよね」ということは冗談交じりに話してたんです。アルバイトだから風邪で一回休んだだけで家賃を滞納してしまったり、ガスや電気が止まったりするので、そのたびに親に電話し、泣きついてお金を借りていましたので。もう正社員にはほぼなれないし、なり方もわからないし。綱渡りの生活をしていた。世の中では自由でいたくてやっているフリーターというイメージがすごく強かったけど、自分たちはまったく自由だと思わなかったですね。でも、上の世代からは甘えてだらしがなくて怠けてるって言われるので、私は甘えているからこういう生活なんだろう、何かが自分に足りないからこうなってるんだって思ってました。社会が悪いとは一切思わなかったです。
−−すれすれの生活ですね。
雨宮さん バイトもしょっちゅうクビになるんです。本当は違法な解雇だったりするんですけど、当時は人格否定されたように思っていました。単純な仕事をクビになると結構きついんです。本当に誰にもできる、クソつまらないような仕事でさえ必要とされないというのは、一番底辺から蹴り落とされるようなところがありました。
−−何かよりどころはあったのでしょうか?
雨宮さん 私は一時期、右翼団体に入っていました。飲食店で働いていると、日本人のフリーターに比べて韓国人のほうが時給は安いのに働き者だから取り換えたいとか、そういうことを言われるんですよ。「自分は日本の底辺にいて、外国人労働者とまったく変わらない。もし外国人労働者と自分を区別するものがあるなら、それって日本人であることしかない」みたいな、過剰に日本人であるってことにすがっていきました。学生時代にバブルだったので、ものすごく受験勉強が厳しくて、受験戦争で傷つけられても、すべて頑張れば報われるという戦後日本の一番大切にしていた「神話」みたいなものを信じてきた。けれども、自分が社会に出たころ、「バブルが崩壊したから今までのことは全部うそになりました」と言われた気がして、すごくびっくりした。大人とか学校から教わってきたことが、たかが経済によってうそになるんだ、みたいな。それで後で思うんですが、天皇制はバブルで崩れなかったので、経済の停滞とかで崩れない揺るぎない価値観が欲しいという気持ちがありました。フリーターとして東京で1人暮らしをしていると、職場がなかったり、職場があってもしょっちゅうクビになったりするので、そこに帰属意識が持てないし、職場が変わるので友達もできない。学校にいけない、企業社会にも入れない、もちろん地域社会もない、どこにも居場所がなくて。そうなると、もう一気に国家しか居場所がないような感覚がありました。教育にうそをつかれたっていう被害者意識があったので、学校で教えてくれない靖国史観的なものが、自分の中にストンと入ってきた。私が入っていた右翼団体には同じような人が入っていました。
−−その団体が、当時の非常に不安定な状況を支えてくれることはあったんでしょうか?
雨宮さん 一時的にはありました。私を唯一必要としてくれる居場所でしたが、自分たちの苦しい現実から目をそらすために、アメリカがどうとか、そんな大きな話をしていた。自分たちの生活を何とかしようとか、自分たちの労働や生活の状況を問題にするということは一切なかったですね。逆に言うと、自分たちは日本人で恵まれているんだということを再確認し合う会話がずーっと続くというような、そんな感じでした。
−−今から考えると、どういうことだったんでしょう?
雨宮さん お前は悪くないよって誰かに言ってほしかったんですね。右翼の大人は、今の世の中で若者が鬱屈して生きづらいのは、日本国憲法が押し付け憲法だから悪い、アメリカと戦後民主主義が悪いと説明するんですが、その意味がわからなくても、自分が悪いと思わなくていいというところで自分の生きづらさをごまかすことができた。それではまりました。
−−右翼をやめたのはどうしてですか。
雨宮さん 私、そのころ総理大臣の名前も知らないくらいの大ばかだったんですけど、右翼の人が時事問題から何から教えてくれました。でも、ある程度物事がわかってきて自分の頭で考えるようになったら、私は全然、右翼じゃないな、右翼の人の言っていることは自分の考えとは違うなと思うようになり、やめました。
−−雨宮さんが「プレカリアート」(不安定な労働者)という問題に取り組み始めたのはいつごろからですか?
雨宮さん 2006年ごろですね。00年に脱フリーターして文筆業になって、不安定なプレカリアートという言葉をたまたまネットで見つけて引っかかるものを感じて、メーデーの集会に行った。そこで、新自由主義と生きづらさや自殺の問題の関係とか、日本の労働政策がどれほど変わってきたかというのを初めて知ったんですね。それまで、自分の周りの人たちがずいぶん自殺していたんですが、その背景には、個人の問題じゃなくて、何か構造的な問題、社会が関わっているんじゃないかとずっと考えていたときだったので、すっと理解できた。その十数年前からの労働政策や新自由主義で格差が広がり、普通に生き、普通に働くってことが特権階級にしか許されなくなったというような状況がある。自己責任などと言われて働けない自分を責めて、「すみません」って遺書とかで謝りながら死んでいった人もいます。どんどん労働市場が過酷になって、ちょっと不器用な人たちの居場所がなくなり、こんな自分が生きてちゃいけないと思って死んでいくような、そういうことがあった。集会で話を聞いて、その人たちのせいで死んだんじゃなく、人を生きさせないようなシステムがもう作られてたんだなと思った。「原因がやっとわかった。ここに敵がいたのか」みたいな感じでした。それをなくさないと私たちの生きづらさは絶対になくならないと思うと、猛然と腹が立った。
−−敵といってもシステムですか。
雨宮さん 当時は小泉政権でした。小泉さんは敵としてはある意味完璧というか、自己責任という言葉もそうですし、既得権益である正社員層からごっそり盗んで、非正規の人が何かおこぼれがくるんじゃないかと錯覚させるようなやり方が巧みだった。小泉さん個人というよりは、小泉さんが進めている労働法制の規制緩和などの政策が自分たちを追い詰めている。本当をいえば、それ以前からの政策で、派遣法ができたときぐらいから自民党の政治が進めてきた方向が、若者の貧困を個人の問題にして企業の利益を最大化していく。そこにみんな気づいて怒りだしたんです。
−−経済の停滞が始まって、企業は非正規を採用してコストを低くしました。それはどのように見えていましたか。
雨宮さん プレカリアートの問題を知ってからは、やっぱり企業は自分たちの利益のために人件費の削減をやっていこうとしているんだと、びっくりしました。日本の企業を誇りに思っているところがあったのに、名だたる大企業が非正規を使い捨てにしたために、派遣労働を経由してホームレスになっている人たちが山ほど生まれた。当時は景気が良いと言われていたけれど、自分たちにはその恩恵はないし、すごく苦しい人が増えているし、大企業の派遣で働きながらも月収10万円ぐらいの人もいた。まったく自分たちが思っていたのとは違う労働世界が広がっていて、その人たちはもう一生はい上がれないようなシステムになっちゃっている。それが始まったのがちょうど私たちの世代くらいからなんです。06年に私は31歳でした。同世代のフリーターは30代を超えて、仕事がなくなり始めてましたね。30の壁を超えられないとか、日本には30歳を超えたフリーターの行き場がないということにも気づいた。
−−企業の言い分についてはどう思いますか。
雨宮さん 結局、グローバル競争を勝ち抜いていくためには人件費を安くして当然じゃないか。一貫してそれです。企業は営利活動を目的としているので、企業を責めてもしょうがない。そこは政治がある程度歯止めをかけないと。営利活動が行き過ぎない雇用形態だとか、あっさりホームレス化しないような生活ができる賃金を払うという法規制は、どこの国でもやっている。日本は働いた賃金だけで生きていけっていうかなりの自己責任社会であるうえに、そこを不安定化、低賃金化されると、働く人に不利にできているので、みんなが不安定になってしまう。雇用保険も失業者の7割以上が受けていない上に住宅政策もないので、失業したらホームレスになっちゃう。
−−80年代から雇用の流動化が進んできましたが、不安定になる人を支える手立てをあんまり考えてこなかったんですね。
雨宮さん そうです。求職者への支援制度とかセーフティーネット的なものがやっとできたのは派遣村以降で、それもあまり使い勝手がいいとはいえないんです。本当は86年に派遣法ができたぐらいからやっておかないといけなかった。00年代に時限爆弾が爆発するように問題化した時には、まだ何もなかった。
−−プレカリアートの人たちに日本が豊かだという感覚は?
雨宮さん まったくないんじゃないですか。90年代は、自分たちが集まって話すときは常にうっすらと「豊かだけど生きづらい」と意識していました。それが00年代に入ると「生きづらいうえに貧乏、カネがない」というのを前提に語られるようになった。だから、一億総中流的なものって、言葉としては05年ぐらいまで生きていた気がします。90年代も自分たちは貧困ライン以下の生活をしていたのに、日本は経済大国という全体の幻想の中で、本当に気づくのが遅れてしまった。当事者は、社会に出たことがないから気づかない。あの時、誰か一人でも、気づいてくれたらと思います。今でこそ、若者の貧困が注目され、非正規の問題に取り組んでくれる人は増えましたけれどね。メディアに問題として発見されたから、認識が改まったってことですよね。
−−今現在の状況はどう見ていますか。
雨宮さん どんどん悪くなっていると思いますね。この前の国民生活基礎調査で、生活が苦しいという人が62・4%と過去最多でした。だから、アベノミクスって何なの、ってことです。年収200万円以下の人が増え、平均年収も下がっています。生活保護受給層は200万人をずっと突破しています。
−−リーマン・ショックの時、緩やかに回復していた景気が急速に悪化して、「派遣切り」などが表面化しました。こうしたことがまた起きる際の備えには何が必要ですか。
雨宮さん 自衛する方法としては制度を知っておくことですかね。労働組合が関われば、寮を追い出されないようにする交渉ができるので、フリーターでも入れる組合を知っておけばいい。あとは、最低限の生活保護に関する知識とか、住宅手当や求職者の支援制度もあります。使えるものは結構あるんですが、それがまったく周知されてない。日本ではそういう生きるか死ぬかにかかわる情報が全然知られてない。
−−どこを変えればいいのでしょうか?
雨宮さん 最低賃金を上げるとか、非正規にいろんな保障をつけるとか、過労死しない労働時間規制とか、そういう個別の小さな政策でできることってちゃんとあります。でも、日本社会がこの格差に対してまひしている感じがあるように思えるんです。最初はみんなすごいショックを受けて聞いてくれたんですが、今は誰も驚かないし、そういう社会だからしょうがないよね、それがグローバリズムに対応する先進国の宿命でしょう、とでもいうようなものを感じるんです。同じ日本に住んでいて言葉が通じないぐらいに格差が広がっていて、生活意識も何もかも全部違って、格差の上位の人と下の人たちで、一つも共感できるところがないふうになっている。そういう社会ってちょっと怖い。そういう相手を助けようとは誰も思わないだろうし、話を聞こうともしない。言葉も通じない怠け者は自己責任だと思ったら、社会保障の分配の対象にするのにも反対すると思うんですね。そういうふうになってきている感じがする。
−−これから先の展望はどうでしょうか?
雨宮さん 自分たちの世代は自分を「絶滅危惧種」って呼ぶようになってきています。結婚して子供を残せない、種を残せないから、そのまま絶滅していくだけの運命という意味です。今住んでいる6畳一間のアパートとかにみんな居続ける。フリーターとか非正規で働いている人たちはその家賃も払えなくなってくると思う。川崎市で起きた簡易宿泊所の火事では、あれが自分たちの未来の姿じゃないかというか、ああいうところで自分たちの世代がどんどん孤独死したり、火事で死んだり、そういう場所に行きつくしかないんじゃないかとすごく感じました。
−−5年先、10年先にやっていきたいことは何ですか。
雨宮さん 自分の世代のこの問題が、何か運動とかすれば解決とか決着というか、どこかに着地するのかと思っていたんですね。雇用があまりにも流動化したことが原因だから、セーフティーネットが必要だ、彼らが悪いわけじゃないんだという認識が社会的にも広まって、どこかに決着の地点があると思ったけれど、10年たってもまったくない。だから、自分の世代の問題として、どこかで落とし前をつけるまではこの問題からは離れられない。10年前は若者の貧困だったけど、今はもう若者じゃない。中年になっていて、それがどんどん初老になり、高齢者になっていく。この世代がどのへんで救われるのかが、ものすごく重要だと思っています。
■あまみや・かりん 1975年、北海道生まれ。高校卒業後、パンクロック歌手、右翼活動家などを経て作家に。2000年、「生き地獄天国」でデビュー。若者の生きづらさをテーマにした著作を発表している。著書に「プレカリアート」「雨宮処凛の闘争ダイアリー」など。「生きさせろ!難民化する若者たち」で日本ジャーナリスト会議賞受賞。「反貧困ネットワーク」世話人。最新刊に「14歳からの戦争のリアル」。
いつも、入れといて下さる「通信紙」
ヒューマン人権ネットワーク八幡NEWS
に載っていた
作家で活動家の 雨宮処凛さんをご紹介します。
※ 人材バンクネット HP です。
http://mainichi.jp/articles/20150804/mog/00m/040/003000c
雨宮さんは、今年、33歳。
今の若い人たちが、抱えている、悩みや混迷を
勉強したくて、UP します。
40歳年下の若い人の置かれている状況・・・
私の子ども時代は、戦後の混乱と復興、
思春期・青年期は
高度経済成長期で、
5年先の見通しが見えて、
希望の持てた社会だったように思います。
今は、どうか・・・?!
雨宮処凛さんの思いを読んで、
今の日本社会の問題点を、学んで行きたいです。m(_ _)m
失われた20年インタビュー
作家・雨宮処凛さん・・・
格差が、同じ日本で言葉が通じないくらい広がった
2015年8月4日
作家の雨宮処凛さん=東京都千代田区で2015年7月16日、内藤絵美撮影
フリーターとして働いた苦しい経験から非正規労働の救いのない状況、貧困を訴え続けている作家の雨宮処凛さん。「同じ日本に住んでいて言葉が通じないぐらいに格差が広がってきている。生活意識も何もかも全部違って、格差の上位の人と下の人たちで、一つも共感できるところがないふうになっている。そういう社会ってちょっと怖い」と話す。【聞き手・尾村洋介/デジタル報道センター】
【徹底総括】失われた20年 変容する日本の雇用はどこへ .
<失われた20年>ジャーナリスト小林美希さんインタビュー「非正規を全体に広げたのは大きな誤りだった」 .
<失われた20年>大田弘子・元経済担当相インタビュー「政治がメッセージ作れず、遠のいた構造改革」 .
<失われた20年>藤井裕久・元財務相インタビュー「恵まれない人に目を向けるのが政治の責任」 .
<座談会>失われた20年に学生たちは何を思う? .
−−雨宮さんがフリーターになったいきさつを教えてください。
雨宮さん 美大に進学したくて1993年に東京に出てきて、美大専門の予備校に行きました。バブル崩壊は何となく知ってたけど、東京に出た時はまだジュリアナ・ブームのような感じで、すごいバブルっぽい雰囲気がありました。94年に進学を諦めたんですが、その時に「就職氷河期」といわれていて、どうしたら就職できるかわからないし、まあアルバイトを始めようと思いました。実際に始めると、時給はどんどん下がっていって、バイト先でも「すごく悪い時にフリーターになったね」って言われましたね。
−−当面の仕事のような意識だったのでしょうか。
雨宮さん 最初はそんな感じでしたけど、始めて半年ぐらいたったら、もう、これ絶対逃れられないんだなっていうのに気づきましたね。95年ぐらいの時、自分の周りの友達と、「うちらは親が死んだらホームレスだよね」「野垂れ死にだよね」ということは冗談交じりに話してたんです。アルバイトだから風邪で一回休んだだけで家賃を滞納してしまったり、ガスや電気が止まったりするので、そのたびに親に電話し、泣きついてお金を借りていましたので。もう正社員にはほぼなれないし、なり方もわからないし。綱渡りの生活をしていた。世の中では自由でいたくてやっているフリーターというイメージがすごく強かったけど、自分たちはまったく自由だと思わなかったですね。でも、上の世代からは甘えてだらしがなくて怠けてるって言われるので、私は甘えているからこういう生活なんだろう、何かが自分に足りないからこうなってるんだって思ってました。社会が悪いとは一切思わなかったです。
−−すれすれの生活ですね。
雨宮さん バイトもしょっちゅうクビになるんです。本当は違法な解雇だったりするんですけど、当時は人格否定されたように思っていました。単純な仕事をクビになると結構きついんです。本当に誰にもできる、クソつまらないような仕事でさえ必要とされないというのは、一番底辺から蹴り落とされるようなところがありました。
−−何かよりどころはあったのでしょうか?
雨宮さん 私は一時期、右翼団体に入っていました。飲食店で働いていると、日本人のフリーターに比べて韓国人のほうが時給は安いのに働き者だから取り換えたいとか、そういうことを言われるんですよ。「自分は日本の底辺にいて、外国人労働者とまったく変わらない。もし外国人労働者と自分を区別するものがあるなら、それって日本人であることしかない」みたいな、過剰に日本人であるってことにすがっていきました。学生時代にバブルだったので、ものすごく受験勉強が厳しくて、受験戦争で傷つけられても、すべて頑張れば報われるという戦後日本の一番大切にしていた「神話」みたいなものを信じてきた。けれども、自分が社会に出たころ、「バブルが崩壊したから今までのことは全部うそになりました」と言われた気がして、すごくびっくりした。大人とか学校から教わってきたことが、たかが経済によってうそになるんだ、みたいな。それで後で思うんですが、天皇制はバブルで崩れなかったので、経済の停滞とかで崩れない揺るぎない価値観が欲しいという気持ちがありました。フリーターとして東京で1人暮らしをしていると、職場がなかったり、職場があってもしょっちゅうクビになったりするので、そこに帰属意識が持てないし、職場が変わるので友達もできない。学校にいけない、企業社会にも入れない、もちろん地域社会もない、どこにも居場所がなくて。そうなると、もう一気に国家しか居場所がないような感覚がありました。教育にうそをつかれたっていう被害者意識があったので、学校で教えてくれない靖国史観的なものが、自分の中にストンと入ってきた。私が入っていた右翼団体には同じような人が入っていました。
−−その団体が、当時の非常に不安定な状況を支えてくれることはあったんでしょうか?
雨宮さん 一時的にはありました。私を唯一必要としてくれる居場所でしたが、自分たちの苦しい現実から目をそらすために、アメリカがどうとか、そんな大きな話をしていた。自分たちの生活を何とかしようとか、自分たちの労働や生活の状況を問題にするということは一切なかったですね。逆に言うと、自分たちは日本人で恵まれているんだということを再確認し合う会話がずーっと続くというような、そんな感じでした。
−−今から考えると、どういうことだったんでしょう?
雨宮さん お前は悪くないよって誰かに言ってほしかったんですね。右翼の大人は、今の世の中で若者が鬱屈して生きづらいのは、日本国憲法が押し付け憲法だから悪い、アメリカと戦後民主主義が悪いと説明するんですが、その意味がわからなくても、自分が悪いと思わなくていいというところで自分の生きづらさをごまかすことができた。それではまりました。
−−右翼をやめたのはどうしてですか。
雨宮さん 私、そのころ総理大臣の名前も知らないくらいの大ばかだったんですけど、右翼の人が時事問題から何から教えてくれました。でも、ある程度物事がわかってきて自分の頭で考えるようになったら、私は全然、右翼じゃないな、右翼の人の言っていることは自分の考えとは違うなと思うようになり、やめました。
−−雨宮さんが「プレカリアート」(不安定な労働者)という問題に取り組み始めたのはいつごろからですか?
雨宮さん 2006年ごろですね。00年に脱フリーターして文筆業になって、不安定なプレカリアートという言葉をたまたまネットで見つけて引っかかるものを感じて、メーデーの集会に行った。そこで、新自由主義と生きづらさや自殺の問題の関係とか、日本の労働政策がどれほど変わってきたかというのを初めて知ったんですね。それまで、自分の周りの人たちがずいぶん自殺していたんですが、その背景には、個人の問題じゃなくて、何か構造的な問題、社会が関わっているんじゃないかとずっと考えていたときだったので、すっと理解できた。その十数年前からの労働政策や新自由主義で格差が広がり、普通に生き、普通に働くってことが特権階級にしか許されなくなったというような状況がある。自己責任などと言われて働けない自分を責めて、「すみません」って遺書とかで謝りながら死んでいった人もいます。どんどん労働市場が過酷になって、ちょっと不器用な人たちの居場所がなくなり、こんな自分が生きてちゃいけないと思って死んでいくような、そういうことがあった。集会で話を聞いて、その人たちのせいで死んだんじゃなく、人を生きさせないようなシステムがもう作られてたんだなと思った。「原因がやっとわかった。ここに敵がいたのか」みたいな感じでした。それをなくさないと私たちの生きづらさは絶対になくならないと思うと、猛然と腹が立った。
−−敵といってもシステムですか。
雨宮さん 当時は小泉政権でした。小泉さんは敵としてはある意味完璧というか、自己責任という言葉もそうですし、既得権益である正社員層からごっそり盗んで、非正規の人が何かおこぼれがくるんじゃないかと錯覚させるようなやり方が巧みだった。小泉さん個人というよりは、小泉さんが進めている労働法制の規制緩和などの政策が自分たちを追い詰めている。本当をいえば、それ以前からの政策で、派遣法ができたときぐらいから自民党の政治が進めてきた方向が、若者の貧困を個人の問題にして企業の利益を最大化していく。そこにみんな気づいて怒りだしたんです。
−−経済の停滞が始まって、企業は非正規を採用してコストを低くしました。それはどのように見えていましたか。
雨宮さん プレカリアートの問題を知ってからは、やっぱり企業は自分たちの利益のために人件費の削減をやっていこうとしているんだと、びっくりしました。日本の企業を誇りに思っているところがあったのに、名だたる大企業が非正規を使い捨てにしたために、派遣労働を経由してホームレスになっている人たちが山ほど生まれた。当時は景気が良いと言われていたけれど、自分たちにはその恩恵はないし、すごく苦しい人が増えているし、大企業の派遣で働きながらも月収10万円ぐらいの人もいた。まったく自分たちが思っていたのとは違う労働世界が広がっていて、その人たちはもう一生はい上がれないようなシステムになっちゃっている。それが始まったのがちょうど私たちの世代くらいからなんです。06年に私は31歳でした。同世代のフリーターは30代を超えて、仕事がなくなり始めてましたね。30の壁を超えられないとか、日本には30歳を超えたフリーターの行き場がないということにも気づいた。
−−企業の言い分についてはどう思いますか。
雨宮さん 結局、グローバル競争を勝ち抜いていくためには人件費を安くして当然じゃないか。一貫してそれです。企業は営利活動を目的としているので、企業を責めてもしょうがない。そこは政治がある程度歯止めをかけないと。営利活動が行き過ぎない雇用形態だとか、あっさりホームレス化しないような生活ができる賃金を払うという法規制は、どこの国でもやっている。日本は働いた賃金だけで生きていけっていうかなりの自己責任社会であるうえに、そこを不安定化、低賃金化されると、働く人に不利にできているので、みんなが不安定になってしまう。雇用保険も失業者の7割以上が受けていない上に住宅政策もないので、失業したらホームレスになっちゃう。
−−80年代から雇用の流動化が進んできましたが、不安定になる人を支える手立てをあんまり考えてこなかったんですね。
雨宮さん そうです。求職者への支援制度とかセーフティーネット的なものがやっとできたのは派遣村以降で、それもあまり使い勝手がいいとはいえないんです。本当は86年に派遣法ができたぐらいからやっておかないといけなかった。00年代に時限爆弾が爆発するように問題化した時には、まだ何もなかった。
−−プレカリアートの人たちに日本が豊かだという感覚は?
雨宮さん まったくないんじゃないですか。90年代は、自分たちが集まって話すときは常にうっすらと「豊かだけど生きづらい」と意識していました。それが00年代に入ると「生きづらいうえに貧乏、カネがない」というのを前提に語られるようになった。だから、一億総中流的なものって、言葉としては05年ぐらいまで生きていた気がします。90年代も自分たちは貧困ライン以下の生活をしていたのに、日本は経済大国という全体の幻想の中で、本当に気づくのが遅れてしまった。当事者は、社会に出たことがないから気づかない。あの時、誰か一人でも、気づいてくれたらと思います。今でこそ、若者の貧困が注目され、非正規の問題に取り組んでくれる人は増えましたけれどね。メディアに問題として発見されたから、認識が改まったってことですよね。
−−今現在の状況はどう見ていますか。
雨宮さん どんどん悪くなっていると思いますね。この前の国民生活基礎調査で、生活が苦しいという人が62・4%と過去最多でした。だから、アベノミクスって何なの、ってことです。年収200万円以下の人が増え、平均年収も下がっています。生活保護受給層は200万人をずっと突破しています。
−−リーマン・ショックの時、緩やかに回復していた景気が急速に悪化して、「派遣切り」などが表面化しました。こうしたことがまた起きる際の備えには何が必要ですか。
雨宮さん 自衛する方法としては制度を知っておくことですかね。労働組合が関われば、寮を追い出されないようにする交渉ができるので、フリーターでも入れる組合を知っておけばいい。あとは、最低限の生活保護に関する知識とか、住宅手当や求職者の支援制度もあります。使えるものは結構あるんですが、それがまったく周知されてない。日本ではそういう生きるか死ぬかにかかわる情報が全然知られてない。
−−どこを変えればいいのでしょうか?
雨宮さん 最低賃金を上げるとか、非正規にいろんな保障をつけるとか、過労死しない労働時間規制とか、そういう個別の小さな政策でできることってちゃんとあります。でも、日本社会がこの格差に対してまひしている感じがあるように思えるんです。最初はみんなすごいショックを受けて聞いてくれたんですが、今は誰も驚かないし、そういう社会だからしょうがないよね、それがグローバリズムに対応する先進国の宿命でしょう、とでもいうようなものを感じるんです。同じ日本に住んでいて言葉が通じないぐらいに格差が広がっていて、生活意識も何もかも全部違って、格差の上位の人と下の人たちで、一つも共感できるところがないふうになっている。そういう社会ってちょっと怖い。そういう相手を助けようとは誰も思わないだろうし、話を聞こうともしない。言葉も通じない怠け者は自己責任だと思ったら、社会保障の分配の対象にするのにも反対すると思うんですね。そういうふうになってきている感じがする。
−−これから先の展望はどうでしょうか?
雨宮さん 自分たちの世代は自分を「絶滅危惧種」って呼ぶようになってきています。結婚して子供を残せない、種を残せないから、そのまま絶滅していくだけの運命という意味です。今住んでいる6畳一間のアパートとかにみんな居続ける。フリーターとか非正規で働いている人たちはその家賃も払えなくなってくると思う。川崎市で起きた簡易宿泊所の火事では、あれが自分たちの未来の姿じゃないかというか、ああいうところで自分たちの世代がどんどん孤独死したり、火事で死んだり、そういう場所に行きつくしかないんじゃないかとすごく感じました。
−−5年先、10年先にやっていきたいことは何ですか。
雨宮さん 自分の世代のこの問題が、何か運動とかすれば解決とか決着というか、どこかに着地するのかと思っていたんですね。雇用があまりにも流動化したことが原因だから、セーフティーネットが必要だ、彼らが悪いわけじゃないんだという認識が社会的にも広まって、どこかに決着の地点があると思ったけれど、10年たってもまったくない。だから、自分の世代の問題として、どこかで落とし前をつけるまではこの問題からは離れられない。10年前は若者の貧困だったけど、今はもう若者じゃない。中年になっていて、それがどんどん初老になり、高齢者になっていく。この世代がどのへんで救われるのかが、ものすごく重要だと思っています。
■あまみや・かりん 1975年、北海道生まれ。高校卒業後、パンクロック歌手、右翼活動家などを経て作家に。2000年、「生き地獄天国」でデビュー。若者の生きづらさをテーマにした著作を発表している。著書に「プレカリアート」「雨宮処凛の闘争ダイアリー」など。「生きさせろ!難民化する若者たち」で日本ジャーナリスト会議賞受賞。「反貧困ネットワーク」世話人。最新刊に「14歳からの戦争のリアル」。