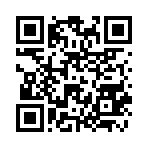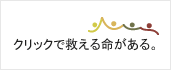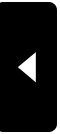昨日も書くこと多くて、ダイジェスト版風に、お送りします。。。
ご機嫌の日
朝から14時ごろまで仕事
終了後直ぐに町内の文化祭会場へ
茶をよばれ
レザークラフトづくりというのですか
子どもたちが
図形の印刷された紙を折り曲げて
電車や自動車づくりに一生懸命
役員さんのご主人がパソコンの名手
ダウンロードして図形を印刷してくれた
かのご主人と雑談
夢想 花、例によって一言
花、例によって一言
・・・人は、子どもの頃に近所の大人にして貰ったことはよく憶えていて、大人になったら何かの形で返してくれる。私も、そうだった。子どもの頃、近所の大人がしてくれた2日にわたる“地蔵盆”が、大人になってからも活動との原点になっている。だから、この取り組みは素晴らしい!・・・
子どもたちを見る地域の大人の目
人の交流
以前に作った草木染め、扇子の展示
綿菓子づくり etc
役員さんの長い期間にわたる準備
一般でお気楽参加の私
ご苦労さん、おおきにと声をかけ
役をしている妻を置いて帰路へ
孫が、「電車見て見て」、と追いかけてきた
夜 西武ライオンズの優勝
ヤング・ライオンズ
巨人より遙かに年俸安い軍団の勝利に歓喜興奮
さまざまに“ご機嫌”を乗せ 日が過ぎてゆきました
ご機嫌の日
朝から14時ごろまで仕事
終了後直ぐに町内の文化祭会場へ
茶をよばれ
レザークラフトづくりというのですか
子どもたちが
図形の印刷された紙を折り曲げて
電車や自動車づくりに一生懸命
役員さんのご主人がパソコンの名手
ダウンロードして図形を印刷してくれた
かのご主人と雑談
夢想
 花、例によって一言
花、例によって一言・・・人は、子どもの頃に近所の大人にして貰ったことはよく憶えていて、大人になったら何かの形で返してくれる。私も、そうだった。子どもの頃、近所の大人がしてくれた2日にわたる“地蔵盆”が、大人になってからも活動との原点になっている。だから、この取り組みは素晴らしい!・・・
子どもたちを見る地域の大人の目
人の交流
以前に作った草木染め、扇子の展示
綿菓子づくり etc
役員さんの長い期間にわたる準備
一般でお気楽参加の私
ご苦労さん、おおきにと声をかけ
役をしている妻を置いて帰路へ
孫が、「電車見て見て」、と追いかけてきた
夜 西武ライオンズの優勝
ヤング・ライオンズ
巨人より遙かに年俸安い軍団の勝利に歓喜興奮
さまざまに“ご機嫌”を乗せ 日が過ぎてゆきました
実は、8月22日の、感動! 女子ソフトボール優勝で、急遽、差し替えられたのは、次の文だったなのです。折角ですから、日の目を見せたく、UPします。
クイズです。
「牙買加」って?
「牙買加」って、何? ヒントを言いますと、
北京オリンピックで陸上男子100m、200mとも、世界新で優勝したボルト選手に関係します。
ヒントを言って、勿体ぶっても、すぐ「答え」がチラついていますので(引っ張るのも無理がありますので・・・)、答えを言いますと、ボルト選手の国 ジャマイカ のことです。
ジャマイカを、中国の漢字表記で書くと、ジャマイカは「牙買加」ということになります。次の、アドレスをクリックしてみてください。
http://www.archiver77.com/olympic/
今回のオリンピック参加の204の国や地域名が、書かれています。これを見るとつくずく世界は広い、知らないことが多すぎる、という現実(夢想花だけかも知れませんが・・・)にぶち当たります。“グローバル化”とか、分かったようなことを言っていますが、まだまだ世界は広い、地球は大きい、そこで、人々は私たちと同じように、毎日を生きているんだなぁ、思わせられるオリンピックでもありました。
なお、因みに、漢字表記の「日本国」は分かりますよね。中国の漢字表記で言っても、日本は「日本国」なのです。
つくずく、我が国は“漢字圏内”の国なんですよね。ジャパン(日本国)は、まさに中国のお隣・親戚みたいな国だなぁ、お互いよいお隣さんご親戚でいたい 、と感慨ひとしきりです。
※ ソフトボール、アメリカとの試合。上野投手が、昨日から三連投。日本式精神論は、グローバル? とブログに書いている今、日本チームが先制の1点をとりました。2点目、ホームランでとりました雨のため「中断」に入りました。頑張れー、ニッポン!
~~以上でございます。ここから下は、昨日、書いたです。~~
地蔵盆 走る子どもの 町五輪
きょうは、街のあちこちで“地蔵盆”が行われている。我が町も地蔵盆があって、役員をしている妻は、犬の介護で寝不足の目をこすりながら、終日、準備運営に出かけていきました。私は、ぶっちゃけ言いますと(因みに「ぶっちゃけ言うと」という言い方は、キムタクさんの造語らしいですね。違ってますか? 違っていようと、本当であろうと、私は、いまや時々“キムタク症候群”にかかって、気分はすっかり“キムタク”です。大勢には、ほとんど、いや全く影響はありませんが・・・。余談はさて置いて、)、昼に食べるものがないので、昼食を一つの大きな目的に会場の公民館に出かけ、草木染めをして、カレーライスを食べました。うまくいかなかった、おいしかった。役員さん、ご苦労様。
会場には、子どもたちや若いお父さん・お母さんやお年寄りが沢山来ていました。子どもたちが、きゃ~きゃ~言いながら、公民館の小さなホールを走り回っていました。こんだけ走って、この中から、ジャマイカの走る走る子どもたち出身のボルト選手のようなランナーが出て来るかなぁ、私は夢想してイマシタ。見出しの句は、私メの、恒例(?)下手俳句(もどき)でゴザイマス。。。
クイズです。
「牙買加」って?
「牙買加」って、何? ヒントを言いますと、
北京オリンピックで陸上男子100m、200mとも、世界新で優勝したボルト選手に関係します。
ヒントを言って、勿体ぶっても、すぐ「答え」がチラついていますので(引っ張るのも無理がありますので・・・)、答えを言いますと、ボルト選手の国 ジャマイカ のことです。
ジャマイカを、中国の漢字表記で書くと、ジャマイカは「牙買加」ということになります。次の、アドレスをクリックしてみてください。
http://www.archiver77.com/olympic/
今回のオリンピック参加の204の国や地域名が、書かれています。これを見るとつくずく世界は広い、知らないことが多すぎる、という現実(夢想花だけかも知れませんが・・・)にぶち当たります。“グローバル化”とか、分かったようなことを言っていますが、まだまだ世界は広い、地球は大きい、そこで、人々は私たちと同じように、毎日を生きているんだなぁ、思わせられるオリンピックでもありました。
なお、因みに、漢字表記の「日本国」は分かりますよね。中国の漢字表記で言っても、日本は「日本国」なのです。
つくずく、我が国は“漢字圏内”の国なんですよね。ジャパン(日本国)は、まさに中国のお隣・親戚みたいな国だなぁ、お互いよいお隣さんご親戚でいたい 、と感慨ひとしきりです。
※ ソフトボール、アメリカとの試合。上野投手が、昨日から三連投。日本式精神論は、グローバル? とブログに書いている今、日本チームが先制の1点をとりました。2点目、ホームランでとりました雨のため「中断」に入りました。頑張れー、ニッポン!
~~以上でございます。ここから下は、昨日、書いたです。~~
地蔵盆 走る子どもの 町五輪
きょうは、街のあちこちで“地蔵盆”が行われている。我が町も地蔵盆があって、役員をしている妻は、犬の介護で寝不足の目をこすりながら、終日、準備運営に出かけていきました。私は、ぶっちゃけ言いますと(因みに「ぶっちゃけ言うと」という言い方は、キムタクさんの造語らしいですね。違ってますか? 違っていようと、本当であろうと、私は、いまや時々“キムタク症候群”にかかって、気分はすっかり“キムタク”です。大勢には、ほとんど、いや全く影響はありませんが・・・。余談はさて置いて、)、昼に食べるものがないので、昼食を一つの大きな目的に会場の公民館に出かけ、草木染めをして、カレーライスを食べました。うまくいかなかった、おいしかった。役員さん、ご苦労様。
会場には、子どもたちや若いお父さん・お母さんやお年寄りが沢山来ていました。子どもたちが、きゃ~きゃ~言いながら、公民館の小さなホールを走り回っていました。こんだけ走って、この中から、ジャマイカの走る走る子どもたち出身のボルト選手のようなランナーが出て来るかなぁ、私は夢想してイマシタ。見出しの句は、私メの、恒例(?)下手俳句(もどき)でゴザイマス。。。
昨日のつづきをお送りします。当時の状況のご理解をより容易にするために、かなり前になりますが、昨年の12月28日号につづいて、「目撃戦後日本世相の」変容(3)」という形でお送りします。(文中 敬称略)
昭和20年代後半から昭和30年代前半
たくましき子どもたちと大人
昭和20年代終わり頃から、街にはすこしずつ白黒テレビが出まわり、力道山がわれら子どもたちのヒーローで、日曜日の昼間、私たち子どもは、学校の校舎に忍び込んでマットを敷き、その上でプロレスごっこをした。
公園の一角に、街頭テレビが置かれ、相撲やプロレス、野球に熱狂した。後に、さだまさしが「親父の一番長い日」という唄を歌い、その中で、『街頭テレビ・・・』云々といった一節があるが、私はその歌詞を懐かしく聴いた。
昭和30年代に入って、「もはや戦後ではない」という政府の白書が出たようであるが、まだ、戦後の傷跡もまだ残り、貧しさと繁栄への熱が同居しているような社会だった。この辺は、今井正監督の白黒映画「キクとイサム」にも描かれている。
白黒テレビ・電気冷蔵庫・電気洗濯機といった、いわゆる「三種の電器」が市場に出回ってきた。が、テレビは、町内でも裕福な1~2軒の家にしかなく、私たち子どもは、大挙して、夜、プロレス中継がある時は、テレビのある家へ押しかけて「おばちゃーん、テレビ見せてー!!」と大声で玄関の扉が開くまでわめき続け、強引に見せてもらった。多分、百姓一揆もこんな風だっただろうと思わせるほどの(?)、ド迫力な押しかけだった。なお、テレビのある間の座敷には泥や砂よけのための新聞紙が敷き詰めてあった。
また、当時、子どもたちの人気番組は大村昆ちゃん、芦屋雁乃助、小雁、茶川一郎出演の30分ものの「番頭はんと丁稚どん」だった。口減らしのために奉公にきた昆ちゃんなどの3人の丁稚が雁乃助扮する番頭にいじめられるというお笑い番組で、昆ちゃんが『飴もろうた~』と踊りまくるシーンや、番頭がいじめるけれども間が抜けているのがおかしくて、笑いこけた。この番組も、子どもたちは押しかけ鑑賞をした。やがてもう少しして、藤田まこと・白木みのるの30分舞台劇「てなもんや三度笠」のテレビ放送も人気番組だった。それに「判決」という30分の真面目な弁護士ドラマがあって、『死刑制度』などの社会問題を真摯に取り上げていた。また、実際の指名手配犯人を扱った30分のドキュメント番組を見て、世相の厳しさとこんな人生したらアカンなぁと思った。「番頭はんと丁稚どん」から指名手配犯人のドキュメント番組まで、確か昭和20年代終わりから30年代半ば頃までだった。私は小学校高学年から中学生、高校生とかけて、近所の家のテレビで見て社会観を形成していった。
社会観を形成と言えば、地域社会、すなわち町内のさまざまな人間関係や出来事も、私に大きな影響を与えた。終戦直後から昭和30年代前半まで、マイカーなんてほとんどの家になかった時期だから、年に1回バスを借り切って(これは20年代後半からかも?)、町内の子どもや大人が揃って、1日バス旅行をした。バスの車中で、マイクで私が唄を歌うとみんなが驚いたように「上手やなぁ」と拍手してくれて嬉しかった。町内は、うるさい大人がたくさんいて、子どもが悪さをすると、注意はもちろんのこと、いつも道ばたで花開いていた『井戸端会議』で悪口も言ってくれてうるさかった。子どもたちは、その中でも、とりわけ悪口好きのおばさんを『NHKババァ』と密かに名付けた。しかし、大人はけっこう親切で、腹を空かしていた私に、「これ食べ」と言ってイモや菓子などをくれたり、夏には町内の子どもたちのために地蔵盆を2日がかりでやって、『当てもの』(抽選のこと。私たちは、こう言っていた)で当てた賞品を、2階の窓から、ロープを伝って子どものいる場所に送ってくれたり、ずいぶん凝ったことをしてくれたりした。
毎日夕方に来る紙芝居屋さんにも、子どもたちは『社会』や『生き方』を教えてもらった。テレビが普及してからは駆逐されるように影を潜めていったが、当時紙芝居のおじさんは、確実に、子どもたちの街の先生だった。5円で、お金のない子には3円でも、煎餅に巻いた水飴やアンズを売り、全くお金のない子はタダ見をさせてもらう代わりに、拍子木を叩いて、紙芝居屋さんが来たことを、町内中に触れ回った。子どもたちは、おじさんの名調子の『鞍馬天狗』で鞍馬天狗や杉作少年の生き方に触れ、『鉄仮面』で夢の世界へ飛んだ。 (つづく)
昭和20年代後半から昭和30年代前半
たくましき子どもたちと大人
昭和20年代終わり頃から、街にはすこしずつ白黒テレビが出まわり、力道山がわれら子どもたちのヒーローで、日曜日の昼間、私たち子どもは、学校の校舎に忍び込んでマットを敷き、その上でプロレスごっこをした。
公園の一角に、街頭テレビが置かれ、相撲やプロレス、野球に熱狂した。後に、さだまさしが「親父の一番長い日」という唄を歌い、その中で、『街頭テレビ・・・』云々といった一節があるが、私はその歌詞を懐かしく聴いた。
昭和30年代に入って、「もはや戦後ではない」という政府の白書が出たようであるが、まだ、戦後の傷跡もまだ残り、貧しさと繁栄への熱が同居しているような社会だった。この辺は、今井正監督の白黒映画「キクとイサム」にも描かれている。
白黒テレビ・電気冷蔵庫・電気洗濯機といった、いわゆる「三種の電器」が市場に出回ってきた。が、テレビは、町内でも裕福な1~2軒の家にしかなく、私たち子どもは、大挙して、夜、プロレス中継がある時は、テレビのある家へ押しかけて「おばちゃーん、テレビ見せてー!!」と大声で玄関の扉が開くまでわめき続け、強引に見せてもらった。多分、百姓一揆もこんな風だっただろうと思わせるほどの(?)、ド迫力な押しかけだった。なお、テレビのある間の座敷には泥や砂よけのための新聞紙が敷き詰めてあった。
また、当時、子どもたちの人気番組は大村昆ちゃん、芦屋雁乃助、小雁、茶川一郎出演の30分ものの「番頭はんと丁稚どん」だった。口減らしのために奉公にきた昆ちゃんなどの3人の丁稚が雁乃助扮する番頭にいじめられるというお笑い番組で、昆ちゃんが『飴もろうた~』と踊りまくるシーンや、番頭がいじめるけれども間が抜けているのがおかしくて、笑いこけた。この番組も、子どもたちは押しかけ鑑賞をした。やがてもう少しして、藤田まこと・白木みのるの30分舞台劇「てなもんや三度笠」のテレビ放送も人気番組だった。それに「判決」という30分の真面目な弁護士ドラマがあって、『死刑制度』などの社会問題を真摯に取り上げていた。また、実際の指名手配犯人を扱った30分のドキュメント番組を見て、世相の厳しさとこんな人生したらアカンなぁと思った。「番頭はんと丁稚どん」から指名手配犯人のドキュメント番組まで、確か昭和20年代終わりから30年代半ば頃までだった。私は小学校高学年から中学生、高校生とかけて、近所の家のテレビで見て社会観を形成していった。
社会観を形成と言えば、地域社会、すなわち町内のさまざまな人間関係や出来事も、私に大きな影響を与えた。終戦直後から昭和30年代前半まで、マイカーなんてほとんどの家になかった時期だから、年に1回バスを借り切って(これは20年代後半からかも?)、町内の子どもや大人が揃って、1日バス旅行をした。バスの車中で、マイクで私が唄を歌うとみんなが驚いたように「上手やなぁ」と拍手してくれて嬉しかった。町内は、うるさい大人がたくさんいて、子どもが悪さをすると、注意はもちろんのこと、いつも道ばたで花開いていた『井戸端会議』で悪口も言ってくれてうるさかった。子どもたちは、その中でも、とりわけ悪口好きのおばさんを『NHKババァ』と密かに名付けた。しかし、大人はけっこう親切で、腹を空かしていた私に、「これ食べ」と言ってイモや菓子などをくれたり、夏には町内の子どもたちのために地蔵盆を2日がかりでやって、『当てもの』(抽選のこと。私たちは、こう言っていた)で当てた賞品を、2階の窓から、ロープを伝って子どものいる場所に送ってくれたり、ずいぶん凝ったことをしてくれたりした。
毎日夕方に来る紙芝居屋さんにも、子どもたちは『社会』や『生き方』を教えてもらった。テレビが普及してからは駆逐されるように影を潜めていったが、当時紙芝居のおじさんは、確実に、子どもたちの街の先生だった。5円で、お金のない子には3円でも、煎餅に巻いた水飴やアンズを売り、全くお金のない子はタダ見をさせてもらう代わりに、拍子木を叩いて、紙芝居屋さんが来たことを、町内中に触れ回った。子どもたちは、おじさんの名調子の『鞍馬天狗』で鞍馬天狗や杉作少年の生き方に触れ、『鉄仮面』で夢の世界へ飛んだ。 (つづく)