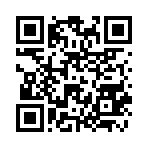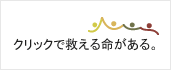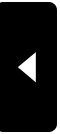世界のあちらこちらで、
ポピュリズムと言われる政治手法が、
勢力を増して来ています。
それと、民主政治は、どう対抗するのだろうか?!
ネットで調べて、このサイトに着きました。
http://www.hino.meisei-u.ac.jp/nihonbun/lecture/062.html
私たちは、目先の小気味よい呼びかけに反応しがちです。
ですが、それが、どういう結果に繋がって来たか・・・?!
この文で、学び、考えさせて頂きたい!!
たいと思います。
読みやすくする為に、
文中の文字に色も付けさせて頂きました。
【民主主義とポピュリズム・・・明星大学教授 服部 裕】
民主主義における政治リーダーのあり方
「決められない政治」あるいは「ぶれる政治家」などというように、昨今の日本では、国政を預かる既成政党の政治に対する批判が高まっている。所謂政治不信であるが、民主主義の場合、極度の政治不信は往々にしてポピュリズムを引き起こすことがある。それは、国民大衆が国難にあっても決断できない既成政治を見限り、より単純明快な主張を掲げる所謂「強いリーダー」を待望する社会心理に支えられるのが一般的である。
昨今の日本の政治状況で言えば、大阪市長や東京都知事に対するリーダー待望論が、その代表的な事例である。「物事を決められない政党政治」にはもはや何も期待できないので、より決断力と実行力があるように見える地方自治体の首長に大きな期待が寄せられるという図式である。実際に、領土問題が取りざたされている小さな島をある地方自治体が購入するとか、全職員に入れ墨の有無を問う調査を実施したりとかという行政手法が示すとおり、そのトップダウン式のやり方は、政府内、与党内そして国会と合議を重ねて物事を決定する国政のやり方に比べて、かなり歯切れの良い「強いリーダー」のイメージを演出していると言える。
では、なぜ地方自治体の首長はより強力なリーダーシップのパフォーマンスを演出しやすいのだろうか。その答えは、中央政府と地方自治における権力の委任形態の違いにあると考えられる。簡単に言えば、地方自治体の首長が住民の直接投票によって選出されて行政府を構築するのとは異なり、中央政府の長つまり内閣総理大臣とそれが任命する諸大臣は国民が直接選出することができないということである。後者が議院内閣制に基づく一方で、前者は言わば「大統領制」に近い権力委任の形態を取っているのである。したがって、政策実現の成否はともかくも、アメリカの「大統領」に近い首長は行政の執行権(予算や人事、さらには専決処分権等々)と議会決議に対する拒否権および事実上の法案請求権を握っているのに反して、内閣総理大臣はまずは閣議(その背後には行政専門職としての官僚が目付役として存在する)、そして与党の合意なくしては、議案の一つも国会に上程することができない。本来、原理的には大統領(首長)の権限と議会の権限が分立し拮抗しあう「大統領制(=二元代表制)」の方が、民意が一元的に委任される「議院内閣制(=一元代表制)」より、国民からの権力の委任は曖昧なはずなのに、上述のように首長が強い行政権を所有するため、見た目の政治的リーダーシップは地方の首長の方がより強く見えるのである。
つまり、昨今の内閣総理大臣のリーダーシップ欠如は、実は戦後の民主主義国家としての日本の政治構造そのものに由来していると考えなければならない。現在の野田総理大臣のみならず、戦後の歴代総理は党派の別なくみな多かれ少なかれ調整型のリーダーであり、強力なトップダウンなど誰一人実行できなかったと言える。(比較的明確なリーダーシップを発揮しようとした田中角栄のような総理大臣は、道半ばで失脚の憂き目を見ている。弱い党内基盤にも拘らず長期政権を実現した小泉首相だけが、例外的に国民の人気を支えに強力なリーダーシップを発揮したポピュリスト的首相だったが、その政治力は「郵政民営化」だけに限定されていた。)
しかし、大統領的な性格を有する首長と雖も、みながみな大阪市長や東京都知事のように強面のリーダーとはなりえない。強いリーダー像を演出するには、もちろん並外れて強烈なキャラクターが必要であろうが、キャラクターだけで政治的リーダーシップを発揮できる訳でもないからである。マックス・ヴェーバーが民主制下の「政治家」を「デマゴーグ(民衆煽動家)」という言葉で定義したように(『職業としての政治家』)、言葉で闘う政治リーダーにとっては、攻撃的かつ打たれ強い性格は必須アイテムである。しかし、そうした煽動家としての強い性格だけでは、強いリーダーにはなれない。強い個性は政治行動を持続させるための基盤でこそあれ、政策を実現するための決定的な資質あるいは政治能力ではない。ヴェーバーが使用した「デマゴーグ」という定義は政治家の性格を言い当てただけではなく、民主主義における政治リーダーに求められる必須の資質と能力を明らかにしていると理解しなければならないのである。それは、「デマゴギー」つまり政治的言説によって民衆を煽動する力(よく言えば、民意を結集する力)こそが、民主主義社会のリーダーに不可欠な資質だということを意味している。
民主主義とポピュリズムの境目
以上のように考えると、民主主義とは言葉巧みな政治家による民衆の「言論操作」あるいは「言論的搾取」のようにも見える。基本的にはそのとおりである。民主政治の構築と執行という局面における政治家と国民大衆との関係、および両者間の手続のあり方に関して見れば、「民主主義」と「ポピュリズム」に本質的な違いはない。
しかし、それにも拘らず、政策実現の局面では両者の間には天と地ほどの違いが生ずる可能性がある。民衆が政治リーダーらの言葉を信じて権力を委任した結果、図らずも大多数の民衆に不幸がもたらされたとき、人々はそれを「ポピュリズム」と呼ぶことに疑問を持たないだろう。つまり、民主主義とは主権者である国民の幸福を追求する方法論であるから、民意として選択した権力者およびその政策が自らの不幸につながったとき、国民はそれをもはや健全な民主主義と認めたくないからである。そのような状況のとき、主権者としての責任を負おうとしない民衆は「政治家に騙された」と嘆き、(自らが招いた)ポピュリズムの責任をポピュリストである政治リーダーたちに転嫁しようとするはずである。
果たして、そのような責任転嫁に妥当性はあるのだろうか。結果を見るまで、それが健全な民主主義なのか、あるいは誤った判断としてのポピュリズムなのかが分からないというのは、いかにも無責任な話である。国民自らに自由な判断が許されている政治社会体制であるならば、結果を見てから民主主義とポピュリズムを区別する態度はいかにも愚民的態度であると言わざるをえない。
民主主義とポピュリズムの間に、手続的に決定的な違いがないことはすでに述べた。違いは政治的な結果であるが、 民主主義における最終的な結果責任は、実は政治家にではなく、主権者である国民に存するのだ。つまりポピュリズムは、偏に主権者である国民自身の間違った判断がもたらす政治状況であると言える。君主制や階級社会における非民主的な政治状況であるなら、民衆は権力者に騙されたと呪詛する(あるいは、それが高ずれば革命を起こす)しかないかもしれないが、言論の自由に基づく普通選挙を基盤にした民主主義体制においては、民主主義を貫くもポピュリズムに堕するも、専ら私たち国民の判断に委ねられているということである。
独裁を招いた究極のポピュリズム
以上、民主主義とポピュリズムとの類縁性および本質的な相違について、いささか抽象的に述べてきた。以下は今日の日本社会のポピュリズム的状況をより明確に把握するために、歴史的事例を挙げて改めてポピュリズムの本質について考えてみよう。
人類史上典型的かつ最大のポピュリズムは、アドルフ・ヒトラーに独裁権を与えたドイツ国民の政治判断に拠るものだった。ヒトラーは1933年1月に権力を奪取すると、自らが仕掛けた世界大戦に敗北する1945年5月までの12年間、ドイツを名実ともに独裁支配することになる。それは、結果的には暴力と武力にものを言わせる独裁であったが、政権および独裁権奪取までの経緯が、実は極めて民主的な手続を踏んでいたという事実は、あまり知られていない。
ドイツにおける普通選挙の導入は意外と早く、19世紀後半のドイツ帝国時代にさかのぼる。もちろん、不完全とは言え民主的な政治が実現するのは1919年以降のワイマール共和国時代であるが、ヒトラー率いるナチ党(国家社会主義ドイツ労働者党)が登場するのは、まさにそのワイマール共和政期であった。ナチ党は当初、武力に頼るクーデターを企てたが、それが完全に失敗すると、(恒常的に国民から一定の支持を得ていた左翼勢力に対抗するために潜在的な暴力性を維持しながらも)地道な政党活動によって国民の支持を獲得することを目指すようになる。
しかし、1928年5月の総選挙までは得票率2%台と低迷し、国民の支持を広げることはまったくできなかった。そうしたなか、1929年の世界的な金融恐慌が、ヒトラーに大きな好機をもたらした。 金融恐慌後の1930年9月に実施された総選挙で、ナチ党は一挙に18.3%の支持を獲得したのである。ちなみに、当時のドイツの政治状況は小党乱立にあった。28年5月の選挙結果を受けて樹立された政府は、左翼のSPD(社会民主党、158議席)と保守派のDVP(ドイツ人民党、45議席)、有産階級を支持母体とするZentrum(中央党、62議席)、DDP(ドイツ民主党、25議席)ならびにBVP(バイエルン人民党、16議席)による大連立政権であった。それ以外にも十をこえる小党乱立の政治的混乱状況のなかで、ヒトラーは政権公約を「失業問題解消」と先の世界大戦の敗戦で「喪失した民族の誇りの回復」の二点に絞ることによって、単純明快な選挙キャンペーンを展開した。また、分かりやすい選挙公約と共に力を入れたのが、「強いリーダー」をアピールするための大々的なイメージ戦略であった。
ヒトラーは金融恐慌による不況に対して「何もできない」既成保守政党の無力ぶりを批判すると共に、左翼勢力の脅威を煽る一方で、自分なら「強いリーダー」として「強いドイツ」を復活することができると、さまざまな広報メディアを駆使して単純明快な言葉を使って訴えた。その結果が1930年の総選挙での躍進であり、さらには32年7月の総選挙での37.2%の得票であった。この選挙で比較第一党となることによって、ヒトラーは政権奪取を現実のものにしたのである。
1932年11月の選挙でも、ナチ党は33.0%を獲得し比較第一党の立場を守ったが、同時に左翼勢力も社会民主党20.4%(28年は29.8%)、共産党16.8%(28年は10.6%)というように相変わらず高い得票率を維持していた。つまり、ワイマール共和政末期は、資本家等の有産階級を支持母体とする中央党以外の中小の保守政党と、政権に関与してきた左翼勢力の社会民主党から一部の支持を奪ったナチ党と左翼勢力が拮抗する政治状況であったと言える。こうした政治的混沌にあってナチ党の33%の得票率は無視できない勢力であるという事実と、共産主義の脅威は相変わらず存在するという恐怖感が、中央党を初めとする保守政党をナチ党との連立に走らせたのである。
以上、非常に複雑かつ微妙な政治勢力の分布状況について述べてきたが、いずれにしても大衆の心を掴んだのは、既成政党にない「強いリーダーシップ」を表現したナチ党だった。たった四年の間に、得票率を2%台半ばから30%を上回る数字に押し上げた事実は、国民のナチ党への熱狂的な支持が生じたことを意味している。つまり、ここで改めて強調したいのは、さまざまな政治状況が複雑に絡み合ったとは言え、その後独裁体制を構築したヒトラーのナチ党は実は民主的な選挙によって権力を奪取したという事実である。そして、その背景には有権者のポピュリズム的熱狂があったことを忘れてはならない。
ヒトラー独裁を可能にしたもう一つの要因も、実は民主的な手続に基づいていた。1933年1月に合法的に宰相に就任したヒトラーは、早くも同じ年の3月には議会に所謂「全権委任法」を上程し、合法的な手続に基づいて可決成立させたのである。「全権委任法」とは、政府に四年間の期限付きながら、議会の承認なしにすべての行政執行権を与えるというものである。つまり、時限付きとは言え、政府、つまりはヒトラーに独裁権を付与するという法律である。ヒトラーはこの独裁法案を三分の二以上の賛成を得て可決させた、つまり民主的な議会において合法的に独裁権を獲得したのである。その背景には、33年3月の選挙において、ナチ党が43.9%の得票率を得た事実がある。絶対過半数こそ獲得できなかったものの、議会において「独裁権」を要求するのに十分な国民の支持だったということである。(「全権委任法」可決後、ヒトラーは合法的に議会の停止や労働組合の禁止等々の政策を実施することで民主主義を廃止し、自らの死まで時限を切らずに究極の独裁体制を敷いた。)
.
民主主義とポピュリズムの狭間にある民意
以上見てきたとおり、ヒトラーの独裁は民意に基づく民主的な手続によって現実のものとなってしまった。この歴史的事実は、民主国家に生きる私たちにとって極めて大きな教訓である。つまり、ファシズムやそれに類する全体主義的体制は、必ずしも民衆を抑圧する暴力装置だけがもたらすものではないということである。言い換えれば、私たちの自由を制限するファシズム的体制は、実は国民自身の自由な判断、つまり民主的な選挙によってもたらされる可能性が大いにあるということである。結果として社会の構成員である個々人の自由と平等なる権利、つまり基本的人権を侵犯する政治権力を、国民自らが進んで選択する政治状況こそがポピュリズムの本質なのである。
思えば、所謂バブル経済崩壊後の日本の調整型統治形態の行き詰まりのなか、党内の支持基盤に拠ることなく、国民の熱狂的な支持だけに権力の正統性を求めた小泉首相は、近代日本の政治史上初の「大統領型」ポピュリストだったと言える。単純明快な「劇場型ワンフレーズ・ポリティクス」は、ポピュリストに共通する政治手法でもある。しかし、ポピュリストの登場が即ちポピュリズムの台頭を意味する、と考えるのは拙速である。民主主義とポピュリズムの境目は、直接国民に訴えかけるポピュリストの政策が、広く国内外の社会の福祉に寄与するものか否かの狭間にあり、それを判断するのは国民自身であるということなのだ。一つだけ確実に言えることは、ヒトラーの場合がそうだったように、ポピュリストが仕掛ける「熱狂」は国民にとって冷静な判断を誤らせる大きな危険要素であるということである。先のフランス大統領選挙の第一回投票でフランス国民戦線のマリーヌ・ルペン党首が、経済不況と失業問題の元凶を移民に押し付けて、国民の偏狭なナショナリズムを煽ることによって18%という高い得票率を得たことを、フランスや他の欧州諸国の政治学者たちはポピュリズムの台頭と看做している(5月8日付け朝日新聞参照)。近代民主主義の発祥の地でありながら、ナチズムという究極かつ最悪のポピュリズムを経験したヨーロッパの専門家はさすがに慧眼である。裏を返せば、民主主義には常にポピュリズムの危険性が潜んでいるということなのである。
私たちが自分たちの幸福のためにより良質の民主主義を実現するか、あるいは自らと他者の自由と平等なる権利を奪うポピュリズムに陥るかは、偏に私たちに付与されている権力委任権、つまり選挙で如何なる民意を形成するかにかかっている。「決断する政治」を標榜する「強い政治リーダー」の歯切れのよい政治姿勢と独善的な政策が、本当に私たちの民主主義を育むものなのか、それとも民主主義を破壊する排他的なポピュリズムにすぎないのかを判断する責任が、主権者である私たち自身に委ねられていることだけは確かである。願わくは、私たち主権者が「愚民」に堕することのないように。
ポピュリズムと言われる政治手法が、
勢力を増して来ています。
それと、民主政治は、どう対抗するのだろうか?!
ネットで調べて、このサイトに着きました。
http://www.hino.meisei-u.ac.jp/nihonbun/lecture/062.html
私たちは、目先の小気味よい呼びかけに反応しがちです。
ですが、それが、どういう結果に繋がって来たか・・・?!
この文で、学び、考えさせて頂きたい!!
たいと思います。
読みやすくする為に、
文中の文字に色も付けさせて頂きました。
【民主主義とポピュリズム・・・明星大学教授 服部 裕】
民主主義における政治リーダーのあり方
「決められない政治」あるいは「ぶれる政治家」などというように、昨今の日本では、国政を預かる既成政党の政治に対する批判が高まっている。所謂政治不信であるが、民主主義の場合、極度の政治不信は往々にしてポピュリズムを引き起こすことがある。それは、国民大衆が国難にあっても決断できない既成政治を見限り、より単純明快な主張を掲げる所謂「強いリーダー」を待望する社会心理に支えられるのが一般的である。
昨今の日本の政治状況で言えば、大阪市長や東京都知事に対するリーダー待望論が、その代表的な事例である。「物事を決められない政党政治」にはもはや何も期待できないので、より決断力と実行力があるように見える地方自治体の首長に大きな期待が寄せられるという図式である。実際に、領土問題が取りざたされている小さな島をある地方自治体が購入するとか、全職員に入れ墨の有無を問う調査を実施したりとかという行政手法が示すとおり、そのトップダウン式のやり方は、政府内、与党内そして国会と合議を重ねて物事を決定する国政のやり方に比べて、かなり歯切れの良い「強いリーダー」のイメージを演出していると言える。
では、なぜ地方自治体の首長はより強力なリーダーシップのパフォーマンスを演出しやすいのだろうか。その答えは、中央政府と地方自治における権力の委任形態の違いにあると考えられる。簡単に言えば、地方自治体の首長が住民の直接投票によって選出されて行政府を構築するのとは異なり、中央政府の長つまり内閣総理大臣とそれが任命する諸大臣は国民が直接選出することができないということである。後者が議院内閣制に基づく一方で、前者は言わば「大統領制」に近い権力委任の形態を取っているのである。したがって、政策実現の成否はともかくも、アメリカの「大統領」に近い首長は行政の執行権(予算や人事、さらには専決処分権等々)と議会決議に対する拒否権および事実上の法案請求権を握っているのに反して、内閣総理大臣はまずは閣議(その背後には行政専門職としての官僚が目付役として存在する)、そして与党の合意なくしては、議案の一つも国会に上程することができない。本来、原理的には大統領(首長)の権限と議会の権限が分立し拮抗しあう「大統領制(=二元代表制)」の方が、民意が一元的に委任される「議院内閣制(=一元代表制)」より、国民からの権力の委任は曖昧なはずなのに、上述のように首長が強い行政権を所有するため、見た目の政治的リーダーシップは地方の首長の方がより強く見えるのである。
つまり、昨今の内閣総理大臣のリーダーシップ欠如は、実は戦後の民主主義国家としての日本の政治構造そのものに由来していると考えなければならない。現在の野田総理大臣のみならず、戦後の歴代総理は党派の別なくみな多かれ少なかれ調整型のリーダーであり、強力なトップダウンなど誰一人実行できなかったと言える。(比較的明確なリーダーシップを発揮しようとした田中角栄のような総理大臣は、道半ばで失脚の憂き目を見ている。弱い党内基盤にも拘らず長期政権を実現した小泉首相だけが、例外的に国民の人気を支えに強力なリーダーシップを発揮したポピュリスト的首相だったが、その政治力は「郵政民営化」だけに限定されていた。)
しかし、大統領的な性格を有する首長と雖も、みながみな大阪市長や東京都知事のように強面のリーダーとはなりえない。強いリーダー像を演出するには、もちろん並外れて強烈なキャラクターが必要であろうが、キャラクターだけで政治的リーダーシップを発揮できる訳でもないからである。マックス・ヴェーバーが民主制下の「政治家」を「デマゴーグ(民衆煽動家)」という言葉で定義したように(『職業としての政治家』)、言葉で闘う政治リーダーにとっては、攻撃的かつ打たれ強い性格は必須アイテムである。しかし、そうした煽動家としての強い性格だけでは、強いリーダーにはなれない。強い個性は政治行動を持続させるための基盤でこそあれ、政策を実現するための決定的な資質あるいは政治能力ではない。ヴェーバーが使用した「デマゴーグ」という定義は政治家の性格を言い当てただけではなく、民主主義における政治リーダーに求められる必須の資質と能力を明らかにしていると理解しなければならないのである。それは、「デマゴギー」つまり政治的言説によって民衆を煽動する力(よく言えば、民意を結集する力)こそが、民主主義社会のリーダーに不可欠な資質だということを意味している。
民主主義とポピュリズムの境目
以上のように考えると、民主主義とは言葉巧みな政治家による民衆の「言論操作」あるいは「言論的搾取」のようにも見える。基本的にはそのとおりである。民主政治の構築と執行という局面における政治家と国民大衆との関係、および両者間の手続のあり方に関して見れば、「民主主義」と「ポピュリズム」に本質的な違いはない。
しかし、それにも拘らず、政策実現の局面では両者の間には天と地ほどの違いが生ずる可能性がある。民衆が政治リーダーらの言葉を信じて権力を委任した結果、図らずも大多数の民衆に不幸がもたらされたとき、人々はそれを「ポピュリズム」と呼ぶことに疑問を持たないだろう。つまり、民主主義とは主権者である国民の幸福を追求する方法論であるから、民意として選択した権力者およびその政策が自らの不幸につながったとき、国民はそれをもはや健全な民主主義と認めたくないからである。そのような状況のとき、主権者としての責任を負おうとしない民衆は「政治家に騙された」と嘆き、(自らが招いた)ポピュリズムの責任をポピュリストである政治リーダーたちに転嫁しようとするはずである。
果たして、そのような責任転嫁に妥当性はあるのだろうか。結果を見るまで、それが健全な民主主義なのか、あるいは誤った判断としてのポピュリズムなのかが分からないというのは、いかにも無責任な話である。国民自らに自由な判断が許されている政治社会体制であるならば、結果を見てから民主主義とポピュリズムを区別する態度はいかにも愚民的態度であると言わざるをえない。
民主主義とポピュリズムの間に、手続的に決定的な違いがないことはすでに述べた。違いは政治的な結果であるが、 民主主義における最終的な結果責任は、実は政治家にではなく、主権者である国民に存するのだ。つまりポピュリズムは、偏に主権者である国民自身の間違った判断がもたらす政治状況であると言える。君主制や階級社会における非民主的な政治状況であるなら、民衆は権力者に騙されたと呪詛する(あるいは、それが高ずれば革命を起こす)しかないかもしれないが、言論の自由に基づく普通選挙を基盤にした民主主義体制においては、民主主義を貫くもポピュリズムに堕するも、専ら私たち国民の判断に委ねられているということである。
独裁を招いた究極のポピュリズム
以上、民主主義とポピュリズムとの類縁性および本質的な相違について、いささか抽象的に述べてきた。以下は今日の日本社会のポピュリズム的状況をより明確に把握するために、歴史的事例を挙げて改めてポピュリズムの本質について考えてみよう。
人類史上典型的かつ最大のポピュリズムは、アドルフ・ヒトラーに独裁権を与えたドイツ国民の政治判断に拠るものだった。ヒトラーは1933年1月に権力を奪取すると、自らが仕掛けた世界大戦に敗北する1945年5月までの12年間、ドイツを名実ともに独裁支配することになる。それは、結果的には暴力と武力にものを言わせる独裁であったが、政権および独裁権奪取までの経緯が、実は極めて民主的な手続を踏んでいたという事実は、あまり知られていない。
ドイツにおける普通選挙の導入は意外と早く、19世紀後半のドイツ帝国時代にさかのぼる。もちろん、不完全とは言え民主的な政治が実現するのは1919年以降のワイマール共和国時代であるが、ヒトラー率いるナチ党(国家社会主義ドイツ労働者党)が登場するのは、まさにそのワイマール共和政期であった。ナチ党は当初、武力に頼るクーデターを企てたが、それが完全に失敗すると、(恒常的に国民から一定の支持を得ていた左翼勢力に対抗するために潜在的な暴力性を維持しながらも)地道な政党活動によって国民の支持を獲得することを目指すようになる。
しかし、1928年5月の総選挙までは得票率2%台と低迷し、国民の支持を広げることはまったくできなかった。そうしたなか、1929年の世界的な金融恐慌が、ヒトラーに大きな好機をもたらした。 金融恐慌後の1930年9月に実施された総選挙で、ナチ党は一挙に18.3%の支持を獲得したのである。ちなみに、当時のドイツの政治状況は小党乱立にあった。28年5月の選挙結果を受けて樹立された政府は、左翼のSPD(社会民主党、158議席)と保守派のDVP(ドイツ人民党、45議席)、有産階級を支持母体とするZentrum(中央党、62議席)、DDP(ドイツ民主党、25議席)ならびにBVP(バイエルン人民党、16議席)による大連立政権であった。それ以外にも十をこえる小党乱立の政治的混乱状況のなかで、ヒトラーは政権公約を「失業問題解消」と先の世界大戦の敗戦で「喪失した民族の誇りの回復」の二点に絞ることによって、単純明快な選挙キャンペーンを展開した。また、分かりやすい選挙公約と共に力を入れたのが、「強いリーダー」をアピールするための大々的なイメージ戦略であった。
ヒトラーは金融恐慌による不況に対して「何もできない」既成保守政党の無力ぶりを批判すると共に、左翼勢力の脅威を煽る一方で、自分なら「強いリーダー」として「強いドイツ」を復活することができると、さまざまな広報メディアを駆使して単純明快な言葉を使って訴えた。その結果が1930年の総選挙での躍進であり、さらには32年7月の総選挙での37.2%の得票であった。この選挙で比較第一党となることによって、ヒトラーは政権奪取を現実のものにしたのである。
1932年11月の選挙でも、ナチ党は33.0%を獲得し比較第一党の立場を守ったが、同時に左翼勢力も社会民主党20.4%(28年は29.8%)、共産党16.8%(28年は10.6%)というように相変わらず高い得票率を維持していた。つまり、ワイマール共和政末期は、資本家等の有産階級を支持母体とする中央党以外の中小の保守政党と、政権に関与してきた左翼勢力の社会民主党から一部の支持を奪ったナチ党と左翼勢力が拮抗する政治状況であったと言える。こうした政治的混沌にあってナチ党の33%の得票率は無視できない勢力であるという事実と、共産主義の脅威は相変わらず存在するという恐怖感が、中央党を初めとする保守政党をナチ党との連立に走らせたのである。
以上、非常に複雑かつ微妙な政治勢力の分布状況について述べてきたが、いずれにしても大衆の心を掴んだのは、既成政党にない「強いリーダーシップ」を表現したナチ党だった。たった四年の間に、得票率を2%台半ばから30%を上回る数字に押し上げた事実は、国民のナチ党への熱狂的な支持が生じたことを意味している。つまり、ここで改めて強調したいのは、さまざまな政治状況が複雑に絡み合ったとは言え、その後独裁体制を構築したヒトラーのナチ党は実は民主的な選挙によって権力を奪取したという事実である。そして、その背景には有権者のポピュリズム的熱狂があったことを忘れてはならない。
ヒトラー独裁を可能にしたもう一つの要因も、実は民主的な手続に基づいていた。1933年1月に合法的に宰相に就任したヒトラーは、早くも同じ年の3月には議会に所謂「全権委任法」を上程し、合法的な手続に基づいて可決成立させたのである。「全権委任法」とは、政府に四年間の期限付きながら、議会の承認なしにすべての行政執行権を与えるというものである。つまり、時限付きとは言え、政府、つまりはヒトラーに独裁権を付与するという法律である。ヒトラーはこの独裁法案を三分の二以上の賛成を得て可決させた、つまり民主的な議会において合法的に独裁権を獲得したのである。その背景には、33年3月の選挙において、ナチ党が43.9%の得票率を得た事実がある。絶対過半数こそ獲得できなかったものの、議会において「独裁権」を要求するのに十分な国民の支持だったということである。(「全権委任法」可決後、ヒトラーは合法的に議会の停止や労働組合の禁止等々の政策を実施することで民主主義を廃止し、自らの死まで時限を切らずに究極の独裁体制を敷いた。)
.
民主主義とポピュリズムの狭間にある民意
以上見てきたとおり、ヒトラーの独裁は民意に基づく民主的な手続によって現実のものとなってしまった。この歴史的事実は、民主国家に生きる私たちにとって極めて大きな教訓である。つまり、ファシズムやそれに類する全体主義的体制は、必ずしも民衆を抑圧する暴力装置だけがもたらすものではないということである。言い換えれば、私たちの自由を制限するファシズム的体制は、実は国民自身の自由な判断、つまり民主的な選挙によってもたらされる可能性が大いにあるということである。結果として社会の構成員である個々人の自由と平等なる権利、つまり基本的人権を侵犯する政治権力を、国民自らが進んで選択する政治状況こそがポピュリズムの本質なのである。
思えば、所謂バブル経済崩壊後の日本の調整型統治形態の行き詰まりのなか、党内の支持基盤に拠ることなく、国民の熱狂的な支持だけに権力の正統性を求めた小泉首相は、近代日本の政治史上初の「大統領型」ポピュリストだったと言える。単純明快な「劇場型ワンフレーズ・ポリティクス」は、ポピュリストに共通する政治手法でもある。しかし、ポピュリストの登場が即ちポピュリズムの台頭を意味する、と考えるのは拙速である。民主主義とポピュリズムの境目は、直接国民に訴えかけるポピュリストの政策が、広く国内外の社会の福祉に寄与するものか否かの狭間にあり、それを判断するのは国民自身であるということなのだ。一つだけ確実に言えることは、ヒトラーの場合がそうだったように、ポピュリストが仕掛ける「熱狂」は国民にとって冷静な判断を誤らせる大きな危険要素であるということである。先のフランス大統領選挙の第一回投票でフランス国民戦線のマリーヌ・ルペン党首が、経済不況と失業問題の元凶を移民に押し付けて、国民の偏狭なナショナリズムを煽ることによって18%という高い得票率を得たことを、フランスや他の欧州諸国の政治学者たちはポピュリズムの台頭と看做している(5月8日付け朝日新聞参照)。近代民主主義の発祥の地でありながら、ナチズムという究極かつ最悪のポピュリズムを経験したヨーロッパの専門家はさすがに慧眼である。裏を返せば、民主主義には常にポピュリズムの危険性が潜んでいるということなのである。
私たちが自分たちの幸福のためにより良質の民主主義を実現するか、あるいは自らと他者の自由と平等なる権利を奪うポピュリズムに陥るかは、偏に私たちに付与されている権力委任権、つまり選挙で如何なる民意を形成するかにかかっている。「決断する政治」を標榜する「強い政治リーダー」の歯切れのよい政治姿勢と独善的な政策が、本当に私たちの民主主義を育むものなのか、それとも民主主義を破壊する排他的なポピュリズムにすぎないのかを判断する責任が、主権者である私たち自身に委ねられていることだけは確かである。願わくは、私たち主権者が「愚民」に堕することのないように。
71年前の8月6日、私は2歳の赤ちゃんでした。
広島には、何度も行ったことがあるし、
私の恩師も、原爆の被爆者です。
原爆を落とされた広島へ、
米国オバマ大統領が訪問し、
原爆資料館で惨状を目の当たりにし、
原爆被災者慰霊碑の前で、スピーチをしました。
米国大統領の広島訪問には、
いろいろな評価があると思いますが、まずは、
じっくりと、スピーチの内容を噛みしめたい、と思います。
オバマ大統領
広島と長崎が教えてくれたのです
71年前の明るく晴れ渡った朝、空から死神が舞い降り、世界は一変しました。閃光と火の玉がこの街を破壊し、人類が自らを破滅に導く手段を手にしたことがはっきりと示されたのです。
なぜ私たちはここ、広島に来たのでしょうか?
私たちは、それほど遠くないある過去に恐ろしい力が解き放たれたことに思いをはせるため、ここにやって来ました。
私たちは、10万人を超える日本の男性、女性、そして子供、数多くの朝鮮の人々、10人ほどのアメリカ人捕虜を含む死者を悼むため、ここにやって来ました。
彼らの魂が、私たちに語りかけています。彼らは、自分たちが一体何者なのか、そして自分たちがどうなったのかを振り返るため、本質を見るように求めています。
広島だけが際立って戦争を象徴するものではありません。遺物を見れば、暴力的な衝突は人類の歴史が始まった頃からあったことがわかります。フリント(編注・岩石の一種)から刃を、木から槍を作るようになった私たちの初期の祖先は、それらの道具を狩りのためだけでなく、自分たちの同類に対して使ったのです。
どの大陸でも、文明の歴史は戦争で満ちています。戦争は食糧不足、あるいは富への渇望から引き起こされ、民族主義者の熱狂や宗教的な熱意でやむなく起きてしまいます。
多くの帝国が勃興と衰退を繰り返しました。多くの人間が隷属と解放を繰り返しました。そして、それぞれの歴史の節目で、罪のない多くの人たちが、数えきれないほどの犠牲者を生んだこと、そして時が経つに連れて自分たちの名前が忘れ去られたことに苦しめられました。
広島と長崎で残酷な終焉へと行き着いた第二次世界大戦は、最も裕福で、もっとも強大な国家たちの間で戦われました。そうした国の文明は、世界に大都市と優れた芸術をもたらしました。そうした国の頭脳たちは、正義、調和、真実に関する先進的な思想を持っていました。にもかかわらず、支配欲あるいは征服欲といった衝動と同じ衝動から、戦争が生まれたのです。そのような衝動が、極めて単純な部族間同士の衝突を引き起こし、新たな能力によって増幅され、新たな制限のないお決まりのパターンを生んでしまったのです。
数年の間に、およそ6000万人もの人たちが亡くなりました。男性、女性、子供、私たちと何ら違いのない人たちがです。射殺され、撲殺され、行進させられて殺され、爆撃で殺され、獄中で殺され、餓死させられ、毒ガスで殺されました。世界中に、この戦争を記録する場所が数多くあります。それは勇気や勇敢な行動を綴った記念碑、言葉では言い表せないような卑劣な行為の名残でもある墓地や空っぽの収容所といったものです。
しかし、この空に立ち上ったキノコ雲の映像を見た時、私たちは人間の中核に矛盾があることを非常にくっきりとした形で思い起こすのです。
私たちの思考、想像力、言語、道具を作る能力、そして人間の本質と切り離して自分たちを定めたり、自分たちの意志に応じてそうした本質を曲げたりする能力といったものを私たちが人類として際立たせること――まさにそうしたことも類を見ない破滅をもたらすような能力を私たちに与えられることによって、どれだけ悲劇をもたらす誘発剤となってしまうか。
物質的な進歩、あるいは社会的な革新によって、どれだけ私たちはこうした真実が見えなくなってしまうのか。
より高い信念という名の下、どれだけ安易に私たちは暴力を正当化してしまうようになるのか。
どの偉大な宗教も、愛や平和、正義への道を約束します。にもかかわらず、信仰こそ殺人許可証であると主張する信者たちから免れられないのです。
科学によって私たちはいろいろなコミュニケーションをとります。空を飛び、病気を治し、科学によって宇宙を理解しようとします。そのような科学が、効率的な殺人の道具となってしまうこともあります。
現代の社会は、私たちに真理を教えています。広島は私たちにこの真理を伝えています。技術の進歩が、人類の制度と一緒に発展しなければならないということを。科学的な革命によって色々な文明が生まれ、そして消えてゆきました。だからこそいま、私たちはここに立っているのです。
私たちは今、この広島の真ん中に立ち、原爆が落とされた時に思いを馳せています。子供たちの苦しみを思い起こします。子供たちが目にしたこと、そして声なき叫び声に耳を傾けます。私たちは罪のない人々が、むごい戦争によって殺されたことを記憶します。これまでの戦争、そしてこれからの戦争の犠牲者に思いを馳せます。
言葉だけで、そのような苦しみに声を与えるものではありません。しかし私たちには共有の責任があります。私たちは、歴史を真っ向から見据えなけれなりません。そして、尋ねるのです。我々は、一体これから何を変えなければならないのか。そのような苦しみを繰り返さないためにはどうしたらいいのかを自問しなくてはなりません。
いつの日か、被爆者の声も消えていくことになるでしょう。しかし「1945年8月6日の苦しみ」というものは、決して消えるものではありません。その記憶に拠って、私たちは慢心と戦わなければなりません。私たちの道徳的な想像力をかきたてるものとなるでしょう。そして、私たちに変化を促すものとなります。
あの運命の日以来、私たちは希望を与える選択をしてきました。
アメリカ合衆国そして日本は、同盟を作っただけではなく友情も育んできました。欧州では連合(EU)ができました。国々は、商業や民主主義で結ばれています。
国、または国民が解放を求めています。そして戦争を避けるための様々な制度や条約もできました。
制約をかけ、交代させ、ひいては核兵器を廃絶へと導くためのものであります。それにもかかわらず、世界中で目にする国家間の攻撃的な行動、テロ、腐敗、残虐行為、抑圧は、「私たちのやることに終わりはないのだ」ということを示しています。
私たちは、人類が悪事をおこなう能力を廃絶することはできないかもしれません。私たちは、自分自身を守るための道具を持たなければならないからです。しかし我が国を含む核保有国は、(他国から攻撃を受けるから核を持たなければいけないという)「恐怖の論理」から逃れる勇気を持つべきです。
私が生きている間にこの目的は達成できないかもしれません。しかし、その可能性を追い求めていきたいと思います。このような破壊をもたらすような核兵器の保有を減らし、この「死の道具」が狂信的な者たちに渡らないようにしなくてはなりません。
それだけでは十分ではありません。世界では、原始的な道具であっても、非常に大きな破壊をもたらすことがあります。私たちの心を変えなくてはなりません。戦争に対する考え方を変える必要があります。紛争を外交的手段で解決することが必要です。紛争を終わらせる努力をしなければなりません。
平和的な協力をしていくことが重要です。暴力的な競争をするべきではありません。私たちは、築きあげていかなければなりません。破壊をしてはならないのです。なによりも、私たちは互いのつながりを再び認識する必要があります。同じ人類の一員としての繋がりを再び確認する必要があります。つながりこそが人類を独自のものにしています。
私たち人類は、過去で過ちを犯しましたが、その過去から学ぶことができます。選択をすることができます。子供達に対して、別の道もあるのだと語ることができます。
人類の共通性、戦争が起こらない世界、残虐性を容易く受け入れない世界を作っていくことができます。物語は、被爆者の方たちが語ってくださっています。原爆を落としたパイロットに会った女性がいました。殺されたそのアメリカ人の家族に会った人たちもいました。アメリカの犠牲も、日本の犠牲も、同じ意味を持っています
アメリカという国の物語は、簡単な言葉で始まります。すべての人類は平等である。そして、生まれもった権利がある。生命の自由、幸福を希求する権利です。しかし、それを現実のものとするのはアメリカ国内であっても、アメリカ人であっても決して簡単ではありません。
しかしその物語は、真実であるということが非常に重要です。努力を怠ってはならない理想であり、すべての国に必要なものです。すべての人がやっていくべきことです。すべての人命は、かけがえのないものです。私たちは「一つの家族の一部である」という考え方です。これこそが、私たちが伝えていかなくてはならない物語です。
だからこそ私たちは、広島に来たのです。そして、私たちが愛している人たちのことを考えます。たとえば、朝起きてすぐの子供達の笑顔、愛する人とのキッチンテーブルを挟んだ優しい触れ合い、両親からの優しい抱擁、そういった素晴らしい瞬間が71年前のこの場所にもあったのだということを考えることができます。
亡くなった方々は、私たちとの全く変わらない人たちです。多くの人々がそういったことが理解できると思います。もはやこれ以上、私たちは戦争は望んでいません。科学をもっと、人生を充実させることに使ってほしいと考えています。
国家や国家のリーダーが選択をするとき、また反省するとき、そのための知恵が広島から得られるでしょう。
世界はこの広島によって一変しました。しかし今日、広島の子供達は平和な日々を生きています。なんと貴重なことでしょうか。この生活は、守る価値があります。それを全ての子供達に広げていく必要があります。この未来こそ、私たちが選択する未来です。未来において広島と長崎は、核戦争の夜明けではなく、私たちの道義的な目覚めの地として知られることでしょう。
広島には、何度も行ったことがあるし、
私の恩師も、原爆の被爆者です。
原爆を落とされた広島へ、
米国オバマ大統領が訪問し、
原爆資料館で惨状を目の当たりにし、
原爆被災者慰霊碑の前で、スピーチをしました。
米国大統領の広島訪問には、
いろいろな評価があると思いますが、まずは、
じっくりと、スピーチの内容を噛みしめたい、と思います。
オバマ大統領
広島と長崎が教えてくれたのです
71年前の明るく晴れ渡った朝、空から死神が舞い降り、世界は一変しました。閃光と火の玉がこの街を破壊し、人類が自らを破滅に導く手段を手にしたことがはっきりと示されたのです。
なぜ私たちはここ、広島に来たのでしょうか?
私たちは、それほど遠くないある過去に恐ろしい力が解き放たれたことに思いをはせるため、ここにやって来ました。
私たちは、10万人を超える日本の男性、女性、そして子供、数多くの朝鮮の人々、10人ほどのアメリカ人捕虜を含む死者を悼むため、ここにやって来ました。
彼らの魂が、私たちに語りかけています。彼らは、自分たちが一体何者なのか、そして自分たちがどうなったのかを振り返るため、本質を見るように求めています。
広島だけが際立って戦争を象徴するものではありません。遺物を見れば、暴力的な衝突は人類の歴史が始まった頃からあったことがわかります。フリント(編注・岩石の一種)から刃を、木から槍を作るようになった私たちの初期の祖先は、それらの道具を狩りのためだけでなく、自分たちの同類に対して使ったのです。
どの大陸でも、文明の歴史は戦争で満ちています。戦争は食糧不足、あるいは富への渇望から引き起こされ、民族主義者の熱狂や宗教的な熱意でやむなく起きてしまいます。
多くの帝国が勃興と衰退を繰り返しました。多くの人間が隷属と解放を繰り返しました。そして、それぞれの歴史の節目で、罪のない多くの人たちが、数えきれないほどの犠牲者を生んだこと、そして時が経つに連れて自分たちの名前が忘れ去られたことに苦しめられました。
広島と長崎で残酷な終焉へと行き着いた第二次世界大戦は、最も裕福で、もっとも強大な国家たちの間で戦われました。そうした国の文明は、世界に大都市と優れた芸術をもたらしました。そうした国の頭脳たちは、正義、調和、真実に関する先進的な思想を持っていました。にもかかわらず、支配欲あるいは征服欲といった衝動と同じ衝動から、戦争が生まれたのです。そのような衝動が、極めて単純な部族間同士の衝突を引き起こし、新たな能力によって増幅され、新たな制限のないお決まりのパターンを生んでしまったのです。
数年の間に、およそ6000万人もの人たちが亡くなりました。男性、女性、子供、私たちと何ら違いのない人たちがです。射殺され、撲殺され、行進させられて殺され、爆撃で殺され、獄中で殺され、餓死させられ、毒ガスで殺されました。世界中に、この戦争を記録する場所が数多くあります。それは勇気や勇敢な行動を綴った記念碑、言葉では言い表せないような卑劣な行為の名残でもある墓地や空っぽの収容所といったものです。
しかし、この空に立ち上ったキノコ雲の映像を見た時、私たちは人間の中核に矛盾があることを非常にくっきりとした形で思い起こすのです。
私たちの思考、想像力、言語、道具を作る能力、そして人間の本質と切り離して自分たちを定めたり、自分たちの意志に応じてそうした本質を曲げたりする能力といったものを私たちが人類として際立たせること――まさにそうしたことも類を見ない破滅をもたらすような能力を私たちに与えられることによって、どれだけ悲劇をもたらす誘発剤となってしまうか。
物質的な進歩、あるいは社会的な革新によって、どれだけ私たちはこうした真実が見えなくなってしまうのか。
より高い信念という名の下、どれだけ安易に私たちは暴力を正当化してしまうようになるのか。
どの偉大な宗教も、愛や平和、正義への道を約束します。にもかかわらず、信仰こそ殺人許可証であると主張する信者たちから免れられないのです。
科学によって私たちはいろいろなコミュニケーションをとります。空を飛び、病気を治し、科学によって宇宙を理解しようとします。そのような科学が、効率的な殺人の道具となってしまうこともあります。
現代の社会は、私たちに真理を教えています。広島は私たちにこの真理を伝えています。技術の進歩が、人類の制度と一緒に発展しなければならないということを。科学的な革命によって色々な文明が生まれ、そして消えてゆきました。だからこそいま、私たちはここに立っているのです。
私たちは今、この広島の真ん中に立ち、原爆が落とされた時に思いを馳せています。子供たちの苦しみを思い起こします。子供たちが目にしたこと、そして声なき叫び声に耳を傾けます。私たちは罪のない人々が、むごい戦争によって殺されたことを記憶します。これまでの戦争、そしてこれからの戦争の犠牲者に思いを馳せます。
言葉だけで、そのような苦しみに声を与えるものではありません。しかし私たちには共有の責任があります。私たちは、歴史を真っ向から見据えなけれなりません。そして、尋ねるのです。我々は、一体これから何を変えなければならないのか。そのような苦しみを繰り返さないためにはどうしたらいいのかを自問しなくてはなりません。
いつの日か、被爆者の声も消えていくことになるでしょう。しかし「1945年8月6日の苦しみ」というものは、決して消えるものではありません。その記憶に拠って、私たちは慢心と戦わなければなりません。私たちの道徳的な想像力をかきたてるものとなるでしょう。そして、私たちに変化を促すものとなります。
あの運命の日以来、私たちは希望を与える選択をしてきました。
アメリカ合衆国そして日本は、同盟を作っただけではなく友情も育んできました。欧州では連合(EU)ができました。国々は、商業や民主主義で結ばれています。
国、または国民が解放を求めています。そして戦争を避けるための様々な制度や条約もできました。
制約をかけ、交代させ、ひいては核兵器を廃絶へと導くためのものであります。それにもかかわらず、世界中で目にする国家間の攻撃的な行動、テロ、腐敗、残虐行為、抑圧は、「私たちのやることに終わりはないのだ」ということを示しています。
私たちは、人類が悪事をおこなう能力を廃絶することはできないかもしれません。私たちは、自分自身を守るための道具を持たなければならないからです。しかし我が国を含む核保有国は、(他国から攻撃を受けるから核を持たなければいけないという)「恐怖の論理」から逃れる勇気を持つべきです。
私が生きている間にこの目的は達成できないかもしれません。しかし、その可能性を追い求めていきたいと思います。このような破壊をもたらすような核兵器の保有を減らし、この「死の道具」が狂信的な者たちに渡らないようにしなくてはなりません。
それだけでは十分ではありません。世界では、原始的な道具であっても、非常に大きな破壊をもたらすことがあります。私たちの心を変えなくてはなりません。戦争に対する考え方を変える必要があります。紛争を外交的手段で解決することが必要です。紛争を終わらせる努力をしなければなりません。
平和的な協力をしていくことが重要です。暴力的な競争をするべきではありません。私たちは、築きあげていかなければなりません。破壊をしてはならないのです。なによりも、私たちは互いのつながりを再び認識する必要があります。同じ人類の一員としての繋がりを再び確認する必要があります。つながりこそが人類を独自のものにしています。
私たち人類は、過去で過ちを犯しましたが、その過去から学ぶことができます。選択をすることができます。子供達に対して、別の道もあるのだと語ることができます。
人類の共通性、戦争が起こらない世界、残虐性を容易く受け入れない世界を作っていくことができます。物語は、被爆者の方たちが語ってくださっています。原爆を落としたパイロットに会った女性がいました。殺されたそのアメリカ人の家族に会った人たちもいました。アメリカの犠牲も、日本の犠牲も、同じ意味を持っています
アメリカという国の物語は、簡単な言葉で始まります。すべての人類は平等である。そして、生まれもった権利がある。生命の自由、幸福を希求する権利です。しかし、それを現実のものとするのはアメリカ国内であっても、アメリカ人であっても決して簡単ではありません。
しかしその物語は、真実であるということが非常に重要です。努力を怠ってはならない理想であり、すべての国に必要なものです。すべての人がやっていくべきことです。すべての人命は、かけがえのないものです。私たちは「一つの家族の一部である」という考え方です。これこそが、私たちが伝えていかなくてはならない物語です。
だからこそ私たちは、広島に来たのです。そして、私たちが愛している人たちのことを考えます。たとえば、朝起きてすぐの子供達の笑顔、愛する人とのキッチンテーブルを挟んだ優しい触れ合い、両親からの優しい抱擁、そういった素晴らしい瞬間が71年前のこの場所にもあったのだということを考えることができます。
亡くなった方々は、私たちとの全く変わらない人たちです。多くの人々がそういったことが理解できると思います。もはやこれ以上、私たちは戦争は望んでいません。科学をもっと、人生を充実させることに使ってほしいと考えています。
国家や国家のリーダーが選択をするとき、また反省するとき、そのための知恵が広島から得られるでしょう。
世界はこの広島によって一変しました。しかし今日、広島の子供達は平和な日々を生きています。なんと貴重なことでしょうか。この生活は、守る価値があります。それを全ての子供達に広げていく必要があります。この未来こそ、私たちが選択する未来です。未来において広島と長崎は、核戦争の夜明けではなく、私たちの道義的な目覚めの地として知られることでしょう。
昨23日、沖縄は、
沖縄の全戦没者を追悼する「慰霊の日」を迎えました。
1945年6月23日に
3カ月近く続いた旧日本軍の組織的戦闘が
終結してから今年で70年。
翁長雄志沖縄県知事が追悼式で、
次の「平和宣言」を読み上げ、
国の内外に訴えました。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
70年目の6月23日を迎えました。
私たちの郷土沖縄では、かつて、史上まれにみる熾烈な地上戦が行われました。20万人余りの尊い命が犠牲となり、家族や友人など愛する人々を失った悲しみを、私たちは永遠に忘れることができません。
それは、私たち沖縄県民が、その目や耳、肌に戦のもたらす悲惨さを鮮明に記憶しているからで、戦争の犠牲になられた方々の安らかであることを心から願い、恒久平和を切望しているからです。
戦後、私たちは、この思いを忘れることなく、復興と発展の道を力強く歩んできました。
しかしながら、国土面積の0・6%にすぎない本県に、日米安全保障体制を担う米軍専用施設の73・8%が集中し、依然として過重な基地負担が県民生活や本県の振興開発にさまざまな影響を与え続けています。米軍再編に基づく普天間飛行場の辺野古への移設をはじめ、嘉手納飛行場より南の米軍基地の整理縮小がなされても、専用施設面積の全国に占める割合はわずか0.7%しか縮小されず、返還時期も含め、基地負担の軽減とはほど遠いものです。
沖縄の米軍基地問題は、我が国の
安全保障の問題であり、国民全体で
負担すべき重要な課題です。
特に、普天間飛行場の辺野古移設については、昨年の選挙で反対の民意が示されており、辺野古に新基地を建設することは困難です。
そもそも、私たち県民の思いとは全く別に、強制接収された世界一危険といわれる普天間飛行場の固定化は許されず、「危険性除去のため辺野古に移設する」「嫌なら沖縄が代替案を出しなさい」との考えは、到底県民には許容できるものではありません。
国民の自由、平等、人権、民主主義が等しく保障されずして、平和の礎を築く
ことはできないのです。
政府においては、固定観念に縛られず、普天間飛行場を辺野古へ移設する作業の中止を決断し、沖縄の基地負担を軽減する政策を再度見直されることを強く求めます。
一方、私たちを取り巻く世界情勢は、地域紛争やテロ、差別や貧困がもととなり、多くの人が命を落としたり、人間としての尊厳が蹂躙されるなど悲劇が今なお繰り返されています。
このような現実にしっかりと向き合い、平和を脅かすさまざまな問題を解決するには、一人一人が積極的に平和を求める強い意志を持つことが重要です。
戦後70年を迎え、アジアの国々をつなぐ架け橋として活躍した先人たちの「万国津梁(ばんこくしんりょう)」の精神を胸に刻み、これからも私たちは、アジア・太平洋地域の発展と、平和の実現に向けて努力していきます。
未来を担う子や孫のために、誇りある豊かさを創りあげ、時を超えて、いつまでも子供たちの笑顔が絶えない豊かな沖縄を目指します。
慰霊の日に当たり、戦没者の御霊に心から哀悼の誠をささげるとともに、沖縄が恒久平和の発信地として輝かしい未来の構築に向けて、全力で取り組んでいく決意をここに宣言します。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
私は、1945年6月23日には、まだ2歳。
戦後日本の様子は、自分なりに目撃して来ましたが、
戦時中の様子は、親から聞いたり、
戦後上映されたニュース映画や
漫画「はだしのゲン」で知るのみでした。
また、数年前に、滋賀咲くブログ仲間たちと、
沖縄県普天間基地や辺野古の海を訪れ、
矛盾や慟哭を目撃しました。
翁長雄志知事のこの「平和宣言」で、
沖縄県に米軍基地負担を強いてきたことへの、
本土の、いわゆる本土モンとしての、我が胸の痛み、
どういう形で、
日本が、国の内外に、平和への貢献をしていくか・・・
何度も、反芻して、噛みしめたい、と思います。(>_<)
なお、
本来ならば、平和宣言文に、色を付けることは、不遜かと思いましたが、
読みやすくするため、文字に色を付けたり、字を大きく表記しました。m(_ _)m
昨日、
部落解放と人権尊重への道を学ぶ学習会に参加しました。
そこで上映された、
ドキュメンタリー映画「ある精肉店のはなし」
http://www.seinikuten-eiga.com/
は、大阪の精肉産業に従事する人たちとお客さんの交流を丹念に描いていました。
その中で、語られた
「水平社宣言」を改めて読み考えました。
http://www1.mahoroba.ne.jp/~suihei/index.html
水平社宣言
全国に散在する吾が特殊部落民よ団結せよ!長い間いぢめられて来た兄弟よ、過去半世紀間に種々なる方法と、多くの人々によってなされた吾等のための運動が、何等の有難い効果をもたらさなかった事実は、それらのすべてが吾々によって、又他の人々によってつねに人間を冒とくされていたばちであったのだ。そしてこれらの人間をいたわるかのごとき運動は、かえって多くの兄弟を堕落させた事を想へば、この際吾等の中より間を尊敬する事によって自ら解放せんとする者の集団運動を起こせるは、むしろ必然である。
兄弟よ、吾々の祖先は自由、平等の渇仰者であり、実行者であった。ろう劣なる階級政策の犠牲者であり男らしき産業的殉教者であったのだ。ケモノの皮はぐ報酬として、生々しき人間の皮をはぎ取られ、ケモノの心臓を裂く代価として、暖かい人間の心臓を引き裂かれ、そこへ下らない嘲笑の唾まで吐きかけられた呪はれの夜の悪夢のうちにも、なほ誇り得る人間の血は、涸れずにあった。そうだ、そして吾々は、この血をうけて人間が神にかわろうとする時代にあうたのだ。犠牲者がその烙印を投げ返す時が来たのだ。
殉教者が、その荊冠を祝福される時が来たのだ。吾々がエタである事を誇り得る時が来たのだ。吾々は、かならず卑屈なる言葉と怯惰なる行為によって、祖先をはずかしめ、人間を冒とくしてはならぬ。そうして人の世の冷たさが、どんなに冷たいか、人間をいたわる事が何であるかをよく知っている吾々は、心から人生の熱と光を願求礼賛するものである。
水平社は、かくして生まれた。人の世に熱あれ、人間に光あれ。
大正十一年三月三日 全国水平社創立大会
~~~~~~~~~~~~~~
以後、
私の体験を言いますと、
昭和44年、当時、
住井すえさん原作の映画「橋のない川」上映運動が各地であり、
そのことで、女子生徒二人から、部落問題について質問され、
教師に成って間のなかった私は、オタオタして、
まともに答えられずに、
一人の女子生徒が、顔を真っ赤にして、その場を離れて行きました。
これは、アカン、と、職場の先輩教師に相談して、
ある同和地区で、毎週金曜日の夜、隣保館で開かれていた、
八八部落研(八幡・八日市の部落問題研究会)で5年間学習し、
私の眼が見開かされ、
地域のおばちゃん・おっちゃん・青年・教師と交流し、
部落問題や差別、人間の生き方、世界観を
学び考える機会を頂き、
以後の教師生活や定年後の自分の生き方に、
決定的な影響を与えて、頂きました。
その私が考えますのに、
この水平社宣言は、素晴らしい人権宣言でありますと共に、
個々の人間に、生き方への示唆を多く含む内容だ!!!
と、思います。
地域のおばちゃんが、私に言って下さった言葉
「先生は、本音を喋る先生でありいや!」
は、以後の私に大きな影響を与えました。
このブログのあちこちに、人権尊重を訴えて居ますのも、
八・八部落研の影響、おばちゃんの言葉です。
以後、ブログで、人権尊重・人間尊厳について、
書いて行きます。
きょうは、
映画をいつか見て頂きたいと、言うことと、
水平社宣言をじっくり読んで、意味することをお考え下さい!!!
ということを、切にお願いして、この号は、ひとまず閉じたいと思います。
m(_ _)m
部落解放と人権尊重への道を学ぶ学習会に参加しました。
そこで上映された、
ドキュメンタリー映画「ある精肉店のはなし」
http://www.seinikuten-eiga.com/
は、大阪の精肉産業に従事する人たちとお客さんの交流を丹念に描いていました。
その中で、語られた
「水平社宣言」を改めて読み考えました。
http://www1.mahoroba.ne.jp/~suihei/index.html
水平社宣言
全国に散在する吾が特殊部落民よ団結せよ!長い間いぢめられて来た兄弟よ、過去半世紀間に種々なる方法と、多くの人々によってなされた吾等のための運動が、何等の有難い効果をもたらさなかった事実は、それらのすべてが吾々によって、又他の人々によってつねに人間を冒とくされていたばちであったのだ。そしてこれらの人間をいたわるかのごとき運動は、かえって多くの兄弟を堕落させた事を想へば、この際吾等の中より間を尊敬する事によって自ら解放せんとする者の集団運動を起こせるは、むしろ必然である。
兄弟よ、吾々の祖先は自由、平等の渇仰者であり、実行者であった。ろう劣なる階級政策の犠牲者であり男らしき産業的殉教者であったのだ。ケモノの皮はぐ報酬として、生々しき人間の皮をはぎ取られ、ケモノの心臓を裂く代価として、暖かい人間の心臓を引き裂かれ、そこへ下らない嘲笑の唾まで吐きかけられた呪はれの夜の悪夢のうちにも、なほ誇り得る人間の血は、涸れずにあった。そうだ、そして吾々は、この血をうけて人間が神にかわろうとする時代にあうたのだ。犠牲者がその烙印を投げ返す時が来たのだ。
殉教者が、その荊冠を祝福される時が来たのだ。吾々がエタである事を誇り得る時が来たのだ。吾々は、かならず卑屈なる言葉と怯惰なる行為によって、祖先をはずかしめ、人間を冒とくしてはならぬ。そうして人の世の冷たさが、どんなに冷たいか、人間をいたわる事が何であるかをよく知っている吾々は、心から人生の熱と光を願求礼賛するものである。
水平社は、かくして生まれた。人の世に熱あれ、人間に光あれ。
大正十一年三月三日 全国水平社創立大会
~~~~~~~~~~~~~~
以後、
私の体験を言いますと、
昭和44年、当時、
住井すえさん原作の映画「橋のない川」上映運動が各地であり、
そのことで、女子生徒二人から、部落問題について質問され、
教師に成って間のなかった私は、オタオタして、
まともに答えられずに、
一人の女子生徒が、顔を真っ赤にして、その場を離れて行きました。
これは、アカン、と、職場の先輩教師に相談して、
ある同和地区で、毎週金曜日の夜、隣保館で開かれていた、
八八部落研(八幡・八日市の部落問題研究会)で5年間学習し、
私の眼が見開かされ、
地域のおばちゃん・おっちゃん・青年・教師と交流し、
部落問題や差別、人間の生き方、世界観を
学び考える機会を頂き、
以後の教師生活や定年後の自分の生き方に、
決定的な影響を与えて、頂きました。
その私が考えますのに、
この水平社宣言は、素晴らしい人権宣言でありますと共に、
個々の人間に、生き方への示唆を多く含む内容だ!!!
と、思います。
地域のおばちゃんが、私に言って下さった言葉
「先生は、本音を喋る先生でありいや!」
は、以後の私に大きな影響を与えました。
このブログのあちこちに、人権尊重を訴えて居ますのも、
八・八部落研の影響、おばちゃんの言葉です。
以後、ブログで、人権尊重・人間尊厳について、
書いて行きます。
きょうは、
映画をいつか見て頂きたいと、言うことと、
水平社宣言をじっくり読んで、意味することをお考え下さい!!!
ということを、切にお願いして、この号は、ひとまず閉じたいと思います。
m(_ _)m
ブログで、皆既月食を、皆さまにご紹介した手前、
月食を見ようとしましたが、結果的に、断続的に、見ました。
断続的に?!
夢想花、夕餉のビールの誘惑に勝てず、
ぐぃ~~、っと!
それでも、寝る前に、近くの公園に出かけて、部分月食 を見、
寝る前には、窓を開けて、違う形の、部分月食 を見ました。
そして、日付変更線を越えたさっき、
表に出て、天上を見上げると、
月食の変身・へんし~~んを終えた
真ん丸お月様が、煌々と輝いて、
あまたのお星様に囲まれて、
鎮座ましまして居ました。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
この思いを、下手な、詩(もどき)に、しました。
恥ずかしながら、ご披露します(^^;)。
天にましますお月様とお星様、
そして、
地上の生き物たち・・・!!
月食の変身を終えた
真ん丸お月様が、煌々と輝いて、
あまたのお星様に囲まれて、
鎮座され、
そして、
地上の草むらから聞こえる、
絶え間なく聞こえる虫たちの声!
この静寂と安寧は、
天上にまします
お月様とお星様の微笑み!
そして、
地上の、
生きとし生けるものの息吹き営み!
微笑みの輝きと、静かなる地上の声の合奏で、
日本中、何処にでも、
世界の地の何処にも、
遍く、広く、平等に、差別なく、
人の世の、過ち、欲と野望を、
照らし賜え、
歌い賜え、
再生と再起と寛恕の道を、
示し賜え、与え賜え!!!
示し賜え、与え賜え、
再生と再起と寛恕の道を!!!
月食を見ようとしましたが、結果的に、断続的に、見ました。
断続的に?!
夢想花、夕餉のビールの誘惑に勝てず、
ぐぃ~~、っと!
それでも、寝る前に、近くの公園に出かけて、部分月食 を見、
寝る前には、窓を開けて、違う形の、部分月食 を見ました。
そして、日付変更線を越えたさっき、
表に出て、天上を見上げると、
月食の変身・へんし~~んを終えた
真ん丸お月様が、煌々と輝いて、
あまたのお星様に囲まれて、
鎮座ましまして居ました。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
この思いを、下手な、詩(もどき)に、しました。
恥ずかしながら、ご披露します(^^;)。
天にましますお月様とお星様、
そして、
地上の生き物たち・・・!!
月食の変身を終えた
真ん丸お月様が、煌々と輝いて、
あまたのお星様に囲まれて、
鎮座され、
そして、
地上の草むらから聞こえる、
絶え間なく聞こえる虫たちの声!
この静寂と安寧は、
天上にまします
お月様とお星様の微笑み!
そして、
地上の、
生きとし生けるものの息吹き営み!
微笑みの輝きと、静かなる地上の声の合奏で、
日本中、何処にでも、
世界の地の何処にも、
遍く、広く、平等に、差別なく、
人の世の、過ち、欲と野望を、
照らし賜え、
歌い賜え、
再生と再起と寛恕の道を、
示し賜え、与え賜え!!!
示し賜え、与え賜え、
再生と再起と寛恕の道を!!!