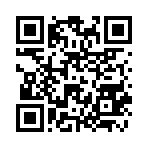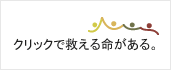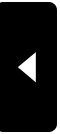今、連日、国の内外の、
核兵器とか武力行使等の
喧騒なニュースが報じられています。
それが、
誰かが意図的に煽っているものなのか?!
それとも、
人間の幸福実現とどう、関わるのか?!
情報が、氾濫・錯綜して、
考える道標を見失いがちです。
今、年々、
戦争の惨禍を知る世代の人が高齢化の為
証言が得にくくなって来ています。
そこで、私の信条の原点
1940年に発表された
映画チャップリンの「独裁者」の動画を
平和への道標に成ればとupします。
1961(昭和36)頃だったか、
映画大好き少年だった高校生の私は、
先ほどまで見ていた
映画の感動に打ち震えて
京都の夜道を歩いていました、
映画チャップリンの「独裁者」の動画です。
https://www.youtube.com/watch?v=biAAmqaMCvo
野中広務さんが、訴え続けて来られたことでもあります。
戦争の惨禍がずっと語り継がれるよう、
風化しないよう、
私の高校生時の感動を
再度、改めて
記す次第です。m(__)m
核兵器とか武力行使等の
喧騒なニュースが報じられています。
それが、
誰かが意図的に煽っているものなのか?!
それとも、
人間の幸福実現とどう、関わるのか?!
情報が、氾濫・錯綜して、
考える道標を見失いがちです。
今、年々、
戦争の惨禍を知る世代の人が高齢化の為
証言が得にくくなって来ています。
そこで、私の信条の原点
1940年に発表された
映画チャップリンの「独裁者」の動画を
平和への道標に成ればとupします。
1961(昭和36)頃だったか、
映画大好き少年だった高校生の私は、
先ほどまで見ていた
映画の感動に打ち震えて
京都の夜道を歩いていました、
映画チャップリンの「独裁者」の動画です。
https://www.youtube.com/watch?v=biAAmqaMCvo
野中広務さんが、訴え続けて来られたことでもあります。
戦争の惨禍がずっと語り継がれるよう、
風化しないよう、
私の高校生時の感動を
再度、改めて
記す次第です。m(__)m
昨日は、
原爆投下から72年目の朝、
長崎平和祈念式典がありました。
それに、関わる動画を探したのですが、
検索が下手なのか?
うまく出て来ませんでしたので
まず、関連する動画と
田上長崎市長の平和宣言
を載せて
平和・核兵器廃絶への願いを
受け止めさせて頂きたいと思います。m(_ _)m
まず、この動画を見て下さい。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170809/k10011094191000.html?utm_int=movie-new_contents_list-items_005&movie=true
https://mainichi.jp/movie/video/?id=120102102
次に、 「ノーモア ヒバクシャ」
長崎市長、平和宣言で 「姿勢理解できない」と政府を批判しました。
★ 長崎平和宣言・・・田上富久長崎市長 ★ です。
この言葉は、未来に向けて、世界中の誰も、
永久に、核兵器による惨禍を体験することがないように、
という被爆者の心からの願いを表したものです。
その願いが、この夏、世界の多くの国々を動かし、
一つの条約を生み出しました。
核兵器を、使うことはもちろん、
持つことも、配備することも禁止した「核兵器禁止条約」が、
国連加盟国の6割を超える122カ国の賛成で採択されたのです。
それは、
被爆者が長年積み重ねてきた努力がようやく形になった瞬間でした。
私たちは
「ヒバクシャ」の苦しみや努力にも言及したこの条約を
「ヒロシマ・ナガサキ条約」と呼びたいと思います。
そして、
核兵器禁止条約を推進する国々や国連、NGOなどの、
人道に反するものを世界からなくそうとする
強い意志と勇気ある行動に深く感謝します。
しかし、これはゴールではありません。
今も世界には、1万5千発近くの核兵器があります。
核兵器を巡る国際情勢は緊張感を増しており、
遠くない未来に核兵器が使われるのではないか、
という強い不安が広がっています。
しかも、
核兵器を持つ国々は、この条約に反対しており、
私たちが目指す
「核兵器のない世界」にたどり着く道筋は
まだ見えていません。
ようやく生まれたこの条約をいかに活(い)かし、
歩みを進めることができるかが、
今、人類に問われています。
核兵器を持つ国々と核の傘の下にいる国々に訴えます。
安全保障上、核兵器が必要だと言い続ける限り、
核の脅威はなくなりません。
核兵器によって国を守ろうとする政策を見直してください。
核不拡散条約(NPT)は、
すべての加盟国に核軍縮の義務を課しているはずです。
その義務を果たしてください。
世界が勇気ある決断を待っています。
日本政府に訴えます。
核兵器のない世界を目指してリーダーシップをとり、
核兵器を持つ国々と持たない国々の
橋渡し役を務めると明言しているにも関わらず、
核兵器禁止条約の交渉会議にさえ参加しない姿勢を、
被爆地は到底理解できません。
唯一の戦争被爆国として、
核兵器禁止条約への一日も早い参加を目指し、
核の傘に依存する政策の見直しを進めてください。
日本の参加を国際社会は待っています。
また、二度と戦争をしてはならないと固く決意した
日本国憲法の平和の理念と非核三原則の厳守を世界に発信し、
核兵器のない世界に向けて前進する
具体的方策の一つとして、
今こそ「北東アジア非核兵器地帯」構想の検討を求めます。
私たちは決して忘れません。
1945年8月9日午前11時2分、
今、私たちがいるこの丘の上空で原子爆弾がさく裂し、
15万人もの人々が死傷した事実を。
あの日、原爆の凄(すさ)まじい熱線と爆風によって、
長崎の街は一面の焼野原(やけのはら)となりました。
皮ふが垂れ下がりながらも、
家族を探し、さ迷い歩く人々。
黒焦げの子どもの傍らで、
茫然(ぼうぜん)と立ちすくむ母親。
街のあちこちに地獄のような光景がありました。
十分な治療も受けられずに、多くの人々が死んでいきました。
そして72年経った今でも、
放射線の障害が被爆者の体をむしばみ続けています。
原爆は、いつも側にいた
大切な家族や友だちの命を
無差別に奪い去っただけでなく、
生き残った人たちのその後の人生を
も無惨(むざん)に狂わせたのです。
世界各国のリーダーの皆さん。被爆地を訪れてください。
遠い原子雲の上からの視点ではなく、
原子雲の下で何が起きたのか、
原爆が人間の尊厳をどれほど残酷に踏みにじったのか、
あなたの目で見て、耳で聴いて、
心で感じてください。
もし自分の家族がそこにいたら、と考えてみてください。
人はあまりにもつらく苦しい体験をしたとき、
その記憶を封印し、語ろうとはしません。
語るためには思い出さなければならないからです。
それでも被爆者が、
心と体の痛みに耐えながら体験を語ってくれるのは、
人類の一員として、私たちの未来を守るために、
懸命に伝えようと決意しているからです。
世界中のすべての人に呼びかけます。
最も怖いのは無関心なこと、
そして忘れていくことです。
戦争体験者や被爆者からの
平和のバトンを途切れさせることなく
未来へつないでいきましょう。
今、長崎では平和首長会議の総会が開かれています。
世界の7400の都市が参加する
このネットワークには、
戦争や内戦などつらい記憶を持つまちの代表も大勢参加しています。
被爆者が私たちに示してくれたように、
小さなまちの平和を願う思いも、力を合わせれば、
そして
あきらめなければ、世界を動かす力になることを、
ここ長崎から、
平和首長会議の仲間たちとともに世界に発信します。
そして、
被爆者が声をからして訴え続けてきた
「長崎を最後の被爆地に」
という言葉が、
人類共通の願いであり、意志であることを示します。
被爆者の平均年齢は81歳を超えました。
「被爆者がいる時代」の終わりが近づいています。
日本政府には、
被爆者のさらなる援護の充実と、
被爆体験者の救済を求めます。
福島の原発事故から6年が経ちました。
長崎は放射能の脅威を経験したまちとして、
福島の被災者に寄り添い、応援します。
原子爆弾で亡くなられた方々に心から追悼の意を捧げ、
私たち長崎市民は、
核兵器のない世界を願う世界の人々と連携して、
核兵器廃絶と恒久平和の実現に
力を尽くし続けることをここに宣言します。
2017年(平成29年)8月9日 長崎市長 田上富久
今、核戦争に繫がりかねない、きな臭い報が、
駆け巡っています。
起こってからでは遅いし、
地球・人類の破滅です。
私が夢描くことは、日本の政治家が、
緊張する国々の“橋渡し役”を誠実に実行して、
ノーベル平和賞、を貰って、
歴史に、レガシーを刻まないか・・・?!
という、願いです。m(_ _)m(T_T)m(_ _)m
原爆投下から72年目の朝、
長崎平和祈念式典がありました。
それに、関わる動画を探したのですが、
検索が下手なのか?
うまく出て来ませんでしたので
まず、関連する動画と
田上長崎市長の平和宣言
を載せて
平和・核兵器廃絶への願いを
受け止めさせて頂きたいと思います。m(_ _)m
まず、この動画を見て下さい。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170809/k10011094191000.html?utm_int=movie-new_contents_list-items_005&movie=true
https://mainichi.jp/movie/video/?id=120102102
次に、 「ノーモア ヒバクシャ」
長崎市長、平和宣言で 「姿勢理解できない」と政府を批判しました。
★ 長崎平和宣言・・・田上富久長崎市長 ★ です。
この言葉は、未来に向けて、世界中の誰も、
永久に、核兵器による惨禍を体験することがないように、
という被爆者の心からの願いを表したものです。
その願いが、この夏、世界の多くの国々を動かし、
一つの条約を生み出しました。
核兵器を、使うことはもちろん、
持つことも、配備することも禁止した「核兵器禁止条約」が、
国連加盟国の6割を超える122カ国の賛成で採択されたのです。
それは、
被爆者が長年積み重ねてきた努力がようやく形になった瞬間でした。
私たちは
「ヒバクシャ」の苦しみや努力にも言及したこの条約を
「ヒロシマ・ナガサキ条約」と呼びたいと思います。
そして、
核兵器禁止条約を推進する国々や国連、NGOなどの、
人道に反するものを世界からなくそうとする
強い意志と勇気ある行動に深く感謝します。
しかし、これはゴールではありません。
今も世界には、1万5千発近くの核兵器があります。
核兵器を巡る国際情勢は緊張感を増しており、
遠くない未来に核兵器が使われるのではないか、
という強い不安が広がっています。
しかも、
核兵器を持つ国々は、この条約に反対しており、
私たちが目指す
「核兵器のない世界」にたどり着く道筋は
まだ見えていません。
ようやく生まれたこの条約をいかに活(い)かし、
歩みを進めることができるかが、
今、人類に問われています。
核兵器を持つ国々と核の傘の下にいる国々に訴えます。
安全保障上、核兵器が必要だと言い続ける限り、
核の脅威はなくなりません。
核兵器によって国を守ろうとする政策を見直してください。
核不拡散条約(NPT)は、
すべての加盟国に核軍縮の義務を課しているはずです。
その義務を果たしてください。
世界が勇気ある決断を待っています。
日本政府に訴えます。
核兵器のない世界を目指してリーダーシップをとり、
核兵器を持つ国々と持たない国々の
橋渡し役を務めると明言しているにも関わらず、
核兵器禁止条約の交渉会議にさえ参加しない姿勢を、
被爆地は到底理解できません。
唯一の戦争被爆国として、
核兵器禁止条約への一日も早い参加を目指し、
核の傘に依存する政策の見直しを進めてください。
日本の参加を国際社会は待っています。
また、二度と戦争をしてはならないと固く決意した
日本国憲法の平和の理念と非核三原則の厳守を世界に発信し、
核兵器のない世界に向けて前進する
具体的方策の一つとして、
今こそ「北東アジア非核兵器地帯」構想の検討を求めます。
私たちは決して忘れません。
1945年8月9日午前11時2分、
今、私たちがいるこの丘の上空で原子爆弾がさく裂し、
15万人もの人々が死傷した事実を。
あの日、原爆の凄(すさ)まじい熱線と爆風によって、
長崎の街は一面の焼野原(やけのはら)となりました。
皮ふが垂れ下がりながらも、
家族を探し、さ迷い歩く人々。
黒焦げの子どもの傍らで、
茫然(ぼうぜん)と立ちすくむ母親。
街のあちこちに地獄のような光景がありました。
十分な治療も受けられずに、多くの人々が死んでいきました。
そして72年経った今でも、
放射線の障害が被爆者の体をむしばみ続けています。
原爆は、いつも側にいた
大切な家族や友だちの命を
無差別に奪い去っただけでなく、
生き残った人たちのその後の人生を
も無惨(むざん)に狂わせたのです。
世界各国のリーダーの皆さん。被爆地を訪れてください。
遠い原子雲の上からの視点ではなく、
原子雲の下で何が起きたのか、
原爆が人間の尊厳をどれほど残酷に踏みにじったのか、
あなたの目で見て、耳で聴いて、
心で感じてください。
もし自分の家族がそこにいたら、と考えてみてください。
人はあまりにもつらく苦しい体験をしたとき、
その記憶を封印し、語ろうとはしません。
語るためには思い出さなければならないからです。
それでも被爆者が、
心と体の痛みに耐えながら体験を語ってくれるのは、
人類の一員として、私たちの未来を守るために、
懸命に伝えようと決意しているからです。
世界中のすべての人に呼びかけます。
最も怖いのは無関心なこと、
そして忘れていくことです。
戦争体験者や被爆者からの
平和のバトンを途切れさせることなく
未来へつないでいきましょう。
今、長崎では平和首長会議の総会が開かれています。
世界の7400の都市が参加する
このネットワークには、
戦争や内戦などつらい記憶を持つまちの代表も大勢参加しています。
被爆者が私たちに示してくれたように、
小さなまちの平和を願う思いも、力を合わせれば、
そして
あきらめなければ、世界を動かす力になることを、
ここ長崎から、
平和首長会議の仲間たちとともに世界に発信します。
そして、
被爆者が声をからして訴え続けてきた
「長崎を最後の被爆地に」
という言葉が、
人類共通の願いであり、意志であることを示します。
被爆者の平均年齢は81歳を超えました。
「被爆者がいる時代」の終わりが近づいています。
日本政府には、
被爆者のさらなる援護の充実と、
被爆体験者の救済を求めます。
福島の原発事故から6年が経ちました。
長崎は放射能の脅威を経験したまちとして、
福島の被災者に寄り添い、応援します。
原子爆弾で亡くなられた方々に心から追悼の意を捧げ、
私たち長崎市民は、
核兵器のない世界を願う世界の人々と連携して、
核兵器廃絶と恒久平和の実現に
力を尽くし続けることをここに宣言します。
2017年(平成29年)8月9日 長崎市長 田上富久
今、核戦争に繫がりかねない、きな臭い報が、
駆け巡っています。
起こってからでは遅いし、
地球・人類の破滅です。
私が夢描くことは、日本の政治家が、
緊張する国々の“橋渡し役”を誠実に実行して、
ノーベル平和賞、を貰って、
歴史に、レガシーを刻まないか・・・?!
という、願いです。m(_ _)m(T_T)m(_ _)m
72年前の朝8時15分、
一発の原子爆弾が、広島に投下され、
広島は、焦土と化し、
今も死者数を特定出来ない程の
多くの方が命を奪われ、
生存された方も、以後ずっと、
被爆の後遺症と辛い記憶と偏見に苦しみ、
ですが、
人々の復興への意欲と取り組みによって
広島は、自然を取り戻し、
世界に向かって、核兵器廃絶を呼びかけています。
今朝の、
広島平和祈念式典の中継動画です。
http://www.fnn-news.com/
被爆者の証言集です。
http://a-bombdb.pcf.city.hiroshima.jp/pdbj/search/col_testify
72年前の朝、
私は2歳の赤ちゃんでした。
72年前の記憶は絶無ですが、
それ以後の、広島の歩みは、
少しずつでも勉強させて頂いてます。
松井一實広島市長の平和宣言、
そして、
二人の小学校6年生の「未来への誓い」
が、深く心に残りました。
世界で唯一の被爆国である日本の政府も、
被爆者救済と、
核兵器廃絶に向かって、
本腰を入れて、
力強い一歩を進めて欲しい!!!
と、強く願って、鎮魂と未来への誓いに、
改めて、頭を垂れる元2歳赤児の私です。m(_ _)m
一発の原子爆弾が、広島に投下され、
広島は、焦土と化し、
今も死者数を特定出来ない程の
多くの方が命を奪われ、
生存された方も、以後ずっと、
被爆の後遺症と辛い記憶と偏見に苦しみ、
ですが、
人々の復興への意欲と取り組みによって
広島は、自然を取り戻し、
世界に向かって、核兵器廃絶を呼びかけています。
今朝の、
広島平和祈念式典の中継動画です。
http://www.fnn-news.com/
被爆者の証言集です。
http://a-bombdb.pcf.city.hiroshima.jp/pdbj/search/col_testify
72年前の朝、
私は2歳の赤ちゃんでした。
72年前の記憶は絶無ですが、
それ以後の、広島の歩みは、
少しずつでも勉強させて頂いてます。
松井一實広島市長の平和宣言、
そして、
二人の小学校6年生の「未来への誓い」
が、深く心に残りました。
世界で唯一の被爆国である日本の政府も、
被爆者救済と、
核兵器廃絶に向かって、
本腰を入れて、
力強い一歩を進めて欲しい!!!
と、強く願って、鎮魂と未来への誓いに、
改めて、頭を垂れる元2歳赤児の私です。m(_ _)m
今、核兵器開発問題を巡って、
誇示ってる北朝鮮政府と
それを牽制しようとする諸国政府の
“綱引き”がビミョーな段階で、
膠着していますが、
米国トランプ米大統領は1日、
適切な状況になれば
北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長と
会談する意向を明らかにしました。
あくまでも適切な状況の下で、会うつもり、
との、
注目すべき発言をしました。
私は、大いに期待して居ます。
朗報!
それとも、トラップ?
いや、トランプ!
茶化したら、イカンね・・・
話し合い解決への道、努力を
深く、強く期待する、
連日、夜空を見上げて心配する
庶民の私です。m(_ _)mm(_ _)m(>_<)
誇示ってる北朝鮮政府と
それを牽制しようとする諸国政府の
“綱引き”がビミョーな段階で、
膠着していますが、
米国トランプ米大統領は1日、
適切な状況になれば
北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長と
会談する意向を明らかにしました。
あくまでも適切な状況の下で、会うつもり、
との、
注目すべき発言をしました。
私は、大いに期待して居ます。
朗報!
それとも、トラップ?
いや、トランプ!
茶化したら、イカンね・・・

話し合い解決への道、努力を
深く、強く期待する、
連日、夜空を見上げて心配する
庶民の私です。m(_ _)mm(_ _)m(>_<)
昨日号に続き、
オバマ米国大統領の真珠湾での演説です。
安倍総理大臣、本日の総理のご出席と心のこもったステートメントは和解の力を証明する歴史的な行為であり、米国民を代表して感謝申し上げます。
また、米国と日本の人々の同盟関係は、戦争による最も深い傷でさえも友情と恒久平和に取って代わられることを私たちに想起させるものであり、謝意を表します。ご列席の皆様、米軍関係者、そしてそのなによりも真珠湾攻撃の生存者の方々及びその大切な人へ。アロハ!
米国人、特にハワイを郷里とする者にとって、この真珠湾は神聖な場所です。未だ嘆き悲しむこの湾に献花し、また花びらを投げ入れるとき、私たちは2400名を超える米国の愛国者たち、天の帆桁で永遠の敬礼をする父や夫、妻や娘を思います。
毎年12月7日になるといつもより少し背筋を正すオアフの守護者に敬礼し、そしてここで75年前に示された勇姿に思いを馳せるのです。
12月のその日、夜が明けると、楽園はこれまでにないほど魅力的でした。水は温かく。そして現実と思えないほどに青く。水兵たちは食堂で食事をしたり、教会に行く準備をしたり、自由を胸にこぎれいな白い半ズボンとTシャツを身につけたりしていました。
湾では、船舶がきちんと列をなして停泊していました。カリフォルニア号、メリーランド号、オクラホマ号、テネシー号、ウエストバージニア号、ネバダ号、そしてアリゾナ号のデッキでは海軍の音楽隊がチューニングをしていました。
その朝、兵士の肩に記された階級は、彼らの胸に宿る勇気ほどに意味をなしませんでした。彼らはこの海において、あらゆる手を尽くして自己を防衛しました。
あるアフリカ系アメリカ人の食堂の給仕係は、普段であれば清掃の役割しか与えられていなかったが、この日、司令官を安全な場所に運び、そして弾薬がなくなるまで地対空砲を打ち続けました。
私たちは、ウエストバージニア号の1級砲撃手であったジム・ダウニングのようなアフリカ人を誇りに思います。真珠湾に急行する前、彼の新妻は彼の手に聖書の言葉の一節を握らせました。「永遠なる神は女の拠り所、その永遠なる胸に抱かれて」というものです。
ジムが戦艦を守ろうと戦っている最中、彼は同時に倒れた者たちの名前を記録しました。家族にその事実を伝えることができるようにするためです。彼は言いました「人がする当然のことです」と。
私たちはハリー・バンのようなアメリカ人を記憶しています。彼はホノルル出身の消防士で、荒れ狂う火を前にし、最後の命を取り綴り、燃える戦闘機の鎮火に取り組みました。彼はパーブル・ハート勲章(名誉負傷)を民間人の消防士として唯一受賞した人です。
私たちは、2時間以上もの間、50口径のマシンガンを撃ち続け、20回以上も負傷し、最も高位の軍人の勲章である名誉勲章を受章したジョン・フリン上等兵層のようなアメリカ人に敬意を表します。
私たちは、戦争のもっとも永続的な価値に対し如何に挑戦するかについて思いを馳せます。日系アメリカ人が如何にして戦争期間中、自由を奪われたのでしょうか。米国史上最も勲章を受章した部隊は、日系アメリカ人2世の舞台である第100歩兵大隊と442連隊でした。私の友達でハワイ出身の上院議員、ダニエル・イノウエさんも所属していました。彼はずっとここに住んでいます。そして私は上院議員になったとき、彼の友人であることを誇りに思いました。彼は名誉勲章、そして自由勲章を授与されました。そして彼の世代で最も偉大な政治家の一人です。
第二次世界大戦における米国の最初の戦場である、ここ真珠湾で、私たちの国は奮起しました。多くの点で、この場所でアメリカ人は成熟したのです。私の祖父母を含め、多くの世代のアメリカ人は戦争を求めたりしませんでした。しかしながら、彼らは戦争から身を背けることを拒否し、経営の場や工場においてその役割を果たしました。そして75年後、誇り高い真珠湾攻撃の生存者の層は、時間の経過とともに薄くなってきています。この場で私たちが思い出す勇者は、私たちの国の心に永遠に生き続けます。真珠湾、そして第二次大戦の退役軍人の皆さん、立ち上がるか手を挙げていただけますでしょうか。感謝の心に富むこの国は、皆さんに御礼申し上げます。
国の本質は、戦時において試されますが、平時において定義されます。人類史上最も恐ろしい期間の一つ、太平洋を渡り悲惨な戦闘により、何百万もの命が奪われた時期の後、米国と日本は何十年もの間、友好と平和を示しています。私たちの同盟は、両国をより繁栄させています。同盟は、新たな世界大戦を予防し、何十億もの人々とを貧困から救った国際秩序の強化に貢献しています。そして本日、米国と日本の同盟は、共通の利益によって結ばれ、共通の価値に基づき、アジア太平洋の平和と安定の礎となっており、世界の進歩を推進する力となっています、実際、私たちの同盟はこれまでにないほど強固なものとなっています。
よい時も悪い時も、私たちはお互いを助けるためにいます。5年前、津波が日本と原子炉を襲い掛かり、福島の原子炉が融解したとき、米軍人は私たちの日本の友人を助けました。世界の中で米日はアジア太平洋地域と世界における安全を強化するために協力しています。たとえば、海賊を後退させ、疾病と戦い、核兵器の拡散を遅らせ、戦時の領土において平和を維持しています。
そして本年前半には、真珠湾の近郊で日米両国の人々は、24か国とともに世界で最大の海上軍事訓練を実施しました。この訓練にはハリー・ハリス司令官が率いる米太平洋軍も参加しました。
ハリス司令官は、米国人の海軍兵を父に、日本人を母に持っています。ハリーは横須賀で生まれましたが、それは彼のテネシーなまりからわからないでしょう。ハリー、あなたの誇りあるリーダーシップに感謝します。
このような観点から、本日私たちがここにいること、安倍総理がここにいることは、国と国、そして人と人との間に何が可能であるかということを気づかせてくれます。戦争は終わります。もっとも厳しい敵対関係にあったものが、最も強い同盟関係を結ぶことができます。平和という果実は、戦争による略奪をはるかに上回るものです。これが真珠湾のゆるぎない事実です。
この場所で、憎しみの炎が最も強く燃え盛る時も、部族間の争いがあるときも、私たちは内向きになったり、私たちとは異なる者とを悪のように扱うといった欲求に抗わなければならないということを想起します。ここで払われた犠牲や戦争による怒りは、私たちの皆の中にある共通項を探すことで思い出させてくれます。これは、日本の友人の言葉を借りれば「オタガイノタメニ」、つまり「相手とともにあって、相手のために尽くす」よう努力することを求めています。これがミズーリ号に乗船していたウィリアム・キラハン船長による教訓です。彼は、彼の船が日本人のパイロットによって攻撃を受けた後も、同パイロットの遺体を米国兵が縫製した日本の国旗で包み、軍葬儀の礼を行うよう指示しました。そしてこれは何年もあとになって真珠湾を再訪し、米国海軍のラッパ手と友人となり、同ラッパ手に軍葬の際に流される曲を演奏してもらうように依頼し、毎月2本のバラの花(1本は米国の犠牲者に、もう一本は日本の犠牲者に)をこの記念館に飾ることとなった。日本人パイロットによる教訓でもあります。
これは、2人の人がいかにもっとも平凡な方法で学ぶことができるかという点についての教訓です。多くの米国人が東京で勉強し、日本の若者も全米で勉強しています。日米の科学者はともに、がんに取り組み、気候変動と闘い、星を探査しています。またこれはマイアミのスタジアムを明るくし、米国人と日本人が共有する誇りによってともに元気づけられている。野球のイチロー選手についてもいえることです。米国人と日本人は平和と友情で結ばれています。
それぞれ国として、そして人として、私たちは私たちが引き継ぐ歴史を選ぶことはできません。しかし、そこからどのような教訓を学び、そして歴史を使ってどのように私たちの未来の計画を立てるかということは選ぶことができます。
安倍総理、私は友情の精神に基づき、あなたをここに歓迎します。それは日本人の人々が常に私を歓迎してくれたことと同様です。私たちが協働することによって、世界に対して、前に進むにあたっては戦争よりも平和によって多くのことを勝ち得ることができる。そして報復よりも若いがより多くの報償をもたらすというメッセージを送ることができることを期待します。
この静かな港で、私たちは亡くなられた方々に対して敬意を表し、我々両国が友人として勝ち得たすべてに対して感謝を表明します。神が戦没者をとこしえの胸に抱え、海が退役軍人を見守り、皆が私たちのために番をしてくださいますように私たちに神の御恵みを
U.S. President Barack Obama, at the Arizona Memorial on Dec. 27, 2016
---
Prime Minister Abe, on behalf of the American people, thank you for your gracious words. Thank you for your presence here today -- a historic gesture that speaks to the power of reconciliation and the alliance between the American and Japanese peoples, a reminder that even the deepest wounds of war can give way to friendship and lasting peace.
Distinguished guests, members of our armed forces -- and most of all survivors of Pearl Harbor and their loved ones -- aloha.
To Americans, especially to those of us who call Hawaii home, this harbor is a sacred place. As we lay a wreath or toss flowers into waters that still weep, we think of the more than 2,400 American patriots -- fathers and husbands, wives and daughters -- manning heaven's rails for all eternity. We salute the defenders of Oahu, who pull themselves a little straighter every December 7th, and we reflect on the heroism that shone here 75 years ago.
As dawn broke that December day, paradise never seemed so sweet. The water was warm and impossibly blue. Sailors ate in the mess hall or readied themselves for church, dressed in crisp white shorts and T-shirts. In the harbor, ships at anchor floated in neat rows: the California, the Maryland, and the Oklahoma, the Tennessee, the West Virginia, and the Nevada. On the deck of the Arizona, the Navy Band was tuning up.
That morning, the ranks on men's shoulders defined them less than the courage in their hearts. Across the island, Americans defended themselves however they could, firing training shells, working old bolt-action rifles. An African-American mess steward, who would typically be confined to cleaning duties, carried his commander to safety and then fired an anti-aircraft gun until he ran out of ammo.
We honor Americans like Jim Downing, a gunner's mate first class of the West Virginia. Before he raced to the harbor, his new bride pressed into his hand a verse of Scripture. "The eternal God is thy refuge, and underneath are the everlasting arms." As Jim fought to save his ship, he simultaneously gathered the names of the fallen so that he could give closure to their families. He said, "It was just something you do."
We remember Americans like Harry Pang, a fireman from Honolulu who, in the face of withering fire, worked to douse burning planes until he gave his "last full measure of devotion" -- one of the only civilian firefighters, ever, to receive the Purple Heart.
We salute Americans like chief petty officer John Finn, who manned a .50-caliber machine gun for more than two hours and was wounded more than 20 times, earning him our nation's highest military decoration, the Medal of Honor.
And it is here that we reflect on how war tests our most enduring values -- how even as Japanese-Americans were deprived of their own liberty during the war, one of the most decorated military units in the history of the United States was the 442nd Infantry Regiment and its 100th Infantry Battalion -- the Japanese-American Nisei.
In that 442nd served my friend and proud Hawaiian, Daniel Inouye, a man who was a Senator from Hawaii for most of my life, and with whom I would find myself proud to serve in the Senate chamber, a man who was not only the recipient of the Medal of Honor and the Presidential Medal of Freedom, but was one of the most distinguished statesmen of his generation as well.
Here at Pearl Harbor, America's first battle of the Second World War roused the nation. Here, in so many ways, America came of age. A generation of Americans -- including my grandparents -- that "Greatest Generation," they did not seek war but they refused to shrink from it, and they all did their part, on fronts and in factories. And while 75 years later the proud ranks of Pearl Harbor survivors have thinned with time, the bravery we recall here is forever etched in our national heart.
I would ask all our Pearl Harbor and World War II veterans who are able to, to please stand or raise your hands, because a grateful nation thanks you.
The character of nations is tested in war, but it is defined in peace. After one of the most horrific chapters in human history -- one that took not tens of thousands but tens of millions of lives -- with ferocious fighting, across this ocean --the United States and Japan chose friendship and they chose peace.
Over the decades, our alliance has made both of our nations more successful. It has helped underwrite an international order that has prevented another world war, and that has lifted more than a billion people out of extreme poverty.
Today, the alliance between the United States and Japan -- bound not only by shared interests but also rooted in common values -- stands as the cornerstone of peace and stability in the Asia-Pacific and a force for progress around the globe. Our alliance has never been stronger. In good times and in bad, we are there for each other.
Recall five years ago, when a wall of water bored down on Japan and reactors in Fukushima melted. America's men and women in uniform were there to help our Japanese friends.
Across the globe, the United States and Japan work shoulder to shoulder to strengthen the security of the Asia-Pacific and the world, turning back piracy, combating disease, slowing the spread of nuclear weapons, keeping the peace in war-torn lands.
Earlier this year, near Pearl Harbor, Japan joined with two dozen nations in the world's largest maritime military exercise, and that included our forces from U.S. Pacific Command, led by Admiral Harry Harris, the son of an American naval officer and a Japanese mother. Harry was born in Yokosuka, but you wouldn't know it from his Tennessee twang.
Thank you, Harry, for your outstanding leadership.
In this sense, our presence here today -- the connections not just between our governments but between our people, the presence of Prime Minister Abe here today -- remind us of what is possible between nations and between peoples. Wars can end. The most bitter of adversaries can become the strongest of allies. The fruits of peace always outweigh the plunder of war. This is the enduring truth of this hallowed harbor. It is here that we remember that, even when hatred burns hottest, even when the tug of tribalism is at its most primal, we must resist the urge to turn inward. We must resist the urge to demonize those who are different.
The sacrifice made here, the anguish of war, reminds us to seek the divine spark that is common to all humanity. It insists that we strive to be what our Japanese friends call "otagai no tame ni" -- "with, and for each other." That's the lesson of Captain William Callaghan of the Missouri. Even after an attack on his ship, he ordered that the Japanese pilot be laid to rest with military honors, wrapped in a Japanese flag sewn by American sailors. It's the lesson, in turn, of the Japanese pilot who, years later, returned to this harbor, befriended an old Marine bugler, and asked him to play "Taps" and lay two roses at this memorial every month -- one for America's fallen and one for Japan's.
It's a lesson our two peoples learn every day, in the most ordinary of ways -- whether it's Americans studying in Tokyo, young Japanese studying across America, scientists from our two nations together unraveling the mysteries of cancer or combating climate change, exploring the stars. It's a baseball player like Ichiro, "lighting up" a stadium in Miami, buoyed by the shared pride of two peoples, both American and Japanese, united in peace and friendship.
As nations and as people, we cannot choose the history that we inherit, but we can choose what lessons to draw from it, and use those lessons to chart our own futures.
Prime Minister Abe, I welcome you here in the spirit of friendship, as the people of Japan have always welcomed me. I hope that, together, we send a message to the world that there is more to be won in peace than in war, that reconciliation carries more rewards than retribution. Here, in this quiet harbor, we honor those we lost, and we give thanks for all that our two nations have won -- together as friends.
May God hold the fallen in his everlasting arms. May he watch over our veterans and all who stand guard on our behalf. May God bless us all.
Thank you.。
~~~~~~~~~~~
日米両首脳の、真珠湾訪問についての自分なりの所感は、
追い追い、このブログで書き加えたいと思っています。
信じられるか? 眉唾ものか?
言葉と行動が一致してしているか、してないか・・・?!
戦争の犠牲者への思いは、どうなのか・・・?!
英語は、頂いたコメントから転載して、
お勉強したいと思います。夢想花m(_ _)m
オバマ米国大統領の真珠湾での演説です。
安倍総理大臣、本日の総理のご出席と心のこもったステートメントは和解の力を証明する歴史的な行為であり、米国民を代表して感謝申し上げます。
また、米国と日本の人々の同盟関係は、戦争による最も深い傷でさえも友情と恒久平和に取って代わられることを私たちに想起させるものであり、謝意を表します。ご列席の皆様、米軍関係者、そしてそのなによりも真珠湾攻撃の生存者の方々及びその大切な人へ。アロハ!
米国人、特にハワイを郷里とする者にとって、この真珠湾は神聖な場所です。未だ嘆き悲しむこの湾に献花し、また花びらを投げ入れるとき、私たちは2400名を超える米国の愛国者たち、天の帆桁で永遠の敬礼をする父や夫、妻や娘を思います。
毎年12月7日になるといつもより少し背筋を正すオアフの守護者に敬礼し、そしてここで75年前に示された勇姿に思いを馳せるのです。
12月のその日、夜が明けると、楽園はこれまでにないほど魅力的でした。水は温かく。そして現実と思えないほどに青く。水兵たちは食堂で食事をしたり、教会に行く準備をしたり、自由を胸にこぎれいな白い半ズボンとTシャツを身につけたりしていました。
湾では、船舶がきちんと列をなして停泊していました。カリフォルニア号、メリーランド号、オクラホマ号、テネシー号、ウエストバージニア号、ネバダ号、そしてアリゾナ号のデッキでは海軍の音楽隊がチューニングをしていました。
その朝、兵士の肩に記された階級は、彼らの胸に宿る勇気ほどに意味をなしませんでした。彼らはこの海において、あらゆる手を尽くして自己を防衛しました。
あるアフリカ系アメリカ人の食堂の給仕係は、普段であれば清掃の役割しか与えられていなかったが、この日、司令官を安全な場所に運び、そして弾薬がなくなるまで地対空砲を打ち続けました。
私たちは、ウエストバージニア号の1級砲撃手であったジム・ダウニングのようなアフリカ人を誇りに思います。真珠湾に急行する前、彼の新妻は彼の手に聖書の言葉の一節を握らせました。「永遠なる神は女の拠り所、その永遠なる胸に抱かれて」というものです。
ジムが戦艦を守ろうと戦っている最中、彼は同時に倒れた者たちの名前を記録しました。家族にその事実を伝えることができるようにするためです。彼は言いました「人がする当然のことです」と。
私たちはハリー・バンのようなアメリカ人を記憶しています。彼はホノルル出身の消防士で、荒れ狂う火を前にし、最後の命を取り綴り、燃える戦闘機の鎮火に取り組みました。彼はパーブル・ハート勲章(名誉負傷)を民間人の消防士として唯一受賞した人です。
私たちは、2時間以上もの間、50口径のマシンガンを撃ち続け、20回以上も負傷し、最も高位の軍人の勲章である名誉勲章を受章したジョン・フリン上等兵層のようなアメリカ人に敬意を表します。
私たちは、戦争のもっとも永続的な価値に対し如何に挑戦するかについて思いを馳せます。日系アメリカ人が如何にして戦争期間中、自由を奪われたのでしょうか。米国史上最も勲章を受章した部隊は、日系アメリカ人2世の舞台である第100歩兵大隊と442連隊でした。私の友達でハワイ出身の上院議員、ダニエル・イノウエさんも所属していました。彼はずっとここに住んでいます。そして私は上院議員になったとき、彼の友人であることを誇りに思いました。彼は名誉勲章、そして自由勲章を授与されました。そして彼の世代で最も偉大な政治家の一人です。
第二次世界大戦における米国の最初の戦場である、ここ真珠湾で、私たちの国は奮起しました。多くの点で、この場所でアメリカ人は成熟したのです。私の祖父母を含め、多くの世代のアメリカ人は戦争を求めたりしませんでした。しかしながら、彼らは戦争から身を背けることを拒否し、経営の場や工場においてその役割を果たしました。そして75年後、誇り高い真珠湾攻撃の生存者の層は、時間の経過とともに薄くなってきています。この場で私たちが思い出す勇者は、私たちの国の心に永遠に生き続けます。真珠湾、そして第二次大戦の退役軍人の皆さん、立ち上がるか手を挙げていただけますでしょうか。感謝の心に富むこの国は、皆さんに御礼申し上げます。
国の本質は、戦時において試されますが、平時において定義されます。人類史上最も恐ろしい期間の一つ、太平洋を渡り悲惨な戦闘により、何百万もの命が奪われた時期の後、米国と日本は何十年もの間、友好と平和を示しています。私たちの同盟は、両国をより繁栄させています。同盟は、新たな世界大戦を予防し、何十億もの人々とを貧困から救った国際秩序の強化に貢献しています。そして本日、米国と日本の同盟は、共通の利益によって結ばれ、共通の価値に基づき、アジア太平洋の平和と安定の礎となっており、世界の進歩を推進する力となっています、実際、私たちの同盟はこれまでにないほど強固なものとなっています。
よい時も悪い時も、私たちはお互いを助けるためにいます。5年前、津波が日本と原子炉を襲い掛かり、福島の原子炉が融解したとき、米軍人は私たちの日本の友人を助けました。世界の中で米日はアジア太平洋地域と世界における安全を強化するために協力しています。たとえば、海賊を後退させ、疾病と戦い、核兵器の拡散を遅らせ、戦時の領土において平和を維持しています。
そして本年前半には、真珠湾の近郊で日米両国の人々は、24か国とともに世界で最大の海上軍事訓練を実施しました。この訓練にはハリー・ハリス司令官が率いる米太平洋軍も参加しました。
ハリス司令官は、米国人の海軍兵を父に、日本人を母に持っています。ハリーは横須賀で生まれましたが、それは彼のテネシーなまりからわからないでしょう。ハリー、あなたの誇りあるリーダーシップに感謝します。
このような観点から、本日私たちがここにいること、安倍総理がここにいることは、国と国、そして人と人との間に何が可能であるかということを気づかせてくれます。戦争は終わります。もっとも厳しい敵対関係にあったものが、最も強い同盟関係を結ぶことができます。平和という果実は、戦争による略奪をはるかに上回るものです。これが真珠湾のゆるぎない事実です。
この場所で、憎しみの炎が最も強く燃え盛る時も、部族間の争いがあるときも、私たちは内向きになったり、私たちとは異なる者とを悪のように扱うといった欲求に抗わなければならないということを想起します。ここで払われた犠牲や戦争による怒りは、私たちの皆の中にある共通項を探すことで思い出させてくれます。これは、日本の友人の言葉を借りれば「オタガイノタメニ」、つまり「相手とともにあって、相手のために尽くす」よう努力することを求めています。これがミズーリ号に乗船していたウィリアム・キラハン船長による教訓です。彼は、彼の船が日本人のパイロットによって攻撃を受けた後も、同パイロットの遺体を米国兵が縫製した日本の国旗で包み、軍葬儀の礼を行うよう指示しました。そしてこれは何年もあとになって真珠湾を再訪し、米国海軍のラッパ手と友人となり、同ラッパ手に軍葬の際に流される曲を演奏してもらうように依頼し、毎月2本のバラの花(1本は米国の犠牲者に、もう一本は日本の犠牲者に)をこの記念館に飾ることとなった。日本人パイロットによる教訓でもあります。
これは、2人の人がいかにもっとも平凡な方法で学ぶことができるかという点についての教訓です。多くの米国人が東京で勉強し、日本の若者も全米で勉強しています。日米の科学者はともに、がんに取り組み、気候変動と闘い、星を探査しています。またこれはマイアミのスタジアムを明るくし、米国人と日本人が共有する誇りによってともに元気づけられている。野球のイチロー選手についてもいえることです。米国人と日本人は平和と友情で結ばれています。
それぞれ国として、そして人として、私たちは私たちが引き継ぐ歴史を選ぶことはできません。しかし、そこからどのような教訓を学び、そして歴史を使ってどのように私たちの未来の計画を立てるかということは選ぶことができます。
安倍総理、私は友情の精神に基づき、あなたをここに歓迎します。それは日本人の人々が常に私を歓迎してくれたことと同様です。私たちが協働することによって、世界に対して、前に進むにあたっては戦争よりも平和によって多くのことを勝ち得ることができる。そして報復よりも若いがより多くの報償をもたらすというメッセージを送ることができることを期待します。
この静かな港で、私たちは亡くなられた方々に対して敬意を表し、我々両国が友人として勝ち得たすべてに対して感謝を表明します。神が戦没者をとこしえの胸に抱え、海が退役軍人を見守り、皆が私たちのために番をしてくださいますように私たちに神の御恵みを
U.S. President Barack Obama, at the Arizona Memorial on Dec. 27, 2016
---
Prime Minister Abe, on behalf of the American people, thank you for your gracious words. Thank you for your presence here today -- a historic gesture that speaks to the power of reconciliation and the alliance between the American and Japanese peoples, a reminder that even the deepest wounds of war can give way to friendship and lasting peace.
Distinguished guests, members of our armed forces -- and most of all survivors of Pearl Harbor and their loved ones -- aloha.
To Americans, especially to those of us who call Hawaii home, this harbor is a sacred place. As we lay a wreath or toss flowers into waters that still weep, we think of the more than 2,400 American patriots -- fathers and husbands, wives and daughters -- manning heaven's rails for all eternity. We salute the defenders of Oahu, who pull themselves a little straighter every December 7th, and we reflect on the heroism that shone here 75 years ago.
As dawn broke that December day, paradise never seemed so sweet. The water was warm and impossibly blue. Sailors ate in the mess hall or readied themselves for church, dressed in crisp white shorts and T-shirts. In the harbor, ships at anchor floated in neat rows: the California, the Maryland, and the Oklahoma, the Tennessee, the West Virginia, and the Nevada. On the deck of the Arizona, the Navy Band was tuning up.
That morning, the ranks on men's shoulders defined them less than the courage in their hearts. Across the island, Americans defended themselves however they could, firing training shells, working old bolt-action rifles. An African-American mess steward, who would typically be confined to cleaning duties, carried his commander to safety and then fired an anti-aircraft gun until he ran out of ammo.
We honor Americans like Jim Downing, a gunner's mate first class of the West Virginia. Before he raced to the harbor, his new bride pressed into his hand a verse of Scripture. "The eternal God is thy refuge, and underneath are the everlasting arms." As Jim fought to save his ship, he simultaneously gathered the names of the fallen so that he could give closure to their families. He said, "It was just something you do."
We remember Americans like Harry Pang, a fireman from Honolulu who, in the face of withering fire, worked to douse burning planes until he gave his "last full measure of devotion" -- one of the only civilian firefighters, ever, to receive the Purple Heart.
We salute Americans like chief petty officer John Finn, who manned a .50-caliber machine gun for more than two hours and was wounded more than 20 times, earning him our nation's highest military decoration, the Medal of Honor.
And it is here that we reflect on how war tests our most enduring values -- how even as Japanese-Americans were deprived of their own liberty during the war, one of the most decorated military units in the history of the United States was the 442nd Infantry Regiment and its 100th Infantry Battalion -- the Japanese-American Nisei.
In that 442nd served my friend and proud Hawaiian, Daniel Inouye, a man who was a Senator from Hawaii for most of my life, and with whom I would find myself proud to serve in the Senate chamber, a man who was not only the recipient of the Medal of Honor and the Presidential Medal of Freedom, but was one of the most distinguished statesmen of his generation as well.
Here at Pearl Harbor, America's first battle of the Second World War roused the nation. Here, in so many ways, America came of age. A generation of Americans -- including my grandparents -- that "Greatest Generation," they did not seek war but they refused to shrink from it, and they all did their part, on fronts and in factories. And while 75 years later the proud ranks of Pearl Harbor survivors have thinned with time, the bravery we recall here is forever etched in our national heart.
I would ask all our Pearl Harbor and World War II veterans who are able to, to please stand or raise your hands, because a grateful nation thanks you.
The character of nations is tested in war, but it is defined in peace. After one of the most horrific chapters in human history -- one that took not tens of thousands but tens of millions of lives -- with ferocious fighting, across this ocean --the United States and Japan chose friendship and they chose peace.
Over the decades, our alliance has made both of our nations more successful. It has helped underwrite an international order that has prevented another world war, and that has lifted more than a billion people out of extreme poverty.
Today, the alliance between the United States and Japan -- bound not only by shared interests but also rooted in common values -- stands as the cornerstone of peace and stability in the Asia-Pacific and a force for progress around the globe. Our alliance has never been stronger. In good times and in bad, we are there for each other.
Recall five years ago, when a wall of water bored down on Japan and reactors in Fukushima melted. America's men and women in uniform were there to help our Japanese friends.
Across the globe, the United States and Japan work shoulder to shoulder to strengthen the security of the Asia-Pacific and the world, turning back piracy, combating disease, slowing the spread of nuclear weapons, keeping the peace in war-torn lands.
Earlier this year, near Pearl Harbor, Japan joined with two dozen nations in the world's largest maritime military exercise, and that included our forces from U.S. Pacific Command, led by Admiral Harry Harris, the son of an American naval officer and a Japanese mother. Harry was born in Yokosuka, but you wouldn't know it from his Tennessee twang.
Thank you, Harry, for your outstanding leadership.
In this sense, our presence here today -- the connections not just between our governments but between our people, the presence of Prime Minister Abe here today -- remind us of what is possible between nations and between peoples. Wars can end. The most bitter of adversaries can become the strongest of allies. The fruits of peace always outweigh the plunder of war. This is the enduring truth of this hallowed harbor. It is here that we remember that, even when hatred burns hottest, even when the tug of tribalism is at its most primal, we must resist the urge to turn inward. We must resist the urge to demonize those who are different.
The sacrifice made here, the anguish of war, reminds us to seek the divine spark that is common to all humanity. It insists that we strive to be what our Japanese friends call "otagai no tame ni" -- "with, and for each other." That's the lesson of Captain William Callaghan of the Missouri. Even after an attack on his ship, he ordered that the Japanese pilot be laid to rest with military honors, wrapped in a Japanese flag sewn by American sailors. It's the lesson, in turn, of the Japanese pilot who, years later, returned to this harbor, befriended an old Marine bugler, and asked him to play "Taps" and lay two roses at this memorial every month -- one for America's fallen and one for Japan's.
It's a lesson our two peoples learn every day, in the most ordinary of ways -- whether it's Americans studying in Tokyo, young Japanese studying across America, scientists from our two nations together unraveling the mysteries of cancer or combating climate change, exploring the stars. It's a baseball player like Ichiro, "lighting up" a stadium in Miami, buoyed by the shared pride of two peoples, both American and Japanese, united in peace and friendship.
As nations and as people, we cannot choose the history that we inherit, but we can choose what lessons to draw from it, and use those lessons to chart our own futures.
Prime Minister Abe, I welcome you here in the spirit of friendship, as the people of Japan have always welcomed me. I hope that, together, we send a message to the world that there is more to be won in peace than in war, that reconciliation carries more rewards than retribution. Here, in this quiet harbor, we honor those we lost, and we give thanks for all that our two nations have won -- together as friends.
May God hold the fallen in his everlasting arms. May he watch over our veterans and all who stand guard on our behalf. May God bless us all.
Thank you.。
~~~~~~~~~~~
日米両首脳の、真珠湾訪問についての自分なりの所感は、
追い追い、このブログで書き加えたいと思っています。
信じられるか? 眉唾ものか?
言葉と行動が一致してしているか、してないか・・・?!
戦争の犠牲者への思いは、どうなのか・・・?!
英語は、頂いたコメントから転載して、
お勉強したいと思います。夢想花m(_ _)m