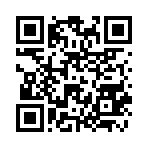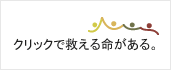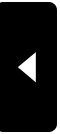きのうの続きで、童謡「シャボン玉」について、ご存知かも知れませんが、少しお話ししますと・・・。
子どもの命と
プライバシーの尊重?
「シャボン玉」の作詞者野口雨情は、生後7日で亡くなったわが子を悲しみ、この歌を作ったと言われています。昔は、医学や衛生水準も低く、食糧事情の悪さもあって、子どもが幼くして亡くなることも多く、「七五三」のお祝いは、子どもの成長を願い祝う切実な行事でした。
シャボン玉飛んだ
屋根まで飛んだ
屋根まで飛んで
こはれて消えた
シャボン玉消えた
飛ばずに消えた
産まれてすぐに
こはれて消えた
風、風、吹くな
シャボン玉飛ばそ
※「シャボン玉」の歌詞は、著作権法の規定により、1995年に著作権が失効したそうです。
切ない事情が背後にあります。子どもの命の危険性・・・人々にとっては、切迫した大変な問題だったでしょう。私の子どもの頃の昭和20年代も、そうした時代だったように覚えていますし、映画もありました。風吹くな、との切なる願いをうたった雨情の気持ち!
 この歌が、今の社会でも提起をしています
この歌が、今の社会でも提起をしています
 。
。
今の時代、医学や衛生、食糧事情によって、未来絶たれる子どもは減りました。しかし、大人の身勝手や虐待によって、未来を奪われる子どもの悲劇が跡を絶ちません。
人権意識の向上もあって「プライバシーの尊重」が、主張されます。これ自体は大事なことですが、
保護者にあたる大人の「プライバシーの尊重」が叫ばれる陰で、子どもが虐待され、子どもの大切な「生存する権利」が脅かされ奪われている現実があるのではないでしょうか? 付近の住民や学校・関係機関の当該保護者への遠慮や配慮の陰で、子どもの命が脅かされ奪われています。
勇み足でもいいから、通報すべきではないか! それを勇気づけ、保障する法整備をすべきでは? 子どもは、声を出せないのです。
野口雨情の願った、シャボン玉が天高く、風吹かれることなく、舞い上がれるよう、もう一度、子どもの日、子どもの成長を願う社会全体の眼を考えましょう! 命に勝る「プライバシーの尊重」はありません!
 児童虐待防止法、民法818条の「親権」規定のあり方、関係機関の権限の強化と体制の増強・・・現実の矛盾に即対応することが求められています
児童虐待防止法、民法818条の「親権」規定のあり方、関係機関の権限の強化と体制の増強・・・現実の矛盾に即対応することが求められています
私も、願いを込めて、詠みました 。
。
風を止め 風にあらがい やよ飛べよ
シャボン玉強く高く 高く強くと
子ども、そして人間は、か細い! ですが、凄い力強さ も持っています
も持っています 。
。
【余談】 きのうは、マイ夫婦の結婚記念日でもアリマシタ。柄にもなく、フランス料理に行っちゃいマシタ
 。
。
子どもの命と
プライバシーの尊重?
「シャボン玉」の作詞者野口雨情は、生後7日で亡くなったわが子を悲しみ、この歌を作ったと言われています。昔は、医学や衛生水準も低く、食糧事情の悪さもあって、子どもが幼くして亡くなることも多く、「七五三」のお祝いは、子どもの成長を願い祝う切実な行事でした。
シャボン玉飛んだ
屋根まで飛んだ
屋根まで飛んで
こはれて消えた
シャボン玉消えた
飛ばずに消えた
産まれてすぐに
こはれて消えた
風、風、吹くな
シャボン玉飛ばそ
※「シャボン玉」の歌詞は、著作権法の規定により、1995年に著作権が失効したそうです。
切ない事情が背後にあります。子どもの命の危険性・・・人々にとっては、切迫した大変な問題だったでしょう。私の子どもの頃の昭和20年代も、そうした時代だったように覚えていますし、映画もありました。風吹くな、との切なる願いをうたった雨情の気持ち!
 この歌が、今の社会でも提起をしています
この歌が、今の社会でも提起をしています
 。
。今の時代、医学や衛生、食糧事情によって、未来絶たれる子どもは減りました。しかし、大人の身勝手や虐待によって、未来を奪われる子どもの悲劇が跡を絶ちません。
人権意識の向上もあって「プライバシーの尊重」が、主張されます。これ自体は大事なことですが、
保護者にあたる大人の「プライバシーの尊重」が叫ばれる陰で、子どもが虐待され、子どもの大切な「生存する権利」が脅かされ奪われている現実があるのではないでしょうか? 付近の住民や学校・関係機関の当該保護者への遠慮や配慮の陰で、子どもの命が脅かされ奪われています。
勇み足でもいいから、通報すべきではないか! それを勇気づけ、保障する法整備をすべきでは? 子どもは、声を出せないのです。
野口雨情の願った、シャボン玉が天高く、風吹かれることなく、舞い上がれるよう、もう一度、子どもの日、子どもの成長を願う社会全体の眼を考えましょう! 命に勝る「プライバシーの尊重」はありません!
 児童虐待防止法、民法818条の「親権」規定のあり方、関係機関の権限の強化と体制の増強・・・現実の矛盾に即対応することが求められています
児童虐待防止法、民法818条の「親権」規定のあり方、関係機関の権限の強化と体制の増強・・・現実の矛盾に即対応することが求められています
私も、願いを込めて、詠みました
 。
。風を止め 風にあらがい やよ飛べよ
シャボン玉強く高く 高く強くと
子ども、そして人間は、か細い! ですが、凄い力強さ
 も持っています
も持っています 。
。【余談】 きのうは、マイ夫婦の結婚記念日でもアリマシタ。柄にもなく、フランス料理に行っちゃいマシタ

 。
。 薄曇り時々気まぐれ晴れ
 薄曇り時々気まぐれ晴れ
薄曇り時々気まぐれ晴れ といった昨日の昼、妻と愛東マーガレットステーションに自動車で到着。しのぶえ千草さんという篠笛の女性奏者のコンサートがあり、“しゃぼん玉”“琵琶湖周航の歌”“赤とんぼ”などの童謡・古歌演奏を聞き、歌いました
といった昨日の昼、妻と愛東マーガレットステーションに自動車で到着。しのぶえ千草さんという篠笛の女性奏者のコンサートがあり、“しゃぼん玉”“琵琶湖周航の歌”“赤とんぼ”などの童謡・古歌演奏を聞き、歌いました 。ステーションには、例年より多い子連れのお客さん。ソフトクリームを買うにも長蛇の列。。。。。不況と新型インフルエンザに抗して、人々の笑いが逞しく響いていました。ただ、平気で人の傍をわきまえずタバコを吸う人のあることには閉口
。ステーションには、例年より多い子連れのお客さん。ソフトクリームを買うにも長蛇の列。。。。。不況と新型インフルエンザに抗して、人々の笑いが逞しく響いていました。ただ、平気で人の傍をわきまえずタバコを吸う人のあることには閉口
 子どもの傍でも平気で吸いよる
子どもの傍でも平気で吸いよる

 思わず注意が、喉まで、出かかりましたが、喧嘩の恐れ大ですので、すんでの所で止めました
思わず注意が、喉まで、出かかりましたが、喧嘩の恐れ大ですので、すんでの所で止めました 。
。
根性なしやねぇ 。
。
うれしかったこと・・・しのぶえ千草さん手作りの、「子どもの日」明日ですがいや今日です が、に因んだ新聞紙製かぶとも2つ頂きました。謝謝!
が、に因んだ新聞紙製かぶとも2つ頂きました。謝謝!
夕方は、静岡在住の姪・夫君・子息が、乗用車で岡山と京都への墓参りの帰途来宅。墓参りの報告その他諸々の話の花が咲きました。それにしても、姪の速射砲のような話のトーン!と、言ったら怒られるかな ?!
?!


 実は、あまりにドラマチック(?)な野良猫
実は、あまりにドラマチック(?)な野良猫 親子物語もありました。見事なまでの親猫の子猫たちへの愛情と純粋な行動、それに比べて人間の思惑の右往左往???!・・・持って回ったような言い方ですが、私の気持ちがなかなかまとまらないのです
親子物語もありました。見事なまでの親猫の子猫たちへの愛情と純粋な行動、それに比べて人間の思惑の右往左往???!・・・持って回ったような言い方ですが、私の気持ちがなかなかまとまらないのです 。近日中予定。
。近日中予定。
 薄曇り時々気まぐれ晴れ
薄曇り時々気まぐれ晴れ といった昨日の昼、妻と愛東マーガレットステーションに自動車で到着。しのぶえ千草さんという篠笛の女性奏者のコンサートがあり、“しゃぼん玉”“琵琶湖周航の歌”“赤とんぼ”などの童謡・古歌演奏を聞き、歌いました
といった昨日の昼、妻と愛東マーガレットステーションに自動車で到着。しのぶえ千草さんという篠笛の女性奏者のコンサートがあり、“しゃぼん玉”“琵琶湖周航の歌”“赤とんぼ”などの童謡・古歌演奏を聞き、歌いました 。ステーションには、例年より多い子連れのお客さん。ソフトクリームを買うにも長蛇の列。。。。。不況と新型インフルエンザに抗して、人々の笑いが逞しく響いていました。ただ、平気で人の傍をわきまえずタバコを吸う人のあることには閉口
。ステーションには、例年より多い子連れのお客さん。ソフトクリームを買うにも長蛇の列。。。。。不況と新型インフルエンザに抗して、人々の笑いが逞しく響いていました。ただ、平気で人の傍をわきまえずタバコを吸う人のあることには閉口
 子どもの傍でも平気で吸いよる
子どもの傍でも平気で吸いよる

 思わず注意が、喉まで、出かかりましたが、喧嘩の恐れ大ですので、すんでの所で止めました
思わず注意が、喉まで、出かかりましたが、喧嘩の恐れ大ですので、すんでの所で止めました 。
。根性なしやねぇ
 。
。うれしかったこと・・・しのぶえ千草さん手作りの、「子どもの日」明日ですがいや今日です
 が、に因んだ新聞紙製かぶとも2つ頂きました。謝謝!
が、に因んだ新聞紙製かぶとも2つ頂きました。謝謝!夕方は、静岡在住の姪・夫君・子息が、乗用車で岡山と京都への墓参りの帰途来宅。墓参りの報告その他諸々の話の花が咲きました。それにしても、姪の速射砲のような話のトーン!と、言ったら怒られるかな
 ?!
?!

 実は、あまりにドラマチック(?)な野良猫
実は、あまりにドラマチック(?)な野良猫 親子物語もありました。見事なまでの親猫の子猫たちへの愛情と純粋な行動、それに比べて人間の思惑の右往左往???!・・・持って回ったような言い方ですが、私の気持ちがなかなかまとまらないのです
親子物語もありました。見事なまでの親猫の子猫たちへの愛情と純粋な行動、それに比べて人間の思惑の右往左往???!・・・持って回ったような言い方ですが、私の気持ちがなかなかまとまらないのです 。近日中予定。
。近日中予定。 きょう、5月5日は「子どもの日」。この日に寄せて、「ドロシー・ロー・ノルト」というアメリカの家庭教育学者の作った「子ども」という詩をご紹介します。この詩は、スウェーデンの中学校の社会科の教科書「あなた自身の社会」(アーネ・リンドクウィスト,ヤン・ウェステル著,川上邦夫訳:新評論から出版:155頁)に収載されています。この詩の作者、ドロシー・ロー・ノルト(Dorothy Law Nolte)は、この教科書では、ノルトはホルトとなっています。
子ども
批判ばかりされた 子どもは
非難することを おぼえる
殴られて大きくなった 子どもは
力にたよることを おぼえる
笑いものにされた 子どもは
ものを言わずにいることを おぼえる
皮肉にさらされた 子どもは
鈍い良心の もちぬしとなる
しかし,
激励をうけた 子どもは
自信を おぼえる
寛容にであった 子どもは
忍耐を おぼえる
賞賛をうけた 子どもは
評価することを おぼえる
フェアプレーを経験した 子どもは
公正を おぼえる
友情を知る 子どもは
親切を おぼえる
安心を経験した 子どもは
信頼を おぼえる
可愛がられ 抱きしめられた 子どもは
世界中の愛情を 感じとることを おぼえる
※ そんなことは常識ヤと思われるかも知れませんが、人間の赤ちゃんは、容貌も声も仕草も、可愛く生まれ育ちます。赤ちゃんを見たら「可愛い!!」というのが、おきまりの第一声です。親や大人から、可愛がられることを前提条件として、生まれ育っていくよう、遺伝子で設計されているそうですね。親や大人から、可愛がられて、受け止めてもらって、初めて、生存を保障され、人間社会に入っていける・・・。人間の赤ちゃんは、生まれた直後は、例えば猿や馬のような“生活力”はありませんが、生まれてから獲得した後天的な力によって、数年もしないうちに、猿や馬よりも可能性を広げていきます。ですが、その大前提は、親や大人に可愛がられ受け止めて育てられることです。このブログのあちらこちらに私の思いは載せているのですが、4月13日、14日、21日~28日号の辺も見ていただければ有り難いです。
1951(昭和26)年のきょう、「児童憲章」が制定されました。
子ども
批判ばかりされた 子どもは
非難することを おぼえる
殴られて大きくなった 子どもは
力にたよることを おぼえる
笑いものにされた 子どもは
ものを言わずにいることを おぼえる
皮肉にさらされた 子どもは
鈍い良心の もちぬしとなる
しかし,
激励をうけた 子どもは
自信を おぼえる
寛容にであった 子どもは
忍耐を おぼえる
賞賛をうけた 子どもは
評価することを おぼえる
フェアプレーを経験した 子どもは
公正を おぼえる
友情を知る 子どもは
親切を おぼえる
安心を経験した 子どもは
信頼を おぼえる
可愛がられ 抱きしめられた 子どもは
世界中の愛情を 感じとることを おぼえる
※ そんなことは常識ヤと思われるかも知れませんが、人間の赤ちゃんは、容貌も声も仕草も、可愛く生まれ育ちます。赤ちゃんを見たら「可愛い!!」というのが、おきまりの第一声です。親や大人から、可愛がられることを前提条件として、生まれ育っていくよう、遺伝子で設計されているそうですね。親や大人から、可愛がられて、受け止めてもらって、初めて、生存を保障され、人間社会に入っていける・・・。人間の赤ちゃんは、生まれた直後は、例えば猿や馬のような“生活力”はありませんが、生まれてから獲得した後天的な力によって、数年もしないうちに、猿や馬よりも可能性を広げていきます。ですが、その大前提は、親や大人に可愛がられ受け止めて育てられることです。このブログのあちらこちらに私の思いは載せているのですが、4月13日、14日、21日~28日号の辺も見ていただければ有り難いです。
1951(昭和26)年のきょう、「児童憲章」が制定されました。