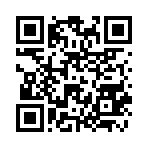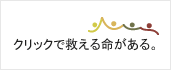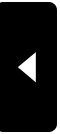テレビのない世界って? ・・・テレビのない世界に突入して、ほぼ、一週間。直すにも、買い換えるにもお金がかかるし、懐具合と長期相談中! の訳の分からん詩(もどき)です
 。
。
テレビのない世界、って?!
テレビのない世界!
「世界」言うたら、大袈裟やなぁ?!
「生活」言う方が、正確かも知れん!
でも、私の語感では、
つい「テレビのない世界」って、言ってしまう、
「テレビのない世界」、って。。。。。。。。
「テレビのない世界」がついに実現!
一週間ほど前、ギターの先が、ちょこんと
テレビ画面に当たったら、
画面に線が猛烈走って、“絵”が見えへん!
“音声”だけの、テレビとの付き合い。
居間のテレビが、あっちゃ向いてホイ!
をやって、今、極めて愛想ナシ、状態!
だから、なんとなしに、テレビの世界から
足を洗って(変な表現?!)
気づいたこと
その1 1日が長い、たっぷりある!
その2 静か
その3 ふと気づいたら、“笑う”ことを忘れてる?
テレビのお笑い番組の効用も、けっこう、あったんだ!
その4 あいた時間、新聞をじっくりと読む
読書は、もう一つ (それは、自分の怠慢!)
その5 趣味の音楽に、やや時間多めに
その6 けど、やっぱり“情報”から取り残されるっ!
その7 はからずも、子どもの頃のテレビのない
ラジオだけの、木箱の雑音混じりの
ラジオ時代のことを、思い出せたこと!
教訓! 人生、半分、悪うても
半分、よい・・・ってか!?

 。
。テレビのない世界、って?!
テレビのない世界!
「世界」言うたら、大袈裟やなぁ?!
「生活」言う方が、正確かも知れん!
でも、私の語感では、
つい「テレビのない世界」って、言ってしまう、
「テレビのない世界」、って。。。。。。。。
「テレビのない世界」がついに実現!
一週間ほど前、ギターの先が、ちょこんと
テレビ画面に当たったら、
画面に線が猛烈走って、“絵”が見えへん!
“音声”だけの、テレビとの付き合い。
居間のテレビが、あっちゃ向いてホイ!
をやって、今、極めて愛想ナシ、状態!
だから、なんとなしに、テレビの世界から
足を洗って(変な表現?!)
気づいたこと
その1 1日が長い、たっぷりある!
その2 静か
その3 ふと気づいたら、“笑う”ことを忘れてる?
テレビのお笑い番組の効用も、けっこう、あったんだ!
その4 あいた時間、新聞をじっくりと読む
読書は、もう一つ (それは、自分の怠慢!)
その5 趣味の音楽に、やや時間多めに
その6 けど、やっぱり“情報”から取り残されるっ!
その7 はからずも、子どもの頃のテレビのない
ラジオだけの、木箱の雑音混じりの
ラジオ時代のことを、思い出せたこと!
教訓! 人生、半分、悪うても
半分、よい・・・ってか!?
昨日のつづきをお送りします。当時の状況のご理解をより容易にするために、かなり前になりますが、昨年の12月28日号につづいて、「目撃戦後日本世相の」変容(3)」という形でお送りします。(文中 敬称略)
昭和20年代後半から昭和30年代前半
たくましき子どもたちと大人
昭和20年代終わり頃から、街にはすこしずつ白黒テレビが出まわり、力道山がわれら子どもたちのヒーローで、日曜日の昼間、私たち子どもは、学校の校舎に忍び込んでマットを敷き、その上でプロレスごっこをした。
公園の一角に、街頭テレビが置かれ、相撲やプロレス、野球に熱狂した。後に、さだまさしが「親父の一番長い日」という唄を歌い、その中で、『街頭テレビ・・・』云々といった一節があるが、私はその歌詞を懐かしく聴いた。
昭和30年代に入って、「もはや戦後ではない」という政府の白書が出たようであるが、まだ、戦後の傷跡もまだ残り、貧しさと繁栄への熱が同居しているような社会だった。この辺は、今井正監督の白黒映画「キクとイサム」にも描かれている。
白黒テレビ・電気冷蔵庫・電気洗濯機といった、いわゆる「三種の電器」が市場に出回ってきた。が、テレビは、町内でも裕福な1~2軒の家にしかなく、私たち子どもは、大挙して、夜、プロレス中継がある時は、テレビのある家へ押しかけて「おばちゃーん、テレビ見せてー!!」と大声で玄関の扉が開くまでわめき続け、強引に見せてもらった。多分、百姓一揆もこんな風だっただろうと思わせるほどの(?)、ド迫力な押しかけだった。なお、テレビのある間の座敷には泥や砂よけのための新聞紙が敷き詰めてあった。
また、当時、子どもたちの人気番組は大村昆ちゃん、芦屋雁乃助、小雁、茶川一郎出演の30分ものの「番頭はんと丁稚どん」だった。口減らしのために奉公にきた昆ちゃんなどの3人の丁稚が雁乃助扮する番頭にいじめられるというお笑い番組で、昆ちゃんが『飴もろうた~』と踊りまくるシーンや、番頭がいじめるけれども間が抜けているのがおかしくて、笑いこけた。この番組も、子どもたちは押しかけ鑑賞をした。やがてもう少しして、藤田まこと・白木みのるの30分舞台劇「てなもんや三度笠」のテレビ放送も人気番組だった。それに「判決」という30分の真面目な弁護士ドラマがあって、『死刑制度』などの社会問題を真摯に取り上げていた。また、実際の指名手配犯人を扱った30分のドキュメント番組を見て、世相の厳しさとこんな人生したらアカンなぁと思った。「番頭はんと丁稚どん」から指名手配犯人のドキュメント番組まで、確か昭和20年代終わりから30年代半ば頃までだった。私は小学校高学年から中学生、高校生とかけて、近所の家のテレビで見て社会観を形成していった。
社会観を形成と言えば、地域社会、すなわち町内のさまざまな人間関係や出来事も、私に大きな影響を与えた。終戦直後から昭和30年代前半まで、マイカーなんてほとんどの家になかった時期だから、年に1回バスを借り切って(これは20年代後半からかも?)、町内の子どもや大人が揃って、1日バス旅行をした。バスの車中で、マイクで私が唄を歌うとみんなが驚いたように「上手やなぁ」と拍手してくれて嬉しかった。町内は、うるさい大人がたくさんいて、子どもが悪さをすると、注意はもちろんのこと、いつも道ばたで花開いていた『井戸端会議』で悪口も言ってくれてうるさかった。子どもたちは、その中でも、とりわけ悪口好きのおばさんを『NHKババァ』と密かに名付けた。しかし、大人はけっこう親切で、腹を空かしていた私に、「これ食べ」と言ってイモや菓子などをくれたり、夏には町内の子どもたちのために地蔵盆を2日がかりでやって、『当てもの』(抽選のこと。私たちは、こう言っていた)で当てた賞品を、2階の窓から、ロープを伝って子どものいる場所に送ってくれたり、ずいぶん凝ったことをしてくれたりした。
毎日夕方に来る紙芝居屋さんにも、子どもたちは『社会』や『生き方』を教えてもらった。テレビが普及してからは駆逐されるように影を潜めていったが、当時紙芝居のおじさんは、確実に、子どもたちの街の先生だった。5円で、お金のない子には3円でも、煎餅に巻いた水飴やアンズを売り、全くお金のない子はタダ見をさせてもらう代わりに、拍子木を叩いて、紙芝居屋さんが来たことを、町内中に触れ回った。子どもたちは、おじさんの名調子の『鞍馬天狗』で鞍馬天狗や杉作少年の生き方に触れ、『鉄仮面』で夢の世界へ飛んだ。 (つづく)
昭和20年代後半から昭和30年代前半
たくましき子どもたちと大人
昭和20年代終わり頃から、街にはすこしずつ白黒テレビが出まわり、力道山がわれら子どもたちのヒーローで、日曜日の昼間、私たち子どもは、学校の校舎に忍び込んでマットを敷き、その上でプロレスごっこをした。
公園の一角に、街頭テレビが置かれ、相撲やプロレス、野球に熱狂した。後に、さだまさしが「親父の一番長い日」という唄を歌い、その中で、『街頭テレビ・・・』云々といった一節があるが、私はその歌詞を懐かしく聴いた。
昭和30年代に入って、「もはや戦後ではない」という政府の白書が出たようであるが、まだ、戦後の傷跡もまだ残り、貧しさと繁栄への熱が同居しているような社会だった。この辺は、今井正監督の白黒映画「キクとイサム」にも描かれている。
白黒テレビ・電気冷蔵庫・電気洗濯機といった、いわゆる「三種の電器」が市場に出回ってきた。が、テレビは、町内でも裕福な1~2軒の家にしかなく、私たち子どもは、大挙して、夜、プロレス中継がある時は、テレビのある家へ押しかけて「おばちゃーん、テレビ見せてー!!」と大声で玄関の扉が開くまでわめき続け、強引に見せてもらった。多分、百姓一揆もこんな風だっただろうと思わせるほどの(?)、ド迫力な押しかけだった。なお、テレビのある間の座敷には泥や砂よけのための新聞紙が敷き詰めてあった。
また、当時、子どもたちの人気番組は大村昆ちゃん、芦屋雁乃助、小雁、茶川一郎出演の30分ものの「番頭はんと丁稚どん」だった。口減らしのために奉公にきた昆ちゃんなどの3人の丁稚が雁乃助扮する番頭にいじめられるというお笑い番組で、昆ちゃんが『飴もろうた~』と踊りまくるシーンや、番頭がいじめるけれども間が抜けているのがおかしくて、笑いこけた。この番組も、子どもたちは押しかけ鑑賞をした。やがてもう少しして、藤田まこと・白木みのるの30分舞台劇「てなもんや三度笠」のテレビ放送も人気番組だった。それに「判決」という30分の真面目な弁護士ドラマがあって、『死刑制度』などの社会問題を真摯に取り上げていた。また、実際の指名手配犯人を扱った30分のドキュメント番組を見て、世相の厳しさとこんな人生したらアカンなぁと思った。「番頭はんと丁稚どん」から指名手配犯人のドキュメント番組まで、確か昭和20年代終わりから30年代半ば頃までだった。私は小学校高学年から中学生、高校生とかけて、近所の家のテレビで見て社会観を形成していった。
社会観を形成と言えば、地域社会、すなわち町内のさまざまな人間関係や出来事も、私に大きな影響を与えた。終戦直後から昭和30年代前半まで、マイカーなんてほとんどの家になかった時期だから、年に1回バスを借り切って(これは20年代後半からかも?)、町内の子どもや大人が揃って、1日バス旅行をした。バスの車中で、マイクで私が唄を歌うとみんなが驚いたように「上手やなぁ」と拍手してくれて嬉しかった。町内は、うるさい大人がたくさんいて、子どもが悪さをすると、注意はもちろんのこと、いつも道ばたで花開いていた『井戸端会議』で悪口も言ってくれてうるさかった。子どもたちは、その中でも、とりわけ悪口好きのおばさんを『NHKババァ』と密かに名付けた。しかし、大人はけっこう親切で、腹を空かしていた私に、「これ食べ」と言ってイモや菓子などをくれたり、夏には町内の子どもたちのために地蔵盆を2日がかりでやって、『当てもの』(抽選のこと。私たちは、こう言っていた)で当てた賞品を、2階の窓から、ロープを伝って子どものいる場所に送ってくれたり、ずいぶん凝ったことをしてくれたりした。
毎日夕方に来る紙芝居屋さんにも、子どもたちは『社会』や『生き方』を教えてもらった。テレビが普及してからは駆逐されるように影を潜めていったが、当時紙芝居のおじさんは、確実に、子どもたちの街の先生だった。5円で、お金のない子には3円でも、煎餅に巻いた水飴やアンズを売り、全くお金のない子はタダ見をさせてもらう代わりに、拍子木を叩いて、紙芝居屋さんが来たことを、町内中に触れ回った。子どもたちは、おじさんの名調子の『鞍馬天狗』で鞍馬天狗や杉作少年の生き方に触れ、『鉄仮面』で夢の世界へ飛んだ。 (つづく)