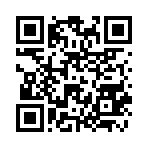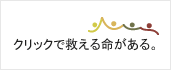今、子どもを巡る状況として
ヤング・ケアラー
を巡る状況が、
強く懸念されています。
それについて、様々、検索しました。
まず、
濱島淑惠教授がNHK「クローズアップ現代」で
語られた内容です。
https://www.osaka-dent.ac.jp/news/2021/H20210519_hamashima_youngcarer_tv.html
~~~~~その内容は~~~~~
特集テーマは
「ヤングケアラー いま大人がすべきこと」。
この中で、濱島先生は、
国が4月に公表した全国調査により、あらためて顕在化した
ヤングケアラー(家族の介護を担う18歳未満の子ども)
の問題について解説されました。
番組では、
ヤングケアラー支援の先進地イギリスの取り組みを紹介。
濱島先生は英国に学ぶ三つのポイントとして
①法制化
②支援メニューの充実
③当事者の運動—を提示されました。
因みに、イギリスは、
濱島先生が「ヤングケアラー」という言葉に
初めて出会った国だ、と言う事です。
この中では、
日本がヤングケアラーの問題に向き合っていく為に
今後何が必要か。
これについて、濱島先生は
「ヤングケアラーに関わる問題は
★ 子どもの人権に関わる事柄であり、
子どもの問題ではあるが、それだけではない。
★ その背後にある大人の問題に注意を払う必要がある。
高齢者福祉、
障がい者福祉、
貧困、社会的孤立、社会的排除
—こうしたさまざまな問題が絡んでおり、
これらが解決されない中で、
そのしわ寄せが子どもたちにいっている。
ヤングケアラーたちはさまざまな困難を抱えることがある。
と、指摘したうえで、
★ ヤングケアラーの支援には
児童福祉や教育というところだけでなく、
さまざまな領域にまたがった包括的な支援が必要になってくる。
★ その意味で、
国には包括的な支援のビジョンを示していただきたいし、
またそれを法制化し、予算化していくという取り組みを期待したい」
★ さらに、
ヤングケアラーが生きやすい社会の姿について
●●一番大事なのは理解。
ヤングケアラーたちがケア経験によって得た価値と、
さまざまな負担・困難。
その両方を理解している人々がたくさんこの社会にいるという事。
★ それが暮らしやすい社会をつくるための第一歩になるのではないか。
★ 最後に、
ヤングケアラーたちにどんな言葉をかけてあげればよいか、
というキャスターの問いに
濱島先生はこう答えました。
大変さはあるかもしれないけれど、あなたたちには価値がある。
大変さと価値—その両方をみながら一緒に考えていこう
と、述べられました。
~~~~~~~~~~~~~~~~
私の子ども・青春期の昭和20~30年代は
社会は、豊かでなかったかも知れませんが、
地域社会の人々の繋がりはかなり有って、
隣近所、お互いに、支えあって来ました。
高度経済成長期を経て、
日本社会が、物質的に豊かに成る一方、
人と人の繋がりは、難しく成ってきた社会での
ヤング・ケアラーの問題の深刻化・・・
その他、
NHK福祉情報サイト です。
https://www.nhk.or.jp/heart-net/article/586/
厚生労働省のHP です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/young-carer.html
全日本おばちゃん党の主張 です。
https://www.nippon.com/ja/in-depth/a04602/
これからの日本・・・
人生の生き方たの多くを学ぶ機会が
保障さtれる・・・
私たちも、
国も、ヤングケアラーについての
理解・施策が深まりますよう、
まだまだ不十分ですが、提起させて下さい。m(__)m
※ このブログで、
ヤング・ケアラー、に触れた号です。
クリックをお願いします。m(__)m
https://poeny.shiga-saku.net/search.php?csrf=b8f76bdd7861b7a9a354b49e21ce95a64fca2d37&search=%E3%83%A4%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B1%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%BC
ヤング・ケアラー
を巡る状況が、
強く懸念されています。
それについて、様々、検索しました。
まず、
濱島淑惠教授がNHK「クローズアップ現代」で
語られた内容です。
https://www.osaka-dent.ac.jp/news/2021/H20210519_hamashima_youngcarer_tv.html
~~~~~その内容は~~~~~
特集テーマは
「ヤングケアラー いま大人がすべきこと」。
この中で、濱島先生は、
国が4月に公表した全国調査により、あらためて顕在化した
ヤングケアラー(家族の介護を担う18歳未満の子ども)
の問題について解説されました。
番組では、
ヤングケアラー支援の先進地イギリスの取り組みを紹介。
濱島先生は英国に学ぶ三つのポイントとして
①法制化
②支援メニューの充実
③当事者の運動—を提示されました。
因みに、イギリスは、
濱島先生が「ヤングケアラー」という言葉に
初めて出会った国だ、と言う事です。
この中では、
日本がヤングケアラーの問題に向き合っていく為に
今後何が必要か。
これについて、濱島先生は
「ヤングケアラーに関わる問題は
★ 子どもの人権に関わる事柄であり、
子どもの問題ではあるが、それだけではない。
★ その背後にある大人の問題に注意を払う必要がある。
高齢者福祉、
障がい者福祉、
貧困、社会的孤立、社会的排除
—こうしたさまざまな問題が絡んでおり、
これらが解決されない中で、
そのしわ寄せが子どもたちにいっている。
ヤングケアラーたちはさまざまな困難を抱えることがある。
と、指摘したうえで、
★ ヤングケアラーの支援には
児童福祉や教育というところだけでなく、
さまざまな領域にまたがった包括的な支援が必要になってくる。
★ その意味で、
国には包括的な支援のビジョンを示していただきたいし、
またそれを法制化し、予算化していくという取り組みを期待したい」
★ さらに、
ヤングケアラーが生きやすい社会の姿について
●●一番大事なのは理解。
ヤングケアラーたちがケア経験によって得た価値と、
さまざまな負担・困難。
その両方を理解している人々がたくさんこの社会にいるという事。
★ それが暮らしやすい社会をつくるための第一歩になるのではないか。
★ 最後に、
ヤングケアラーたちにどんな言葉をかけてあげればよいか、
というキャスターの問いに
濱島先生はこう答えました。
大変さはあるかもしれないけれど、あなたたちには価値がある。
大変さと価値—その両方をみながら一緒に考えていこう
と、述べられました。
~~~~~~~~~~~~~~~~
私の子ども・青春期の昭和20~30年代は
社会は、豊かでなかったかも知れませんが、
地域社会の人々の繋がりはかなり有って、
隣近所、お互いに、支えあって来ました。
高度経済成長期を経て、
日本社会が、物質的に豊かに成る一方、
人と人の繋がりは、難しく成ってきた社会での
ヤング・ケアラーの問題の深刻化・・・
その他、
NHK福祉情報サイト です。
https://www.nhk.or.jp/heart-net/article/586/
厚生労働省のHP です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/young-carer.html
全日本おばちゃん党の主張 です。
https://www.nippon.com/ja/in-depth/a04602/
これからの日本・・・
人生の生き方たの多くを学ぶ機会が
保障さtれる・・・
私たちも、
国も、ヤングケアラーについての
理解・施策が深まりますよう、
まだまだ不十分ですが、提起させて下さい。m(__)m
※ このブログで、
ヤング・ケアラー、に触れた号です。
クリックをお願いします。m(__)m
https://poeny.shiga-saku.net/search.php?csrf=b8f76bdd7861b7a9a354b49e21ce95a64fca2d37&search=%E3%83%A4%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B1%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%BC
迂闊ながら、
今まで、この言葉すら知りませんでした。
先日のテレビ 報道特集 で初めて知りました。
ヤング・ケァラーを説明し、施策の大切さを訴える
成蹊大学文学部准教授・澁谷智子さんのHP です。
http://www.asahi.com/and_w/articles/SDI2018021329511.html
~私なりに、重要点を書きますと~
家族の介護を担う「ヤングケアラー」・・・
慢性的な病気や障害、あるいは
精神的な問題を抱える親やきょうだい、祖父母――。
そんな家族を、
子どもがケアしなければならないケースがある。
18歳未満のこれらの子どもや若者は
「ヤングケアラー」と呼ばれ、
近年、その存在や実態に関心が高まっている。
しかし、
周囲や社会がどう支援したらいいのか、
その道筋は見えていないのが現状。
子どもたちは「介護」や「ケア」という自覚がない。
だけど、、
家事や家の切り盛り、金銭面の切り盛り、
身の回りのケア、
感情面のケア、
きょうだいのケアといったものがあります。
わかりやすいのは家事で、
掃除や料理、お皿洗いや洗濯ですね。
ヤングケアラーは、家のお手伝いというよりは、
もっと重い責任をもって、
家族のための家事を行っています。
それから
買い物をしたり支払いの処理をしたりといった、
物やお金の流れの管理。
着替えやお風呂、
トイレの介助などのケアもあります。
「お母さん、薬飲んで」と声をかけることも、
服薬管理というケアになります。
日本ではまだケアを担っている
子どもたちがいるという認識がなく、
国的な調査がされていないのが現状です。
イギリスでは25年以上前から
ヤングケアラーの存在に目が向けられてきましたが、
011年の国勢調査で2
16万人を超えるヤングケアラーがいることがわかっています。
ヤングケアラープロジェクトとして、
彼らを支援する場所が国内に300ぐらいあり、
例えば
「きょうだいケアラーの日」のように、
同じような立場にいる
特定のタイプのケアラーが集まれる機会もあります。
私も、全く認識不足、と言うより、
認識欠如でした。
今、青春賛歌の、スポーツやドラマ花盛りですが、
ヤング・ケアラーの人たちは、
家に居ることが多く、
社会との接点を失い、
同年齢の友だちとも交流しにく、
それでいて、
社会から認められず、
生き方に自信を失いかねない
若者も居る、とのことです。
これから、一層、高齢化が進み、
ヤング・ケァラーが増える可能性は大きいです。
それでいて、
国の施策も無く、
社会的にも認識されない事態が続くと、
ヤング・ケアラーの人が苦しみます。
私たちも、認識を持ち、
国の施策を要求し、
地域社会としても、応援できる
人間関係の構築が大切だ!!!
ということを、お訴えしたい、
75歳高齢者の願いです。m(__)m