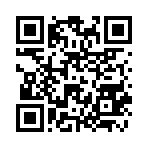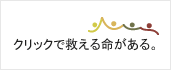今日は、3月も16日、と云うのに、
寒さが、ひとしお、厳しく迫って来る、
今日デス、
そこで、今朝のテレビ番組
健康カプセル・元気の時間のHP
を見て、お勉強しました。
そのHP、です。
https://hicbc.com/magazine/article/?id=genki-column-250316
その中には、次のように、記されています。
血液には、全身に酸素や栄養を運んだり、老廃物の回収をしたり、体温調節などの役割があります。正式な医学用語ではないそうですが、血液を全身の隅々まで流して身体機能を正常に保つ力を「血流力」と呼ぶそうです。血流力の指標となる数値は「NT-proBNP」(※一般の健康診断の項目には含まれていないため、オプションでの追加になります)。この数値が300以上で心不全のリスクが高くなるそうです。
血流力低下による様々な不調
血流力が低下すると、血液が隅々まで行き渡らず全身に酸素や栄養を届けられないばかりか疲労物質も回収できないため「疲れやすさ」や「冷え性」といった症状につながるそうです。また、心臓や肺にも酸素が十分に供給できず「動悸」や「息切れ」にもつながるのだとか。もしこの状態を放っておくと「心筋梗塞」や「脳卒中」など重大な病気のリスクも高まると言います。さらに、骨の中にも血管は通っており、血液を通じて栄養を届けることで骨を丈夫にしています。そのため、血流が滞ってしまうと十分に栄養が届かず「骨粗しょう症」につながる恐れも。脳も同じく、血流が滞ることで「認知症」のリスクが高まってしまうそうです。
血流力が下がる原因は?
<糖質と脂質でドロドロに 原因(1)「血液の質」>
血液で注意すべきは「糖質」と「脂質」。この2つが血中に多いと、質が悪くなってドロドロになるため血流の悪さに直結してしまいます。健康診断で「血糖値」「中性脂肪」「LDLコレステロール」が下記の基準値より高い場合は、ドロドロ血液になっている可能性があるそうです。
・血糖値→99mg/dL以上(空腹時)
・HbA1c→5.5%以上
・中性脂肪→150mg/dL以上(空腹時)
・LDLコレステロール→120mg/dL以上
<動脈硬化も改善!原因(2)「血管内皮細胞」>
心臓から全身に血液を運ぶときに血管は収縮を行い、適度な量の血液を全身に供給しています。その血管の収縮を行い、血流を一定に保っているのが「血管内皮細胞」。つまり、この細胞の機能が低下すると、血流力も下がってしまうのだとか。先生によると、血管は一度硬くなったりプラークができたりするとなかなか元には戻らないそうですが、血管内皮細胞機能に関しては回復させることができるとのこと。血管内皮細胞機能が回復すると、動脈硬化の予防・改善にもつながっていくそうです。
原因は生活の中にあり!血流力を下げる悪習慣
血液の質・血管内皮機能が下がる原因の多くは生活の中にあるそうです。
<血流力低下を招く生活習慣>
下記の項目に4つ以上当てはまる場合は、血流力が下がっている可能性があるそうです。
□食物繊維が足りていない
□肉・魚をあまり食べない(たんぱく質不足)
□甘い物をよく食べる(間食が多い)
□運動不足・筋力不足
□座っている時間が長い
□塩分が多い
□睡眠不足
□ストレスの多い生活
<悪習慣:食物繊維が足りない>
食物繊維を摂ると血糖値の急上昇が抑えられるそうです。血糖値が高いと血流力も下がってしまうため、血糖値が高めな人はしっかりと野菜を摂り、食物繊維で血液の質を改善していくことが大切なのだとか。野菜ジュースは食物繊維が少なく糖質が多い場合もあるため、成分表示をよく確認しましょう。野菜ジュースの代わりにスムージーを飲むのもおすすめだそうです。
<悪習慣:甘いものをよく食べる(間食が多い)>
もし間食を食べたくなった場合、先生のおすすめは「ポップコーン」。とうもろこしは、玄米などと同じ全粒穀物(種皮などを除去していない穀物)の仲間。全粒穀物には、食物繊維・ビタミンB群・抗酸化物質など、血液の循環を良くする成分が豊富だそうです。
<悪習慣:肉・魚をあまり食べない(たんぱく質不足)>
血液は、水分以外はほとんどたんぱく質でできているそうです。そのため、たんぱく質をとることで、質の良い血液を増やす効果が期待できるのだとか。血液の質を高める「食物繊維」と「たんぱく質」がしっかり含まれている食事が、血流力を上げる理想的な食生活だそうです。
<悪習慣:運動不足・筋力不足>
筋肉には血液を全身に循環させるポンプの役割があります。そのため、筋肉量が少ないと血流が悪化し、血管内皮細胞の機能も落ちてしまうそうです。さらに、筋力が少ないと基礎代謝が下がるため、冷え性にもつながってしまうのだとか。先生によると、ウォーキングなど軽めの有酸素運動は、一時的には血流が良くなりますが、筋力がつくほどの強度がないため、根本的な血流力アップは望めないそうです。
<悪習慣:ストレス>
ストレスは、自律神経の乱れやストレスホルモンの分泌を招きます。すると、血管内皮細胞の機能を低下させるのだとか。一時的なストレスでも永続的なストレスでも、心筋梗塞のリスクが2倍になるというデータもあるそうです。
簡単!血流力アップ法
CBCテレビ『健康カプセル!ゲンキの時間』
<血流力アップ法(1)朝のたんぱく質>
たんぱく質の摂取は夜が多く、朝・昼は少ない傾向にあると言います。ところが、1日のたんぱく質を同じ量摂ったときに、朝昼晩に満遍なく摂取した場合と夜に多く摂取した場合では、満遍なく摂取した方が、筋肉が落ちなかったというデータがあるのだとか。先生によると、朝に摂って欲しいたんぱく質は約30〜40g。豆腐や納豆がおすすめだそうです。
<朝にとるたんぱく質の目安(約40g)>
・卵1個(たんぱく質:約6g)
・納豆1パック(たんぱく質:約8g)
・豆腐100g(たんぱく質:約7g)
・青魚100g(たんぱく質:約21g)
<血管内皮細胞機能を改善させる食品>
血管内皮細胞機能を改善させる代表的な食品は「クルミ」。クルミ1粒あたりのたんぱく質の量は約0.5gと意外と豊富で、クルミに含まれるオメガ3脂肪酸にはコレステロール値を正常に保ち、血流をスムーズにする効果が期待できるそうです。(※クルミはアレルギーリスクのある食品です。体調に異変を感じた人は摂取しないようご注意ください)
<血流力アップ法(2)脚の筋肉>
血流力アップに重要なのが、下半身の筋肉。脚の筋肉は、足元まで巡った血液を心臓に押し上げる大切な働きを担っているのだとか。ところが、脚の筋肉は年齢とともに落ち続けるので、スクワットなどの筋トレを行うことがとても大切だそうです。
<先生おすすめ!スクワットのやり方>
▼ひじとひざがつく程度までしゃがむ
▼立ち上がる
▼5〜10回1セット 1日3セットが目標
(※無理のない範囲で行なってください)
難しい場合は、椅子に座った状態で前に置いた椅子につかまって立ち上がる「椅子立ち上がり運動」もおすすめ。まずは無理のないよう週に1日からでもはじめてみましょう。
<全身をめぐる生命線!血流力アップで不調改善>
先生によると、血流力アップに一番大切なのは悪い生活習慣の改善。また、運動をスクワットに限らず行うと血流力アップにつながるのだとか。ご紹介した2つの血流力アップ法も取り入れながら、健康長寿を目指しましょう。
(2025年3月16日(日)放送 CBCテレビ『健康カプセル!ゲンキの時間』より)
※ このブログで、
健康、について触れた号です。
クリックをお願いします。m(__)m
https://poeny.shiga-saku.net/search.php?csrf=ca433f3dd9e5d529597dbdefd04ae285b112d442&search=%E5%81%A5%E5%BA%B7
こ
寒さが、ひとしお、厳しく迫って来る、
今日デス、
そこで、今朝のテレビ番組
健康カプセル・元気の時間のHP
を見て、お勉強しました。
そのHP、です。
https://hicbc.com/magazine/article/?id=genki-column-250316
その中には、次のように、記されています。
血液には、全身に酸素や栄養を運んだり、老廃物の回収をしたり、体温調節などの役割があります。正式な医学用語ではないそうですが、血液を全身の隅々まで流して身体機能を正常に保つ力を「血流力」と呼ぶそうです。血流力の指標となる数値は「NT-proBNP」(※一般の健康診断の項目には含まれていないため、オプションでの追加になります)。この数値が300以上で心不全のリスクが高くなるそうです。
血流力低下による様々な不調
血流力が低下すると、血液が隅々まで行き渡らず全身に酸素や栄養を届けられないばかりか疲労物質も回収できないため「疲れやすさ」や「冷え性」といった症状につながるそうです。また、心臓や肺にも酸素が十分に供給できず「動悸」や「息切れ」にもつながるのだとか。もしこの状態を放っておくと「心筋梗塞」や「脳卒中」など重大な病気のリスクも高まると言います。さらに、骨の中にも血管は通っており、血液を通じて栄養を届けることで骨を丈夫にしています。そのため、血流が滞ってしまうと十分に栄養が届かず「骨粗しょう症」につながる恐れも。脳も同じく、血流が滞ることで「認知症」のリスクが高まってしまうそうです。
血流力が下がる原因は?
<糖質と脂質でドロドロに 原因(1)「血液の質」>
血液で注意すべきは「糖質」と「脂質」。この2つが血中に多いと、質が悪くなってドロドロになるため血流の悪さに直結してしまいます。健康診断で「血糖値」「中性脂肪」「LDLコレステロール」が下記の基準値より高い場合は、ドロドロ血液になっている可能性があるそうです。
・血糖値→99mg/dL以上(空腹時)
・HbA1c→5.5%以上
・中性脂肪→150mg/dL以上(空腹時)
・LDLコレステロール→120mg/dL以上
<動脈硬化も改善!原因(2)「血管内皮細胞」>
心臓から全身に血液を運ぶときに血管は収縮を行い、適度な量の血液を全身に供給しています。その血管の収縮を行い、血流を一定に保っているのが「血管内皮細胞」。つまり、この細胞の機能が低下すると、血流力も下がってしまうのだとか。先生によると、血管は一度硬くなったりプラークができたりするとなかなか元には戻らないそうですが、血管内皮細胞機能に関しては回復させることができるとのこと。血管内皮細胞機能が回復すると、動脈硬化の予防・改善にもつながっていくそうです。
原因は生活の中にあり!血流力を下げる悪習慣
血液の質・血管内皮機能が下がる原因の多くは生活の中にあるそうです。
<血流力低下を招く生活習慣>
下記の項目に4つ以上当てはまる場合は、血流力が下がっている可能性があるそうです。
□食物繊維が足りていない
□肉・魚をあまり食べない(たんぱく質不足)
□甘い物をよく食べる(間食が多い)
□運動不足・筋力不足
□座っている時間が長い
□塩分が多い
□睡眠不足
□ストレスの多い生活
<悪習慣:食物繊維が足りない>
食物繊維を摂ると血糖値の急上昇が抑えられるそうです。血糖値が高いと血流力も下がってしまうため、血糖値が高めな人はしっかりと野菜を摂り、食物繊維で血液の質を改善していくことが大切なのだとか。野菜ジュースは食物繊維が少なく糖質が多い場合もあるため、成分表示をよく確認しましょう。野菜ジュースの代わりにスムージーを飲むのもおすすめだそうです。
<悪習慣:甘いものをよく食べる(間食が多い)>
もし間食を食べたくなった場合、先生のおすすめは「ポップコーン」。とうもろこしは、玄米などと同じ全粒穀物(種皮などを除去していない穀物)の仲間。全粒穀物には、食物繊維・ビタミンB群・抗酸化物質など、血液の循環を良くする成分が豊富だそうです。
<悪習慣:肉・魚をあまり食べない(たんぱく質不足)>
血液は、水分以外はほとんどたんぱく質でできているそうです。そのため、たんぱく質をとることで、質の良い血液を増やす効果が期待できるのだとか。血液の質を高める「食物繊維」と「たんぱく質」がしっかり含まれている食事が、血流力を上げる理想的な食生活だそうです。
<悪習慣:運動不足・筋力不足>
筋肉には血液を全身に循環させるポンプの役割があります。そのため、筋肉量が少ないと血流が悪化し、血管内皮細胞の機能も落ちてしまうそうです。さらに、筋力が少ないと基礎代謝が下がるため、冷え性にもつながってしまうのだとか。先生によると、ウォーキングなど軽めの有酸素運動は、一時的には血流が良くなりますが、筋力がつくほどの強度がないため、根本的な血流力アップは望めないそうです。
<悪習慣:ストレス>
ストレスは、自律神経の乱れやストレスホルモンの分泌を招きます。すると、血管内皮細胞の機能を低下させるのだとか。一時的なストレスでも永続的なストレスでも、心筋梗塞のリスクが2倍になるというデータもあるそうです。
簡単!血流力アップ法
CBCテレビ『健康カプセル!ゲンキの時間』
<血流力アップ法(1)朝のたんぱく質>
たんぱく質の摂取は夜が多く、朝・昼は少ない傾向にあると言います。ところが、1日のたんぱく質を同じ量摂ったときに、朝昼晩に満遍なく摂取した場合と夜に多く摂取した場合では、満遍なく摂取した方が、筋肉が落ちなかったというデータがあるのだとか。先生によると、朝に摂って欲しいたんぱく質は約30〜40g。豆腐や納豆がおすすめだそうです。
<朝にとるたんぱく質の目安(約40g)>
・卵1個(たんぱく質:約6g)
・納豆1パック(たんぱく質:約8g)
・豆腐100g(たんぱく質:約7g)
・青魚100g(たんぱく質:約21g)
<血管内皮細胞機能を改善させる食品>
血管内皮細胞機能を改善させる代表的な食品は「クルミ」。クルミ1粒あたりのたんぱく質の量は約0.5gと意外と豊富で、クルミに含まれるオメガ3脂肪酸にはコレステロール値を正常に保ち、血流をスムーズにする効果が期待できるそうです。(※クルミはアレルギーリスクのある食品です。体調に異変を感じた人は摂取しないようご注意ください)
<血流力アップ法(2)脚の筋肉>
血流力アップに重要なのが、下半身の筋肉。脚の筋肉は、足元まで巡った血液を心臓に押し上げる大切な働きを担っているのだとか。ところが、脚の筋肉は年齢とともに落ち続けるので、スクワットなどの筋トレを行うことがとても大切だそうです。
<先生おすすめ!スクワットのやり方>
▼ひじとひざがつく程度までしゃがむ
▼立ち上がる
▼5〜10回1セット 1日3セットが目標
(※無理のない範囲で行なってください)
難しい場合は、椅子に座った状態で前に置いた椅子につかまって立ち上がる「椅子立ち上がり運動」もおすすめ。まずは無理のないよう週に1日からでもはじめてみましょう。
<全身をめぐる生命線!血流力アップで不調改善>
先生によると、血流力アップに一番大切なのは悪い生活習慣の改善。また、運動をスクワットに限らず行うと血流力アップにつながるのだとか。ご紹介した2つの血流力アップ法も取り入れながら、健康長寿を目指しましょう。
(2025年3月16日(日)放送 CBCテレビ『健康カプセル!ゲンキの時間』より)
※ このブログで、
健康、について触れた号です。
クリックをお願いします。m(__)m
https://poeny.shiga-saku.net/search.php?csrf=ca433f3dd9e5d529597dbdefd04ae285b112d442&search=%E5%81%A5%E5%BA%B7
こ
今日は、雨模様で、しかも寒く、
ひたすら、テレビ視聴と、
眠気の間を
行き来している私ですが、
それでも、
適度な暖房と食物に
恵まれている私です。
ですが、
世界には、
その日の食物や飲み物に困る
極貧の方々・子ども達が、居ます。
ネットに、
そうした人達への支援を
呼びかける、サイトがあります。
ユニセフのHP です。
https://www.unicef.or.jp/cooperate/coop_monthly2.html?utm_source=yahoo&utm_medium=display&utm_campaign=yda_infeed_monthly_malnutrition_retargeting&utm_term=1200_628&utm_content=monthly(AJ)_300x250_20240305&yclid=YJAD.1713680477.A12wJGYAAFH1meW7YjO1dkrKr34eNmN7cX2JubYjgTv5s9F1nqXgN8lAXochMNESIN-SrrNhWFyf_Lb1ZKX_WkdxyxBatqN0IluhHu4_aMRO9MQOoxbh2PxjLLHbL8R52UskqCv_9ic8VavJnmb2aQjkz7oxj4Ng1NJVdNnkXgxuHvQkV5wlcs-_HD4lZRegxQ&yj_r=1b
既に、ご寄付をされてる
かも知れませんが、
ユニセフさんのお役に立てればと
そのHPを、ご紹介します。m(__)m
※ このブログで、
人道支援、に触れた号です。
クリックをお願いします。m(__)m
https://poeny.shiga-saku.net/search.php?csrf=0b81e5adcfab0ab7bd248a577a08016a9a65a8d5&search=%E4%BA%BA%E9%81%93%E6%94%AF%E6%8F%B4
※ このブログで、
生存権、に触れた号です。
クリックをお願いします。。。m(_ _)m
https://poeny.shiga-saku.net/search.php?csrf=114810df5d605c3d796f109ade4652d1dfb0a2a8&search=%E7%94%9F%E5%AD%98%E6%A8%A9
ひたすら、テレビ視聴と、
眠気の間を
行き来している私ですが、
それでも、
適度な暖房と食物に
恵まれている私です。
ですが、
世界には、
その日の食物や飲み物に困る
極貧の方々・子ども達が、居ます。
ネットに、
そうした人達への支援を
呼びかける、サイトがあります。
ユニセフのHP です。
https://www.unicef.or.jp/cooperate/coop_monthly2.html?utm_source=yahoo&utm_medium=display&utm_campaign=yda_infeed_monthly_malnutrition_retargeting&utm_term=1200_628&utm_content=monthly(AJ)_300x250_20240305&yclid=YJAD.1713680477.A12wJGYAAFH1meW7YjO1dkrKr34eNmN7cX2JubYjgTv5s9F1nqXgN8lAXochMNESIN-SrrNhWFyf_Lb1ZKX_WkdxyxBatqN0IluhHu4_aMRO9MQOoxbh2PxjLLHbL8R52UskqCv_9ic8VavJnmb2aQjkz7oxj4Ng1NJVdNnkXgxuHvQkV5wlcs-_HD4lZRegxQ&yj_r=1b
既に、ご寄付をされてる
かも知れませんが、
ユニセフさんのお役に立てればと
そのHPを、ご紹介します。m(__)m
※ このブログで、
人道支援、に触れた号です。
クリックをお願いします。m(__)m
https://poeny.shiga-saku.net/search.php?csrf=0b81e5adcfab0ab7bd248a577a08016a9a65a8d5&search=%E4%BA%BA%E9%81%93%E6%94%AF%E6%8F%B4
※ このブログで、
生存権、に触れた号です。
クリックをお願いします。。。m(_ _)m
https://poeny.shiga-saku.net/search.php?csrf=114810df5d605c3d796f109ade4652d1dfb0a2a8&search=%E7%94%9F%E5%AD%98%E6%A8%A9
https://mag.nhk-book.co.jp/article/38371
運動はわたしたちをストレスから守り、脳の老化を後戻りさせる
読む その他
2023/10/01
運動 健康 認知機能 PMS ストレス 認知症 老化
X
facebook
line
ストレス、不安、うつ、ホルモンバランス、PMS、認知症などに運動が良い影響をもたらすことを明らかにしたロングセラー『脳を鍛えるには運動しかない! 最新科学でわかった脳細胞の増やし方』。運動が脳を育ててよい状態を保ち、心身の様々な悩みを解決するという研究は、これまでに数多くの読者を勇気づけてきました。当記事では、本書の15万部突破を記念して、本文の一部を公開します。
人類の脳の回路には、体の活動と学習とのつながりが組み込まれている
運動すると気分がすっきりすることはだれでも知っている。けれども、なぜそうなるのかわかっている人はほとんどいない。ストレスが解消されるから、筋肉の緊張がやわらぐから、あるいは、脳内物質のエンドルフィンが増えるから――たいていの人はそんなふうに考えている。でも本当は、運動で爽快な気分になるのは、心臓から血液がさかんに送り出され、脳がベストの状態になるからなのだ。わたしに言わせれば、運動が脳にもたらすそのような効果は、体への効果よりはるかに重要で、魅力的だ。筋力や心肺機能を高めることは、むしろ運動の副次的効果にすぎない。わたしはよく患者に、運動をするのは、脳を育ててよい状態に保つためだと話している。
科学技術に支配され、世界のどこの様子もプラズマ画面ですぐに見られる現代にあって、人間が動くように生まれついていること、つまり動物だということは忘れられがちだ。それはわたしたちが動かなくていい生活を築いてきたからだ。皮肉なことに、生物として当然の活動さえしなくてすむ社会を夢想し、計画し、実現した人間の能力は、運動をつかさどる脳の領域に根ざしている。人類は過去50万年にわたって、絶えず変化する環境に適応するために、身体能力を磨き、思考する脳を進化させてきた。ともすればわたしたちは狩猟採集生活をしていた祖先を、もっぱら体力に頼って生きていた野蛮な人間と見なしがちだが、彼らにしても長く生き延びるには、知恵をはたらかせて食物を見つけ、蓄えなければならなかった。人類の脳の回路には、食物と体の活動と学習とのつながりがもともと組み込まれているのだ。
運動はわたしたちをストレスから守り、脳の老化を後戻りさせる
しかし、わたしたちはもはや狩りも採集もしていない。そこに問題がある。動くことの少ない現代の生活は人間本来の性質を壊し、人類という種の存続を根底から脅かしている。証拠はあちこちに見られる。アメリカのおとなの65パーセントが太りすぎで、国民の10パーセントがⅡ型糖尿病を患っている。運動不足と栄養の偏りが原因の破滅的な疾病だが、生活習慣によって十分予防できるはずだ。かつては中高年の病気と言われていたこの疾病が、今では若い人たちにも広まりつつある。わたしたちは自分で自分の首を絞めているようなもので、しかもそれは生活のすべてが特大サイズのアメリカに限った話ではなく、先進国全体の問題となっている。もっと気がかりで、しかも、ほとんどだれも気づいていないのは、動かない生活は脳も殺してしまうということだ。実際に脳は縮んでいくのである。
脳を最高の状態に保つには、体を精一杯はたらかせなければならない。本書では、体の活動がわたしたちの考え方や感じ方にとって、なぜ、そしていかに大切なのかを説明していこう。運動すると、脳の学習機能を支える基本要素にどんな指示が出されるのか。運動は、気分や不安や注意力にどんな影響を及ぼすのか。どうやってわたしたちをストレスから守り、脳の老化をいくぶんでも後戻りさせるのか。そして女性に関して、ホルモンの変調がもたらす厄介な症状を運動がどのように阻止するのか。そういったことを科学的に説明していきたい。ランナーズハイのような、あいまいな概念について語るつもりはない。そもそも、ここで語るのは概念ではない。実験室のラットで計測し、人間において確認した具体的な変化なのだ。
運動をすると、脳の機能がその根元から強化される
運動をすると、セロトニンやノルアドレナリンやドーパミン――思考や感情にかかわる重要な神経伝達物質――が増えることはよく知られている。読者の皆さんも、セロトニンについては耳にされたことがあるだろうし、その不足が抑うつに関係していることもご存じかもしれないが、わたしが会ってきた多くの精神科医でさえ、それ以上のことはあまり知らないようだ。強いストレスを受けると脳の何十億というニューロンの結合が蝕まれることや、うつの状態が長引くと脳の一部が萎縮してしまうこと、しかし運動をすれば神経化学物質(神経伝達物質のほか、ニューロンの成長や機能調節などさまざまな役割を担っている化学物質の総称)や成長因子がつぎつぎに放出されてこのプロセスを逆行させ、脳の基礎構造を物理的に強くできること、そういったことをほとんどの人は知らないのだ。実際のところ脳は筋肉と同じで、使えば育つし、使わなければ萎縮してしまう。脳の神経細胞(ニューロン)は、枝先の「葉」を通じて互いに結びついている。運動をすると、これらの枝が生長し、新しい芽がたくさん出てきて、脳の機能がその根元から強化される。
神経科学者たちは、運動が脳細胞の内部――遺伝子そのもの――に及ぼす影響を研究し始めたところだ。生物の基礎である遣伝子レベルでも、体の活動が心に影響することを示す兆候が見つかっている。また、筋肉を動かすとタンパク質が作り出され、血流に乗って脳にたどり着き、高次の思考メカニズムにおいて重要な役割を果たすことがわかってきた。そうしたタンパク質群にはインスリン様成長因子(IGF-1)や血管内皮成長因子(VEGF)などがあり、その発見により、心と体の結びつきを新たな角度から見られるようになった。神経科学者がこうした因子の機能に注目し始めたのはここ数年のことだが、続々と新しい発見がなされ、驚異的な事実が明かされている。脳のミクロの環境でなにが起きているかについては、わからないことの方がはるかに多いが、すでにわかっていることだけでも人々の生活は変えられる。そして、おそらく社会も変えることができるはずだ。
運動は、認知能力と心の健康に強い影響力をもっている
わたしが願うのは、運動が脳のはたらきをどれほど向上させるかを多くの人が知り、それをモチベーションとして積極的に運動を生活に取り入れるようになることだ。もっとも、それを義務だとは思ってほしくない。運動はもちろんするべきなのだが、無理強いするつもりはない(おそらく、そんなことをしても無駄だ。ラットの実験により、強制された運動では自発的な運動ほどの効果が出ないことがわかっている)。運動をしたいと心から思えるようになれば、そのとき、あなたは違う未来へ向かう道を歩み始めている。それは生き残るための道ではなく、成長するための道なのだ。
わたしが目指すのは、運動と脳をつなぐ驚きに満ちた科学をわかりやすい言葉で語り、それが人間の生活にどのような形で現れるかを示すことだ。そして、運動が認知能力と心の健康に強い影響力をもっているという認識を確かなものにしたい。運動は、ほとんどの精神の問題にとって最高の治療法なのだ。
脳を鍛えるには運動しかない! 最新科学でわかった脳細胞の増やし方
脳を鍛えるには運動しかない! 最新科学でわかった脳細胞の増やし方
15万人の生き方を変えたロングセラー!ストレス、不安、認知症、ホルモンバランス――あなたの悩みはこれで解決!
NHK出版ECサイトへ
Amazon.co.jp
楽天ブックス
著者
ジョン J. レイティ
医学博士。ハーバード大学医学部臨床精神医学准教授。マサチューセッツ州ケンブリッジで開業医としても活躍。著書に『へんてこな贈り物』(インターメディカル)、『シャドー・シンドローム~心と脳と薬物治療』(河出書房新社)(キャサリン・ジョンソン博士との共著)、『脳のはたらきのすべてがわかる本』(角川書店)など。
おすすめ記事
ハーバード教育大学院で活躍の心理学者が「みんな同じ」に潜む危険性を解説【「集団の思い込み」を打ち砕く技術】
ハーバード教育大学院で活躍の心理学者が「みんな同じ」に潜む危険性を解説【「集団の思い込み」を打ち砕く技術】
NHKテキストからの試し読み記事やお役立ち情報をお知らせ!NHKテキスト公式LINEの友だち追加はこちら!
X
facebook
line
運動はわたしたちをストレスから守り、脳の老化を後戻りさせる
読む その他
2023/10/01
運動 健康 認知機能 PMS ストレス 認知症 老化
X
line
ストレス、不安、うつ、ホルモンバランス、PMS、認知症などに運動が良い影響をもたらすことを明らかにしたロングセラー『脳を鍛えるには運動しかない! 最新科学でわかった脳細胞の増やし方』。運動が脳を育ててよい状態を保ち、心身の様々な悩みを解決するという研究は、これまでに数多くの読者を勇気づけてきました。当記事では、本書の15万部突破を記念して、本文の一部を公開します。
人類の脳の回路には、体の活動と学習とのつながりが組み込まれている
運動すると気分がすっきりすることはだれでも知っている。けれども、なぜそうなるのかわかっている人はほとんどいない。ストレスが解消されるから、筋肉の緊張がやわらぐから、あるいは、脳内物質のエンドルフィンが増えるから――たいていの人はそんなふうに考えている。でも本当は、運動で爽快な気分になるのは、心臓から血液がさかんに送り出され、脳がベストの状態になるからなのだ。わたしに言わせれば、運動が脳にもたらすそのような効果は、体への効果よりはるかに重要で、魅力的だ。筋力や心肺機能を高めることは、むしろ運動の副次的効果にすぎない。わたしはよく患者に、運動をするのは、脳を育ててよい状態に保つためだと話している。
科学技術に支配され、世界のどこの様子もプラズマ画面ですぐに見られる現代にあって、人間が動くように生まれついていること、つまり動物だということは忘れられがちだ。それはわたしたちが動かなくていい生活を築いてきたからだ。皮肉なことに、生物として当然の活動さえしなくてすむ社会を夢想し、計画し、実現した人間の能力は、運動をつかさどる脳の領域に根ざしている。人類は過去50万年にわたって、絶えず変化する環境に適応するために、身体能力を磨き、思考する脳を進化させてきた。ともすればわたしたちは狩猟採集生活をしていた祖先を、もっぱら体力に頼って生きていた野蛮な人間と見なしがちだが、彼らにしても長く生き延びるには、知恵をはたらかせて食物を見つけ、蓄えなければならなかった。人類の脳の回路には、食物と体の活動と学習とのつながりがもともと組み込まれているのだ。
運動はわたしたちをストレスから守り、脳の老化を後戻りさせる
しかし、わたしたちはもはや狩りも採集もしていない。そこに問題がある。動くことの少ない現代の生活は人間本来の性質を壊し、人類という種の存続を根底から脅かしている。証拠はあちこちに見られる。アメリカのおとなの65パーセントが太りすぎで、国民の10パーセントがⅡ型糖尿病を患っている。運動不足と栄養の偏りが原因の破滅的な疾病だが、生活習慣によって十分予防できるはずだ。かつては中高年の病気と言われていたこの疾病が、今では若い人たちにも広まりつつある。わたしたちは自分で自分の首を絞めているようなもので、しかもそれは生活のすべてが特大サイズのアメリカに限った話ではなく、先進国全体の問題となっている。もっと気がかりで、しかも、ほとんどだれも気づいていないのは、動かない生活は脳も殺してしまうということだ。実際に脳は縮んでいくのである。
脳を最高の状態に保つには、体を精一杯はたらかせなければならない。本書では、体の活動がわたしたちの考え方や感じ方にとって、なぜ、そしていかに大切なのかを説明していこう。運動すると、脳の学習機能を支える基本要素にどんな指示が出されるのか。運動は、気分や不安や注意力にどんな影響を及ぼすのか。どうやってわたしたちをストレスから守り、脳の老化をいくぶんでも後戻りさせるのか。そして女性に関して、ホルモンの変調がもたらす厄介な症状を運動がどのように阻止するのか。そういったことを科学的に説明していきたい。ランナーズハイのような、あいまいな概念について語るつもりはない。そもそも、ここで語るのは概念ではない。実験室のラットで計測し、人間において確認した具体的な変化なのだ。
運動をすると、脳の機能がその根元から強化される
運動をすると、セロトニンやノルアドレナリンやドーパミン――思考や感情にかかわる重要な神経伝達物質――が増えることはよく知られている。読者の皆さんも、セロトニンについては耳にされたことがあるだろうし、その不足が抑うつに関係していることもご存じかもしれないが、わたしが会ってきた多くの精神科医でさえ、それ以上のことはあまり知らないようだ。強いストレスを受けると脳の何十億というニューロンの結合が蝕まれることや、うつの状態が長引くと脳の一部が萎縮してしまうこと、しかし運動をすれば神経化学物質(神経伝達物質のほか、ニューロンの成長や機能調節などさまざまな役割を担っている化学物質の総称)や成長因子がつぎつぎに放出されてこのプロセスを逆行させ、脳の基礎構造を物理的に強くできること、そういったことをほとんどの人は知らないのだ。実際のところ脳は筋肉と同じで、使えば育つし、使わなければ萎縮してしまう。脳の神経細胞(ニューロン)は、枝先の「葉」を通じて互いに結びついている。運動をすると、これらの枝が生長し、新しい芽がたくさん出てきて、脳の機能がその根元から強化される。
神経科学者たちは、運動が脳細胞の内部――遺伝子そのもの――に及ぼす影響を研究し始めたところだ。生物の基礎である遣伝子レベルでも、体の活動が心に影響することを示す兆候が見つかっている。また、筋肉を動かすとタンパク質が作り出され、血流に乗って脳にたどり着き、高次の思考メカニズムにおいて重要な役割を果たすことがわかってきた。そうしたタンパク質群にはインスリン様成長因子(IGF-1)や血管内皮成長因子(VEGF)などがあり、その発見により、心と体の結びつきを新たな角度から見られるようになった。神経科学者がこうした因子の機能に注目し始めたのはここ数年のことだが、続々と新しい発見がなされ、驚異的な事実が明かされている。脳のミクロの環境でなにが起きているかについては、わからないことの方がはるかに多いが、すでにわかっていることだけでも人々の生活は変えられる。そして、おそらく社会も変えることができるはずだ。
運動は、認知能力と心の健康に強い影響力をもっている
わたしが願うのは、運動が脳のはたらきをどれほど向上させるかを多くの人が知り、それをモチベーションとして積極的に運動を生活に取り入れるようになることだ。もっとも、それを義務だとは思ってほしくない。運動はもちろんするべきなのだが、無理強いするつもりはない(おそらく、そんなことをしても無駄だ。ラットの実験により、強制された運動では自発的な運動ほどの効果が出ないことがわかっている)。運動をしたいと心から思えるようになれば、そのとき、あなたは違う未来へ向かう道を歩み始めている。それは生き残るための道ではなく、成長するための道なのだ。
わたしが目指すのは、運動と脳をつなぐ驚きに満ちた科学をわかりやすい言葉で語り、それが人間の生活にどのような形で現れるかを示すことだ。そして、運動が認知能力と心の健康に強い影響力をもっているという認識を確かなものにしたい。運動は、ほとんどの精神の問題にとって最高の治療法なのだ。
脳を鍛えるには運動しかない! 最新科学でわかった脳細胞の増やし方
脳を鍛えるには運動しかない! 最新科学でわかった脳細胞の増やし方
15万人の生き方を変えたロングセラー!ストレス、不安、認知症、ホルモンバランス――あなたの悩みはこれで解決!
NHK出版ECサイトへ
Amazon.co.jp
楽天ブックス
著者
ジョン J. レイティ
医学博士。ハーバード大学医学部臨床精神医学准教授。マサチューセッツ州ケンブリッジで開業医としても活躍。著書に『へんてこな贈り物』(インターメディカル)、『シャドー・シンドローム~心と脳と薬物治療』(河出書房新社)(キャサリン・ジョンソン博士との共著)、『脳のはたらきのすべてがわかる本』(角川書店)など。
おすすめ記事
ハーバード教育大学院で活躍の心理学者が「みんな同じ」に潜む危険性を解説【「集団の思い込み」を打ち砕く技術】
ハーバード教育大学院で活躍の心理学者が「みんな同じ」に潜む危険性を解説【「集団の思い込み」を打ち砕く技術】
NHKテキストからの試し読み記事やお役立ち情報をお知らせ!NHKテキスト公式LINEの友だち追加はこちら!
X
line
Posted by 夢想花 at
21:04
│Comments(0)
今朝のテレビ番組
健康カプセル!ゲンキの時間、を視聴して
納得・感激しました 。
。
CBCマガジンの
健康カプセル!ゲンキの時間 の記述です。
https://hicbc.com/magazine/article/?id=genki-column-230212
MCは、石丸幹二さんと坂下千里子さん、
助言ドクターは、
東海大学名誉教授 医学博士石井直明さんです。
老境に入って、
体が悲鳴を上げている昨今、
私にも凄く勉強に成るお話を伺えました。
石井直明先生は
★ 健康な毎日を送るために欠かせないのが栄養素。
厚生労働省が推奨している1日に必要な栄養素は約30種類。
しかし、栄養素は
「これだけ摂っておけばいい」というものではなく、
1つでも不足すると低いレベルに合わせて
健康度が下がってしまうのだとか。
そこで今回は、
病気に負けない身体作りのために
「栄養素の役割」を、述べたい。
との事です。
★ 疲労・メタボの救世主?!「ビタミンB群」
ビタミンB群は、
ビタミンB1・B2・B6・B12・ナイアシン・パントテン酸・葉酸・ピオチン、
と、8種類有るそうです。
★ <疲労回復!ビタミンB群の役割>
ビタミンB群の役割の主な効果は、疲労の回復。
ビタミンB群は、
細胞内で、
糖質・タンパク質・脂質を効率よく燃焼させ、
エネルギーを作り出しているそうです。
その為、
ビタミンB群が不足すると、
エネルギーの製造が滞りがちに成り、身体機能が低下。
疲労に始まり、
めまいや食欲不振といった
健康被害に繋がってしまうそうです。
★ <ビタミンB群を含む食材>
うなぎ・ブロッコリー・鶏肉・アボガド・バナナ・納豆など、
※ 取り過ぎは控え、適切な量を摂取しましょう。
★ <脱メタボの救世主! ビタミンB1>
ビタミンB1は、
主に、糖を材料にして、
エネルギーを、作り出しているそうです。
その為、不足すると、
糖が溜まって、
脂肪に変化してしまい、メタボの原因に成ることもあるとか?!
ビタミンB1は、
他のビタミンB群よ比べると、
不足しがちに成るので、
意識して、摂取する事が大切です。
★ <ビタミンB1を含む食材>
豚肉・玄米・大豆・かつお節・アーモンドなど、
米 取り過ぎは控え、適切な量を摂取しましょう。
★ ニンニクに含まれるアリシンには、
ビタミンB1の摂取を促す働きがあるそうです。
その為、
豚の生姜焼きなどに入れると、
よりメタボの予防効果が、期待できるそうです。
★ 打ち消す力で、老化を防止?! ビタミンC
<しみ・しわ等、肌の悩みに有効! ビタミンCの働き>
コラーゲンと関係の有る、
健康カプセル!ゲンキの時間
今回のテーマは「〜あなたも不足しているかも!?〜イチから学ぶ“栄養素”の役割」
健康な毎日を送るために欠かせないのが栄養素。厚生労働省が推奨している1日に必要な栄養素は約30種類。しかし、栄養素は「これだけ摂っておけばいい」というものではなく、1つでも不足すると低いレベルに合わせて健康度が下がってしまうのだとか。そこで今回は、病気に負けない身体作りのために「栄養素の役割」を専門医に教えてもらいました。
疲労・メタボの救世主!?「ビタミンB群」
CBCテレビ『健康カプセル!ゲンキの時間』
ビタミンB群は、ビタミンB1・ビタミンB2・ビタミンB6・ビタミンB12・ナイアシン・パントテン酸・葉酸・ビオチンと8種類あるそうです。
<疲労回復!ビタミンB群の役割>
先生曰く、ビタミンB群の主な効果は疲労の回復。ビタミンB群は、細胞内で糖質・たんぱく質・脂質を効率良く燃焼させエネルギーを作り出しているそうです。そのため、ビタミンB群が不足すると、エネルギーの製造が滞りがちになり身体機能が低下。疲労に始まり、めまいや食欲不振といった健康被害にもつながってしまうそうです。
<ビタミンB群を含む食材>
うなぎ・ブロッコリー・鶏肉・アボカド・バナナ・納豆など
※摂り過ぎは控え適切な量を摂取しましょう
<脱メタボの救世主!ビタミンB1>
ビタミンB1は、主に糖を材料にしてエネルギーを作り出しているそうです。そのため、不足すると、糖が溜まって脂肪に変化してしまいメタボの原因になる事もあるのだとか。ビタミンB1は、他のビタミンB群と比べると不足しがちなので、意識して摂摂取する事が大切だそうです。
<ビタミンB1を含む食材>
豚肉・玄米・大豆・かつお節・アーモンドなど
※摂り過ぎは控え適切な量を摂取しましょう
<ビタミンB1を賢く摂取する方法>
先生によると、ニンニクに含まれるアリシンには、ビタミンB1の吸収を促進してくれる働きがあるのだとか。そのため、豚の生姜焼きなどに入れるとよりメタボの予防効果が期待できるそうです。
打ち消す力で老化を防止!?「ビタミンC」
CBCテレビ『健康カプセル!ゲンキの時間』
<しみ・しわなど肌の悩みに有効!ビタミンCの働き」>
肌に良いイメージのあるビタミンCですが、その理由はコラーゲンと関係があるのだとか。コラーゲンは皮膚や血管、じん帯などの素となるたんぱく質。細胞と細胞の間を繋げる接着剤の様な働きをしています。このコラーゲンを作るのに欠かせないのがビタミンC。不足すると、皮膚の張りがなくなりしみ・しわなどの肌トラブルにつながるだけでなく、コラーゲンが効率良く作られず血管から出血しやすくなってしまうそうです。
<老化を防止する抗酸化作用も!>
体内にできる活性酸素は、本来その強い酸化力で、ウイルスなどを撃退するという大切な働きを担っています。しかし、これが大量発生するとDNAやたんぱく質を傷つけ、細胞の機能低下を招く事に。すると、身体の老化が早まってしまい、動脈硬化や認知症など大病につながるリスクも高まってしまうのだとか。そんな活性酸素から身体を守ってくれるのが、ビタミンCの抗酸化作用。活性酸素を打ち消す働きをしてくれるそうです。
<ストレスでビタミンCが次々消費!?>
先生によると、ビタミンCは日常のちょっとした行動で次々と消費されてしまうそうです。なかでも大敵はストレス。ストレスを感じると、一時的に血流が悪くなり、この流れが元に戻る際に活性酸素が発生。それを除去しようとビタミンCがどんどん消費されていくのだとか。実際、満員電車に乗った学生を調べたところ、乗車してから30分後には血中ビタミンCが90%に減少。1時間後には66%まで減っていたというデータも。他にも、パソコンやスマホなど目を酷使する事でも活性酸素が発生し、ビタミンCが消費されるので注意が必要だそうです。
<ビタミンCを含む食材>
ピーマン、ブロッコリー、ジャガイモ、芽キャベツ、レモンなど
※摂り過ぎは控え適切な量を摂取しましょう
<ビタミンCを賢く摂取する方法>
厚生労働省が推奨する1日に必要なビタミンCの摂取量は100mg。ただし、ビタミンCは水溶性なので、一度に大量に摂ると余分なものは尿と一緒に排泄されてしまうのだとか。そのため、一度に摂取するのではなく、3回に分けて食事に取り入れるなどできる範囲でこまめに摂取すると良いそうです。
<抗酸化作用をアップさせる方法>
先生によると、ビタミンAやビタミンEにも抗酸化作用があるのだとか。そのためビタミンACEを一緒に摂るとより効果が期待できるそうです。
世界が注目!「ビタミンD」
近年世界レベルでビタミンDが注目されており、新たな働きが次々と解明されているそうです。
<カルシウムの運び屋 !ビタミンD>
ビタミンDはカルシウムを骨へと運び、吸収を促進する働きがあり「カルシウムの運び屋」と呼ばれているのだとか。そのため、骨が強くなり骨粗しょう症や骨折のリスクの軽減にもつながるそうです。
<他にもある!ビタミンDの健康パワー>
先生によると、ビタミンDには体内にウイルスが侵入した際に免疫細胞を活性化する働きがあるとの事。他にも糖尿病・筋力低下・認知症の予防など数々の健康効果があると言われているそうです。
<ビタミンDを含む食材>
魚類・きのこ類
鮭はビタミンDが豊富な上、手軽に購入できるので特にオススメだそうです。
※摂り過ぎは控え適切な量を摂取しましょう
<ミネラルも大切!>
カルシウムや亜鉛などの必須ミネラルは、
身体を構成し生命活動を維持するために必要な栄養素。
ただし、これらは身体で作る事が不可能なので
食物から摂る必要があるそうです。
<亜鉛の健康パワー>
先生によると、亜鉛はたんぱく質やDNAの合成をサポートし、免疫力を上げる働きがあるとの事。ただし、過剰摂取すると鉄・銅の吸収を抑えてしまうため適量を摂る事が大切だそうです。
栄養素を正しく理解し健康な身体づくりを
先生によると、必須栄養素のどれか1つが不足するとそれに合わせて健康度が下がってしまうそうです。ただし、摂り過ぎも禁物。そのため、より健康な身体を作るためには栄養素の働きを正しく理解する事が大切なのだとか。また、リコピンやポリフェノールなどの機能性成分は、それだけを摂るのではなく、必須栄養素をしっかり摂った上で摂取する事が大事との事です。
実は、今まで、iPadへの記述を基に、
今朝の番組の内容を
纏めていたのですが、
iPadを睨み続けている内に、
iPadの電力が、枯渇してしまいまいた。
健康オタクの、夢想人の私、
番組の内容を、勉強したく
皆さまのお役に立ちたく、
医学的知識の弱い私、
勉強の為、細々、記しました。
今後とも、この番組を視聴し、
応援しますので
今号の発信をお許し下さい。m(__)m
※ このブログで、
健康情報、について触れた号です。
クリックをお願いします。m(__)m
https://poeny.shiga-saku.net/search.php?csrf=ba9b1773d5533263c6e454487a1d1ca273018c9c&search=%E5%81%A5%E5%BA%B7%E6%83%85%E5%A0%B1
健康カプセル!ゲンキの時間、を視聴して
納得・感激しました
 。
。CBCマガジンの
健康カプセル!ゲンキの時間 の記述です。
https://hicbc.com/magazine/article/?id=genki-column-230212
MCは、石丸幹二さんと坂下千里子さん、
助言ドクターは、
東海大学名誉教授 医学博士石井直明さんです。
老境に入って、
体が悲鳴を上げている昨今、
私にも凄く勉強に成るお話を伺えました。
石井直明先生は
★ 健康な毎日を送るために欠かせないのが栄養素。
厚生労働省が推奨している1日に必要な栄養素は約30種類。
しかし、栄養素は
「これだけ摂っておけばいい」というものではなく、
1つでも不足すると低いレベルに合わせて
健康度が下がってしまうのだとか。
そこで今回は、
病気に負けない身体作りのために
「栄養素の役割」を、述べたい。
との事です。
★ 疲労・メタボの救世主?!「ビタミンB群」
ビタミンB群は、
ビタミンB1・B2・B6・B12・ナイアシン・パントテン酸・葉酸・ピオチン、
と、8種類有るそうです。
★ <疲労回復!ビタミンB群の役割>
ビタミンB群の役割の主な効果は、疲労の回復。
ビタミンB群は、
細胞内で、
糖質・タンパク質・脂質を効率よく燃焼させ、
エネルギーを作り出しているそうです。
その為、
ビタミンB群が不足すると、
エネルギーの製造が滞りがちに成り、身体機能が低下。
疲労に始まり、
めまいや食欲不振といった
健康被害に繋がってしまうそうです。
★ <ビタミンB群を含む食材>
うなぎ・ブロッコリー・鶏肉・アボガド・バナナ・納豆など、
※ 取り過ぎは控え、適切な量を摂取しましょう。
★ <脱メタボの救世主! ビタミンB1>
ビタミンB1は、
主に、糖を材料にして、
エネルギーを、作り出しているそうです。
その為、不足すると、
糖が溜まって、
脂肪に変化してしまい、メタボの原因に成ることもあるとか?!
ビタミンB1は、
他のビタミンB群よ比べると、
不足しがちに成るので、
意識して、摂取する事が大切です。
★ <ビタミンB1を含む食材>
豚肉・玄米・大豆・かつお節・アーモンドなど、
米 取り過ぎは控え、適切な量を摂取しましょう。
★ ニンニクに含まれるアリシンには、
ビタミンB1の摂取を促す働きがあるそうです。
その為、
豚の生姜焼きなどに入れると、
よりメタボの予防効果が、期待できるそうです。
★ 打ち消す力で、老化を防止?! ビタミンC
<しみ・しわ等、肌の悩みに有効! ビタミンCの働き>
コラーゲンと関係の有る、
健康カプセル!ゲンキの時間
今回のテーマは「〜あなたも不足しているかも!?〜イチから学ぶ“栄養素”の役割」
健康な毎日を送るために欠かせないのが栄養素。厚生労働省が推奨している1日に必要な栄養素は約30種類。しかし、栄養素は「これだけ摂っておけばいい」というものではなく、1つでも不足すると低いレベルに合わせて健康度が下がってしまうのだとか。そこで今回は、病気に負けない身体作りのために「栄養素の役割」を専門医に教えてもらいました。
疲労・メタボの救世主!?「ビタミンB群」
CBCテレビ『健康カプセル!ゲンキの時間』
ビタミンB群は、ビタミンB1・ビタミンB2・ビタミンB6・ビタミンB12・ナイアシン・パントテン酸・葉酸・ビオチンと8種類あるそうです。
<疲労回復!ビタミンB群の役割>
先生曰く、ビタミンB群の主な効果は疲労の回復。ビタミンB群は、細胞内で糖質・たんぱく質・脂質を効率良く燃焼させエネルギーを作り出しているそうです。そのため、ビタミンB群が不足すると、エネルギーの製造が滞りがちになり身体機能が低下。疲労に始まり、めまいや食欲不振といった健康被害にもつながってしまうそうです。
<ビタミンB群を含む食材>
うなぎ・ブロッコリー・鶏肉・アボカド・バナナ・納豆など
※摂り過ぎは控え適切な量を摂取しましょう
<脱メタボの救世主!ビタミンB1>
ビタミンB1は、主に糖を材料にしてエネルギーを作り出しているそうです。そのため、不足すると、糖が溜まって脂肪に変化してしまいメタボの原因になる事もあるのだとか。ビタミンB1は、他のビタミンB群と比べると不足しがちなので、意識して摂摂取する事が大切だそうです。
<ビタミンB1を含む食材>
豚肉・玄米・大豆・かつお節・アーモンドなど
※摂り過ぎは控え適切な量を摂取しましょう
<ビタミンB1を賢く摂取する方法>
先生によると、ニンニクに含まれるアリシンには、ビタミンB1の吸収を促進してくれる働きがあるのだとか。そのため、豚の生姜焼きなどに入れるとよりメタボの予防効果が期待できるそうです。
打ち消す力で老化を防止!?「ビタミンC」
CBCテレビ『健康カプセル!ゲンキの時間』
<しみ・しわなど肌の悩みに有効!ビタミンCの働き」>
肌に良いイメージのあるビタミンCですが、その理由はコラーゲンと関係があるのだとか。コラーゲンは皮膚や血管、じん帯などの素となるたんぱく質。細胞と細胞の間を繋げる接着剤の様な働きをしています。このコラーゲンを作るのに欠かせないのがビタミンC。不足すると、皮膚の張りがなくなりしみ・しわなどの肌トラブルにつながるだけでなく、コラーゲンが効率良く作られず血管から出血しやすくなってしまうそうです。
<老化を防止する抗酸化作用も!>
体内にできる活性酸素は、本来その強い酸化力で、ウイルスなどを撃退するという大切な働きを担っています。しかし、これが大量発生するとDNAやたんぱく質を傷つけ、細胞の機能低下を招く事に。すると、身体の老化が早まってしまい、動脈硬化や認知症など大病につながるリスクも高まってしまうのだとか。そんな活性酸素から身体を守ってくれるのが、ビタミンCの抗酸化作用。活性酸素を打ち消す働きをしてくれるそうです。
<ストレスでビタミンCが次々消費!?>
先生によると、ビタミンCは日常のちょっとした行動で次々と消費されてしまうそうです。なかでも大敵はストレス。ストレスを感じると、一時的に血流が悪くなり、この流れが元に戻る際に活性酸素が発生。それを除去しようとビタミンCがどんどん消費されていくのだとか。実際、満員電車に乗った学生を調べたところ、乗車してから30分後には血中ビタミンCが90%に減少。1時間後には66%まで減っていたというデータも。他にも、パソコンやスマホなど目を酷使する事でも活性酸素が発生し、ビタミンCが消費されるので注意が必要だそうです。
<ビタミンCを含む食材>
ピーマン、ブロッコリー、ジャガイモ、芽キャベツ、レモンなど
※摂り過ぎは控え適切な量を摂取しましょう
<ビタミンCを賢く摂取する方法>
厚生労働省が推奨する1日に必要なビタミンCの摂取量は100mg。ただし、ビタミンCは水溶性なので、一度に大量に摂ると余分なものは尿と一緒に排泄されてしまうのだとか。そのため、一度に摂取するのではなく、3回に分けて食事に取り入れるなどできる範囲でこまめに摂取すると良いそうです。
<抗酸化作用をアップさせる方法>
先生によると、ビタミンAやビタミンEにも抗酸化作用があるのだとか。そのためビタミンACEを一緒に摂るとより効果が期待できるそうです。
世界が注目!「ビタミンD」
近年世界レベルでビタミンDが注目されており、新たな働きが次々と解明されているそうです。
<カルシウムの運び屋 !ビタミンD>
ビタミンDはカルシウムを骨へと運び、吸収を促進する働きがあり「カルシウムの運び屋」と呼ばれているのだとか。そのため、骨が強くなり骨粗しょう症や骨折のリスクの軽減にもつながるそうです。
<他にもある!ビタミンDの健康パワー>
先生によると、ビタミンDには体内にウイルスが侵入した際に免疫細胞を活性化する働きがあるとの事。他にも糖尿病・筋力低下・認知症の予防など数々の健康効果があると言われているそうです。
<ビタミンDを含む食材>
魚類・きのこ類
鮭はビタミンDが豊富な上、手軽に購入できるので特にオススメだそうです。
※摂り過ぎは控え適切な量を摂取しましょう
<ミネラルも大切!>
カルシウムや亜鉛などの必須ミネラルは、
身体を構成し生命活動を維持するために必要な栄養素。
ただし、これらは身体で作る事が不可能なので
食物から摂る必要があるそうです。
<亜鉛の健康パワー>
先生によると、亜鉛はたんぱく質やDNAの合成をサポートし、免疫力を上げる働きがあるとの事。ただし、過剰摂取すると鉄・銅の吸収を抑えてしまうため適量を摂る事が大切だそうです。
栄養素を正しく理解し健康な身体づくりを
先生によると、必須栄養素のどれか1つが不足するとそれに合わせて健康度が下がってしまうそうです。ただし、摂り過ぎも禁物。そのため、より健康な身体を作るためには栄養素の働きを正しく理解する事が大切なのだとか。また、リコピンやポリフェノールなどの機能性成分は、それだけを摂るのではなく、必須栄養素をしっかり摂った上で摂取する事が大事との事です。
実は、今まで、iPadへの記述を基に、
今朝の番組の内容を
纏めていたのですが、
iPadを睨み続けている内に、
iPadの電力が、枯渇してしまいまいた。
健康オタクの、夢想人の私、
番組の内容を、勉強したく
皆さまのお役に立ちたく、
医学的知識の弱い私、
勉強の為、細々、記しました。
今後とも、この番組を視聴し、
応援しますので
今号の発信をお許し下さい。m(__)m
※ このブログで、
健康情報、について触れた号です。
クリックをお願いします。m(__)m
https://poeny.shiga-saku.net/search.php?csrf=ba9b1773d5533263c6e454487a1d1ca273018c9c&search=%E5%81%A5%E5%BA%B7%E6%83%85%E5%A0%B1
今日は、何故か、
足の裏が、ポカポカ暖かいので、
健康情報を、検索じました。
すると、
次のような、記事に出会いました。
まず、
讀賣新聞オンラインニュース です。
https://news.yahoo.co.jp/articles/834f87c0788cb3beb8863d978fb38b6bb7d9652e
次に、
国立ガン研究センターのHP です。
https://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/2022/0908/index.html
国立研究開発法人国立がん研究センターと
横浜市立大学で構成される
研究グループは、
研究開始から5年後に行った食事調査票に回答し、
がん、循環器疾患、肝疾患になっていなかった
約9万5千人を、
平成30年(2018年)まで追跡した調査結果に基づいて
野菜と果物の摂取量と死亡リスクとの関連を調べた結果
果物・野菜摂取量が少ないグループに比べ、
果物摂取量が多いグループでは
全死亡リスクが約8-9%、
心臓血管死亡リスクが約9%低く、
野菜摂取量が多いグループでは
全死亡リスクが約7-8%低い事が
分かったという事です。
本研究の研究成果は
国際学術誌「Journal of Nutrition」に
発表されたと、言う事です。
私、79歳は、日々、筋肉の衰え、
脳の忘れっぽさ、と闘っていますが、
これも、ワイフの食事作りと
皆さまのご訪問に、励まされて、
この理屈っぽいブログ、発信で
乏しい脳を活用する、私、
感謝しきり、有難うございます。m(__)m
※ このブログで、
食物、への思いについて触れた号です。
クリックをお願いします。m(__)m
https://poeny.shiga-saku.net/search.php?csrf=d09edf534019a9a073489c3572d7e73d478bdc93&search=%E9%A3%9F%E7%89%A9
足の裏が、ポカポカ暖かいので、
健康情報を、検索じました。
すると、
次のような、記事に出会いました。
まず、
讀賣新聞オンラインニュース です。
https://news.yahoo.co.jp/articles/834f87c0788cb3beb8863d978fb38b6bb7d9652e
次に、
国立ガン研究センターのHP です。
https://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/2022/0908/index.html
国立研究開発法人国立がん研究センターと
横浜市立大学で構成される
研究グループは、
研究開始から5年後に行った食事調査票に回答し、
がん、循環器疾患、肝疾患になっていなかった
約9万5千人を、
平成30年(2018年)まで追跡した調査結果に基づいて
野菜と果物の摂取量と死亡リスクとの関連を調べた結果
果物・野菜摂取量が少ないグループに比べ、
果物摂取量が多いグループでは
全死亡リスクが約8-9%、
心臓血管死亡リスクが約9%低く、
野菜摂取量が多いグループでは
全死亡リスクが約7-8%低い事が
分かったという事です。
本研究の研究成果は
国際学術誌「Journal of Nutrition」に
発表されたと、言う事です。
私、79歳は、日々、筋肉の衰え、
脳の忘れっぽさ、と闘っていますが、
これも、ワイフの食事作りと
皆さまのご訪問に、励まされて、
この理屈っぽいブログ、発信で
乏しい脳を活用する、私、
感謝しきり、有難うございます。m(__)m
※ このブログで、
食物、への思いについて触れた号です。
クリックをお願いします。m(__)m
https://poeny.shiga-saku.net/search.php?csrf=d09edf534019a9a073489c3572d7e73d478bdc93&search=%E9%A3%9F%E7%89%A9