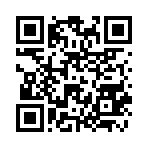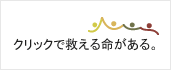突然、しんみりした話しをすると、私は現在64歳、人生で残された時間はいかほどかということを、折に触れ考える年頃になった。今、日本は世界でも有数の経済大国である。街には、モノがあふれ、行き交う人の服装もまばゆい。絶えず音が流れ、情報が家の中に飛び込んで、人工の光芒が夜空を刺している。空腹で苦しむ人も、滅多に見かけない。社会の様相の変貌はすさまじく、人間を置き去りにして、激変している。取り残された人間は、生き方に迷い苦しみ、まわりに助言してくれる人もいず、孤独の淵で苦しんでいる。私が子ども時代、まわりに一杯のお節介おばさんやおじさんがいた。誰かの噂話に花を咲かせて、放送局みたいにうるさい大人や、と迷惑に思ったこともあったけど、結構、お節介おばさんやおじさんが、子どもたちに注意をし、手を差し伸べてくれた。まわりの人が、お互いに、関心を持っていた。
私は、このようなことについて、どれほどのことができるか分からない。ただ、残された時間の一部でも、そういうことを語るお節介じいさんでいたいな、とも考えている。
私は1943(昭和18)年に京都市で生まれた。以後戦後日本の変貌を、子どもとして青年として壮年として高齢者として見てきた。すべてを網羅することはできない。しかし、戦後の日本の世相の変貌のようなものの一部でも、若い人たちや子どもたちにも知ってもらいたい。私は、貧しい日本と、豊かな日本の両方を見てきた。
過去を知って、現在や未来の生き方の参考にする・・・そんな思いを抱いて、このブログで、一つのテーマとして取り上げてみようと思う。いろいろ取り混ぜながら、肩の凝らないように気を使いながら、それでも戦後の日本社会の姿の変貌を、書いていきたいと思うに至った。
話しは変わるが、映画「オールウエイズ 3丁目の夕日」がヒットした。昭和30年代の日本が描かれている。今の日本で失われつつあるものへの郷愁・・・多くの人が求めてる・・・そう信じて、、基本的には私が経験したことをベースに、不定期且つ個人的好みも交えて書いていきたい。
<敗戦そして昭和20年代幼き日>
私は、1943(昭和18)年に京都市で生まれた。戦時中については、ほとんど記憶がないはずであるが、不思議なことに、ある夜、母親に抱かれていて、暗い空に飛行機の閃光が筋を引いていて、まわりの人が「B29や」と声を上げていたことを覚えている。いつ見たのか分からないが、米軍の戦闘機の「B29」という名と、暗い夜空の光りの筋を覚えている。
終戦の1945(昭和20)年には2歳、日本国憲法が施行された47年には4歳であった。
子ども時代は、腹ぺこ空腹が当たり前の毎日であった。家で飼っていたウサギが、肉として食卓に上り、それを味気なく食べた時のことを覚えている。靴は、配給制で、育ち盛りの子どもの発育に追いつかず、私の母親は、靴の先をハサミで切って、そこから私は足の指を出して歩いていた。私は、現在、足のサイズが24.5センチメートルであるが、足の小ささを思うとき、中国で昔、女性の足を小さくするために使われた「纏足」を連想する。また今も、身長の低さを思うとき、もののないひもじかった幼少の頃を思い出す。
小学校に入ったのが、1950(昭和25)年。あとから勉強してわかったのであるが、朝鮮戦争の始まった年である。私も含めて近所の子どもたちは、馬蹄形の磁石にヒモをつけて地面を這わせ、地面に散乱する釘や鉄片を拾って、ザル一杯で5円か10円で業者に買ってもらっていた。これもあとから聞いたところによると、朝鮮戦争の軍需物資に使われたとか・・・。
幼い頃は、アメリカの影が街に溢れていて、ラジオから、連日、マッカーサ元帥のことが流れていた。私は、単語として「マッカーサ元帥」という言葉を聞いていた。彼が日本を離れるとき、ラジオから、マッカーサ元帥万歳、といったような声がワーワーっと流れていた。その騒がしさを私が聞くと、父親は「マッカーサは、日本によいことをしてくれた」と言っていた。当時、彼の人気は凄かったんだろう。それに対して、ソ連については、父親は「日ソ不可侵条約を破って卑怯や」と言って決して褒めようとしなかった。アメリカの対日政策の巧妙さ(これも後から知ったのであるが)は、子どもの私にも、アメリカへの親近感や憧れを抱かせるには十分だった。進駐軍のジープに乗った米兵が、子どもたちを集めて、チョコレートやキャンディをばらまき、私たち子どもはそれに群がり、回らぬ舌で「ギブミー・チョコレート」と叫んで、菓子を拾った。夜には、広い空き地に昼間張られた白い幕にアメリカのワーナーやパラマウントの映画が上映された。それを見た子どもの私は、何とアメリカは金持ちなんだろう、行きたい、住みたい国と、憧れをいっぱい募らせていった。なお、私の幼い頃の記憶では、「進駐軍」という言い方しかなく、「占領軍」という言い方は記憶にない。
当時のことを詳しく言うのは、それを通して、当時の子どもたちの状況を知ってもらいたいためである。簡潔に言えば、終戦直後から1952(昭和27年の本土の独立ごろまでの子どもたちは、ひもじいけれど活動的ということではなかったのだろうか。この辺は、漫画「ハダシのゲン」を読んでくだされば、一層、理解してもらえよう。
ものごころつくかつかない幼い頃に、私は、母親が『河岸の柳の行きずりーに』と歌っていたのを聞いて育った。やがて、空腹を癒すためにか、四角い雑音混じりの木箱のラジオにしがみついて聞くようになった。、水泳の古橋・橋爪の活躍を聞いて幼心なりに胸を躍らせたり、笠置シヅ子や天才子ども歌手と言われていた美空ひばりの歌や広沢虎造の浪曲を聞いて真似た。虎造の「妻は夫に従いつ、夫は妻を慕いつつ・・・」だったかの浪曲をよくうなった。また、ラジオ放送で、親も身寄りも失った戦災孤児の話、確か『鐘の鳴る丘』だったと思うが、を聞いていた。昭和27年、ボクシングの白井義男が世界チャンピオンになり、その活躍は映画館でのニュース映画で見た。映画館といえば、当時、日本映画3本立て80円ぐらいで、親にせがんでお金をもらい、子どもだけで、朝一番で映画館に入って映画三本を見て、午後の3時か4時に表に出たときは目がくらくらした。昭和29年、自衛隊が発足した年だが、このころそんなことは知らず、映画が大好きで中村錦之助(後の萬屋錦之介)主演の「笛吹童子」「紅孔雀」などに熱中した。 (つづく)
私は、このようなことについて、どれほどのことができるか分からない。ただ、残された時間の一部でも、そういうことを語るお節介じいさんでいたいな、とも考えている。
私は1943(昭和18)年に京都市で生まれた。以後戦後日本の変貌を、子どもとして青年として壮年として高齢者として見てきた。すべてを網羅することはできない。しかし、戦後の日本の世相の変貌のようなものの一部でも、若い人たちや子どもたちにも知ってもらいたい。私は、貧しい日本と、豊かな日本の両方を見てきた。
過去を知って、現在や未来の生き方の参考にする・・・そんな思いを抱いて、このブログで、一つのテーマとして取り上げてみようと思う。いろいろ取り混ぜながら、肩の凝らないように気を使いながら、それでも戦後の日本社会の姿の変貌を、書いていきたいと思うに至った。
話しは変わるが、映画「オールウエイズ 3丁目の夕日」がヒットした。昭和30年代の日本が描かれている。今の日本で失われつつあるものへの郷愁・・・多くの人が求めてる・・・そう信じて、、基本的には私が経験したことをベースに、不定期且つ個人的好みも交えて書いていきたい。
<敗戦そして昭和20年代幼き日>
私は、1943(昭和18)年に京都市で生まれた。戦時中については、ほとんど記憶がないはずであるが、不思議なことに、ある夜、母親に抱かれていて、暗い空に飛行機の閃光が筋を引いていて、まわりの人が「B29や」と声を上げていたことを覚えている。いつ見たのか分からないが、米軍の戦闘機の「B29」という名と、暗い夜空の光りの筋を覚えている。
終戦の1945(昭和20)年には2歳、日本国憲法が施行された47年には4歳であった。
子ども時代は、腹ぺこ空腹が当たり前の毎日であった。家で飼っていたウサギが、肉として食卓に上り、それを味気なく食べた時のことを覚えている。靴は、配給制で、育ち盛りの子どもの発育に追いつかず、私の母親は、靴の先をハサミで切って、そこから私は足の指を出して歩いていた。私は、現在、足のサイズが24.5センチメートルであるが、足の小ささを思うとき、中国で昔、女性の足を小さくするために使われた「纏足」を連想する。また今も、身長の低さを思うとき、もののないひもじかった幼少の頃を思い出す。
小学校に入ったのが、1950(昭和25)年。あとから勉強してわかったのであるが、朝鮮戦争の始まった年である。私も含めて近所の子どもたちは、馬蹄形の磁石にヒモをつけて地面を這わせ、地面に散乱する釘や鉄片を拾って、ザル一杯で5円か10円で業者に買ってもらっていた。これもあとから聞いたところによると、朝鮮戦争の軍需物資に使われたとか・・・。
幼い頃は、アメリカの影が街に溢れていて、ラジオから、連日、マッカーサ元帥のことが流れていた。私は、単語として「マッカーサ元帥」という言葉を聞いていた。彼が日本を離れるとき、ラジオから、マッカーサ元帥万歳、といったような声がワーワーっと流れていた。その騒がしさを私が聞くと、父親は「マッカーサは、日本によいことをしてくれた」と言っていた。当時、彼の人気は凄かったんだろう。それに対して、ソ連については、父親は「日ソ不可侵条約を破って卑怯や」と言って決して褒めようとしなかった。アメリカの対日政策の巧妙さ(これも後から知ったのであるが)は、子どもの私にも、アメリカへの親近感や憧れを抱かせるには十分だった。進駐軍のジープに乗った米兵が、子どもたちを集めて、チョコレートやキャンディをばらまき、私たち子どもはそれに群がり、回らぬ舌で「ギブミー・チョコレート」と叫んで、菓子を拾った。夜には、広い空き地に昼間張られた白い幕にアメリカのワーナーやパラマウントの映画が上映された。それを見た子どもの私は、何とアメリカは金持ちなんだろう、行きたい、住みたい国と、憧れをいっぱい募らせていった。なお、私の幼い頃の記憶では、「進駐軍」という言い方しかなく、「占領軍」という言い方は記憶にない。
当時のことを詳しく言うのは、それを通して、当時の子どもたちの状況を知ってもらいたいためである。簡潔に言えば、終戦直後から1952(昭和27年の本土の独立ごろまでの子どもたちは、ひもじいけれど活動的ということではなかったのだろうか。この辺は、漫画「ハダシのゲン」を読んでくだされば、一層、理解してもらえよう。
ものごころつくかつかない幼い頃に、私は、母親が『河岸の柳の行きずりーに』と歌っていたのを聞いて育った。やがて、空腹を癒すためにか、四角い雑音混じりの木箱のラジオにしがみついて聞くようになった。、水泳の古橋・橋爪の活躍を聞いて幼心なりに胸を躍らせたり、笠置シヅ子や天才子ども歌手と言われていた美空ひばりの歌や広沢虎造の浪曲を聞いて真似た。虎造の「妻は夫に従いつ、夫は妻を慕いつつ・・・」だったかの浪曲をよくうなった。また、ラジオ放送で、親も身寄りも失った戦災孤児の話、確か『鐘の鳴る丘』だったと思うが、を聞いていた。昭和27年、ボクシングの白井義男が世界チャンピオンになり、その活躍は映画館でのニュース映画で見た。映画館といえば、当時、日本映画3本立て80円ぐらいで、親にせがんでお金をもらい、子どもだけで、朝一番で映画館に入って映画三本を見て、午後の3時か4時に表に出たときは目がくらくらした。昭和29年、自衛隊が発足した年だが、このころそんなことは知らず、映画が大好きで中村錦之助(後の萬屋錦之介)主演の「笛吹童子」「紅孔雀」などに熱中した。 (つづく)