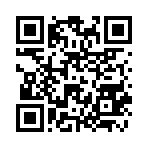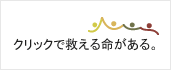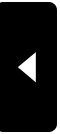大相撲千秋楽テレビ中継で、解説の舞の海さんが、千秋楽の観客の盛り上がりを見て、印象的なコメント・・・「昨日、琴欧洲の初優勝が決まったのに、千秋楽のきょうも大変な盛り上がり。ファンが、いかに、“変化”を求めているか、ですねぇ。」と。
伝統と変化・CHANGE
不易流行
私も、同感。琴欧洲関の喜びを素直に謙虚に表す態度、お父さんの喜び、ブルガリア語での母国の人への思いはち切れんばかりのメッセージ・・・初初しくて、見てる私も心が揺すられる。朝青龍のふてぶてしく見える態度にも、やや食傷気味。白鵬も、圧倒的な強さがない。日本人力士の台頭もイマイチ。相撲協会は、暗いイメージ。それを、吹っ飛ばすような、来場所も強いかどうか ? だけれど、ここは琴欧洲の笑顔に、酔ってみたい。
“変化”“CHANGE”・・・閉塞感ある中で、人は“変化”“CHANGE”を求めている。政治の世界でも同じことなのかも・・・。キムタク首相を求める人の気持ちもよく分かる。
と思いつつ、イヤ、ここは待てよ、と考え、ひとこと言いたくなるのが、私の特性(取り柄?)。ちょっと、話が飛躍しすぎですが、連想した言葉が 「不易流行」 。この言葉、【広辞苑】には、・・・(芭蕉の俳諧用語)不易は詩の基本である永遠性。流行はその時々の新風の体。・・・とある。抽象的で分かりにくいけれど、転じて私は、、“伝統”と“変化”の相互の関連性とか、伝統と変化相互の啓発・刺激の大切さを言っているように、理解しています。
何もかも、新しいことがイイのではなく、悪いのでなく、古いことがイイのでなく、悪いのではなく、それぞれが学び、吸収して、さらに発展していく、と理解している。だから、年寄りも若者も、それぞれを、敬遠することなく、お互いに、学びあったら・・・と、祈念する次第です。
大相撲の基本・伝統は大事。そこに、どう新風を吹き込んで、新しい“命”を宿らせるか。これは、どこの世界でも、同じ。・・・だと、舞の海さん話を聞きつつ、飛躍させつつ思いました。
例えば、歌舞伎でも、落語でも、何でも、伝統ができるまでは、いろいろ新しいコトを試行錯誤して、伝統様式らしきものを創ります。その上に、安住していては、伝統も干涸らびる。安住と、無反省は、最大の敵で、それを「ゴ-マン」「怠惰」「封建的」「閉鎖的」と言うのかも、知れマセン。 さまざま、思い巡らせた、夕方から夜でした。
※ 「不易流行」について、さらに、とお思いの方は、このアドレスを見てください。
http://www.yadonet.ne.jp/junior/1314/keieisya/keieisya2/inakumatopix-2.htm
※ 若い頃やっていた剣道では、よく似た意味(ちょっと違うかな?)の言葉として、 「守・破・離」 というのがあります。これについても、近々に、頼まれもシテイマセンガ、お節介ウンチクしたいと思っています。ご迷惑をおかけシマスが、おつきあいのほどを・・・。
※ 琴欧洲は、以前、琴欧州の四股名で、大関になってから伸び悩んで、験担ぎで四股名を「琴欧洲」と変えたようです。24日のブログは、四股名の表記を間違えていましたので、琴欧洲と、訂正させて頂きました。すみません。
伝統と変化・CHANGE
不易流行
私も、同感。琴欧洲関の喜びを素直に謙虚に表す態度、お父さんの喜び、ブルガリア語での母国の人への思いはち切れんばかりのメッセージ・・・初初しくて、見てる私も心が揺すられる。朝青龍のふてぶてしく見える態度にも、やや食傷気味。白鵬も、圧倒的な強さがない。日本人力士の台頭もイマイチ。相撲協会は、暗いイメージ。それを、吹っ飛ばすような、来場所も強いかどうか ? だけれど、ここは琴欧洲の笑顔に、酔ってみたい。
“変化”“CHANGE”・・・閉塞感ある中で、人は“変化”“CHANGE”を求めている。政治の世界でも同じことなのかも・・・。キムタク首相を求める人の気持ちもよく分かる。
と思いつつ、イヤ、ここは待てよ、と考え、ひとこと言いたくなるのが、私の特性(取り柄?)。ちょっと、話が飛躍しすぎですが、連想した言葉が 「不易流行」 。この言葉、【広辞苑】には、・・・(芭蕉の俳諧用語)不易は詩の基本である永遠性。流行はその時々の新風の体。・・・とある。抽象的で分かりにくいけれど、転じて私は、、“伝統”と“変化”の相互の関連性とか、伝統と変化相互の啓発・刺激の大切さを言っているように、理解しています。
何もかも、新しいことがイイのではなく、悪いのでなく、古いことがイイのでなく、悪いのではなく、それぞれが学び、吸収して、さらに発展していく、と理解している。だから、年寄りも若者も、それぞれを、敬遠することなく、お互いに、学びあったら・・・と、祈念する次第です。
大相撲の基本・伝統は大事。そこに、どう新風を吹き込んで、新しい“命”を宿らせるか。これは、どこの世界でも、同じ。・・・だと、舞の海さん話を聞きつつ、飛躍させつつ思いました。
例えば、歌舞伎でも、落語でも、何でも、伝統ができるまでは、いろいろ新しいコトを試行錯誤して、伝統様式らしきものを創ります。その上に、安住していては、伝統も干涸らびる。安住と、無反省は、最大の敵で、それを「ゴ-マン」「怠惰」「封建的」「閉鎖的」と言うのかも、知れマセン。 さまざま、思い巡らせた、夕方から夜でした。
※ 「不易流行」について、さらに、とお思いの方は、このアドレスを見てください。
http://www.yadonet.ne.jp/junior/1314/keieisya/keieisya2/inakumatopix-2.htm
※ 若い頃やっていた剣道では、よく似た意味(ちょっと違うかな?)の言葉として、 「守・破・離」 というのがあります。これについても、近々に、頼まれもシテイマセンガ、お節介ウンチクしたいと思っています。ご迷惑をおかけシマスが、おつきあいのほどを・・・。
※ 琴欧洲は、以前、琴欧州の四股名で、大関になってから伸び悩んで、験担ぎで四股名を「琴欧洲」と変えたようです。24日のブログは、四股名の表記を間違えていましたので、琴欧洲と、訂正させて頂きました。すみません。
琴欧洲が、大相撲で優勝しました。ブルガリアから、単身、来日。長い、ながい苦労の末に、勝ち得た優勝。お父さんが、応援に来ていました。
琴欧洲、初優勝!
優勝決定後の親子の抱擁。「親孝行」・・・今、日本では、語られづらくなった“親孝行”の3文字を、欧州から来た青年が、私たちの眼前に、運んできてくれました。彼は、元レスリング選手。欧州ジュニア王者にまで なったが、家族を支えるために19歳で来日したそうな・・・。彼は、インタビュウアーの質問に答えて「やっと掴んだ」と答えます。 “苦労”“辛抱”・・・日本では、使われることの少なくなった言葉をも、彷彿させる彼。国際化の進む大相撲。だけど、一方で、日本人が忘れつつあるものを、逆に、多くの外国人力士が体現しているようです。 だけど、やっぱり、大相撲は、ドラマやねぇ。口惜しさも、悲しみも、喜びも、凝縮して見せてくれるドラマですねぇ、おめでとう、琴欧洲関!!!
【蛇足? 補足? 郷愁?】 私の小学生から中学生の頃は、横綱千代の山、鏡里、吉葉山、栃若時代。誰が早かったか、後だったか、私の記憶が曖昧で、その順番は定かではないですが、とりわけ栃若の技の応酬に興奮し、地面に石ころや釘で土俵の円を描いて、その上で、連れの悪ガキと相撲取るのが、日課でした。当時の楽しみは、相撲とセカンド・ベースなしの三角ベースの野球。グローブは、素手や紙で作ったもの。それでボールを受ました。相撲に話を戻しますと、栃錦が、なぜか好きで、その加減で、彼が所属していた春日野部屋が好きで、だから後に大関になった栃光の押し相撲も、小兵横綱栃ノ海の業師ぶりも好きでした。私の得意技は、押しと、どういう訳か出し投げ。だけど、よく負けた。友だちの中には、鎖骨を折ってもなお、相撲をしていた人もありました。それに大相撲をやめてプロレスに転向した力道山に、興奮しまくりました。以後、柏鵬時代、玉の海、千代の富士、最近では若貴時代。歌は世に連れ、世は歌に連れ。と同じく、お相撲さんも、世の光陰を、強く、彩っていました。昔は、「故郷に錦を飾る」というのが、他郷へ志を持って働きに出る青年の大きなモティべーションだったのですが、それも、朝青龍や白鳳、琴欧洲関などによって体現されているようです。「気は優しくて力持ち」・・・漂流している日本の“男の子”像の復活が、少しは、アッテモイイのじゃないでしょうか、と、ノスタルジーする私でした。
※ なお、この文は、あくまで、相撲の一ファンとして、私の情緒的な記憶というか印象を基に書いた文でありますので、時間の前後が不確かで、また触れていない力士も多くいます、という前提で、お読みくださいますよう・・・。文中の力士から、少年から大人になってからも、私が夢をもらってきたように、本来、大相撲は、夢を与えるものであって欲しい。
ここで、“勇み足”気味の詩(もどき)を・・・。
土 俵
人生の 光陰織りなす 大相撲
負けるも 勝つも 繰り返してきた挑戦の末
土俵に浸みる 汗 涙 そして 夢
琴欧洲、初優勝!
優勝決定後の親子の抱擁。「親孝行」・・・今、日本では、語られづらくなった“親孝行”の3文字を、欧州から来た青年が、私たちの眼前に、運んできてくれました。彼は、元レスリング選手。欧州ジュニア王者にまで なったが、家族を支えるために19歳で来日したそうな・・・。彼は、インタビュウアーの質問に答えて「やっと掴んだ」と答えます。 “苦労”“辛抱”・・・日本では、使われることの少なくなった言葉をも、彷彿させる彼。国際化の進む大相撲。だけど、一方で、日本人が忘れつつあるものを、逆に、多くの外国人力士が体現しているようです。 だけど、やっぱり、大相撲は、ドラマやねぇ。口惜しさも、悲しみも、喜びも、凝縮して見せてくれるドラマですねぇ、おめでとう、琴欧洲関!!!
【蛇足? 補足? 郷愁?】 私の小学生から中学生の頃は、横綱千代の山、鏡里、吉葉山、栃若時代。誰が早かったか、後だったか、私の記憶が曖昧で、その順番は定かではないですが、とりわけ栃若の技の応酬に興奮し、地面に石ころや釘で土俵の円を描いて、その上で、連れの悪ガキと相撲取るのが、日課でした。当時の楽しみは、相撲とセカンド・ベースなしの三角ベースの野球。グローブは、素手や紙で作ったもの。それでボールを受ました。相撲に話を戻しますと、栃錦が、なぜか好きで、その加減で、彼が所属していた春日野部屋が好きで、だから後に大関になった栃光の押し相撲も、小兵横綱栃ノ海の業師ぶりも好きでした。私の得意技は、押しと、どういう訳か出し投げ。だけど、よく負けた。友だちの中には、鎖骨を折ってもなお、相撲をしていた人もありました。それに大相撲をやめてプロレスに転向した力道山に、興奮しまくりました。以後、柏鵬時代、玉の海、千代の富士、最近では若貴時代。歌は世に連れ、世は歌に連れ。と同じく、お相撲さんも、世の光陰を、強く、彩っていました。昔は、「故郷に錦を飾る」というのが、他郷へ志を持って働きに出る青年の大きなモティべーションだったのですが、それも、朝青龍や白鳳、琴欧洲関などによって体現されているようです。「気は優しくて力持ち」・・・漂流している日本の“男の子”像の復活が、少しは、アッテモイイのじゃないでしょうか、と、ノスタルジーする私でした。
※ なお、この文は、あくまで、相撲の一ファンとして、私の情緒的な記憶というか印象を基に書いた文でありますので、時間の前後が不確かで、また触れていない力士も多くいます、という前提で、お読みくださいますよう・・・。文中の力士から、少年から大人になってからも、私が夢をもらってきたように、本来、大相撲は、夢を与えるものであって欲しい。
ここで、“勇み足”気味の詩(もどき)を・・・。
土 俵
人生の 光陰織りなす 大相撲
負けるも 勝つも 繰り返してきた挑戦の末
土俵に浸みる 汗 涙 そして 夢
久し振りの我が家の犬情報です。
我が家歴17年
犬虚空を掴もうと・・・
3日ほど前の深夜、私がパソコンをいじって、また寝ようかな、と思って、パソコンを閉め、電気を消して、2階の部屋に向かうべく、階段を上がりつつある時、階下で、何か物音がしました。何かな、と思って降りると、静かに寝ていたはずの我が家の犬が、床に横になったまま、手足をバタバタさせているのです。因みに、我が家歴17年の犬は、本来は家の外に居があるのですが、ここ半年ぐらいは、老衰で極度に弱ったため、家の入り口入ったところで、寝起きさせています。夜はオムツをして、半介護状態です。
で、我が家の犬は、手足を、まるで虚空を切ったように、空転(? 「バタバタ」の表現が難しい)させ、見ると少し、モドしているようです。目も定かでない。「どない、したんや?」・・・私の声も上ずって、犬に声をかけるのですが、いつもなら、振ってくれるシッポも振らずに、反応も、ない。これは、ヤバイ。こう判断した私は、妻を、急遽、起こしました。
二人で、犬を見守り、いよいよ最後のときかな、動物病院へ行くにも深夜だし、救急車もないし、犬に声をかけ、頭をなで、私は、今までのサマザマなことを反省して、「ゴメンな」と謝りました。1時間半ほど、吐瀉物で濡れた床を拭いたり、犬を抱かえて家の外に出しておシッコさせようとしたり・・・外へ出たとき、その夜は満月で、月光を写す犬の“黒い瞳”は本当に美しかった・・・、口に水を含ませようとしたり、どうやら人間の手で頭を起こしたら少し楽みたい、・・・そうこうしていたでしょうか。妻が、「お父さんは、あした仕事やし、寝」と言いますので、「何かありそうになったら、起こしてヤ」と頼んで、2階の部屋に行きました。
朝5時半頃に起きて、1階に降りて、犬の様子を見ますと、ピクリともせずに横たわっています。よくよく見ると、すこし腹が動いている。呼吸は、している!!!。
そうして、朝を迎えました。妻と私の見立てでは、どうやら、妻が犬が欲しがるので、ドッグフードを寝る前に少しやったのが、胃で耐えきれなかったのかな、それと、日中の暑さのため、少し、熱中症状態になったのかな、という結論になりました。
あれ以後、相変わらずヨロヨロ歩くし、食欲はあるし、すっかり吠えない「歌を忘れた犬」状態ではありますけれど、あの深夜劇は何だったのだろうと思う状態で、ここ2日ほど過ごしています。ですが、ほとんど屋内犬・半介護状態は、続いています。犬の生命力に感動、私たちも、犬を通して、生と死の境界線らしきものを垣間見させて頂きました。お騒がせの一節、おつきあい、有り難うございました。 ここで、下手な自己満足一句と一首。
空切れど 初夏の夜長の 犬の意地
月光を 瞳(め)に宿らせて 老いし犬
ただひたむきに 生きて見つめて
我が家歴17年
犬虚空を掴もうと・・・
3日ほど前の深夜、私がパソコンをいじって、また寝ようかな、と思って、パソコンを閉め、電気を消して、2階の部屋に向かうべく、階段を上がりつつある時、階下で、何か物音がしました。何かな、と思って降りると、静かに寝ていたはずの我が家の犬が、床に横になったまま、手足をバタバタさせているのです。因みに、我が家歴17年の犬は、本来は家の外に居があるのですが、ここ半年ぐらいは、老衰で極度に弱ったため、家の入り口入ったところで、寝起きさせています。夜はオムツをして、半介護状態です。
で、我が家の犬は、手足を、まるで虚空を切ったように、空転(? 「バタバタ」の表現が難しい)させ、見ると少し、モドしているようです。目も定かでない。「どない、したんや?」・・・私の声も上ずって、犬に声をかけるのですが、いつもなら、振ってくれるシッポも振らずに、反応も、ない。これは、ヤバイ。こう判断した私は、妻を、急遽、起こしました。
二人で、犬を見守り、いよいよ最後のときかな、動物病院へ行くにも深夜だし、救急車もないし、犬に声をかけ、頭をなで、私は、今までのサマザマなことを反省して、「ゴメンな」と謝りました。1時間半ほど、吐瀉物で濡れた床を拭いたり、犬を抱かえて家の外に出しておシッコさせようとしたり・・・外へ出たとき、その夜は満月で、月光を写す犬の“黒い瞳”は本当に美しかった・・・、口に水を含ませようとしたり、どうやら人間の手で頭を起こしたら少し楽みたい、・・・そうこうしていたでしょうか。妻が、「お父さんは、あした仕事やし、寝」と言いますので、「何かありそうになったら、起こしてヤ」と頼んで、2階の部屋に行きました。
朝5時半頃に起きて、1階に降りて、犬の様子を見ますと、ピクリともせずに横たわっています。よくよく見ると、すこし腹が動いている。呼吸は、している!!!。
そうして、朝を迎えました。妻と私の見立てでは、どうやら、妻が犬が欲しがるので、ドッグフードを寝る前に少しやったのが、胃で耐えきれなかったのかな、それと、日中の暑さのため、少し、熱中症状態になったのかな、という結論になりました。
あれ以後、相変わらずヨロヨロ歩くし、食欲はあるし、すっかり吠えない「歌を忘れた犬」状態ではありますけれど、あの深夜劇は何だったのだろうと思う状態で、ここ2日ほど過ごしています。ですが、ほとんど屋内犬・半介護状態は、続いています。犬の生命力に感動、私たちも、犬を通して、生と死の境界線らしきものを垣間見させて頂きました。お騒がせの一節、おつきあい、有り難うございました。 ここで、下手な自己満足一句と一首。
空切れど 初夏の夜長の 犬の意地
月光を 瞳(め)に宿らせて 老いし犬
ただひたむきに 生きて見つめて
昨日に続いて、お送りします。暫時、ご辛抱を・・・。
異質・異端は、貴重な教科書
官も民も、組織として動いている。現実には、組織の多くが、自分たちにとって“異質”とか“異端”とか“都合の悪い外部”の意見を排除する傾向がつよい。だけど、“異質”“異端”“外部の意見”から学び、内側に入れてこそ、組織としての膨らみ・柔軟性・可能性が広がっていくのではないだろうか? 指摘に対して、議論して、共通の理解に到達した方が、組織にとっても、意見を言う人にとっても、納得できる未来が開けてくる。
「生活者」「市民・主権者」として共通の課題を持つ者が、共に社会を構成する組織が、話し合い、議論する・・・これこそ、民主主義であり、話し合い、議論することによって、国民(住民)も、行政組織(公務員組織)も、自分のものの見方の狭さに気づき、より合理的で、より多くの人が納得できる普遍的な考え方に到達できる。
敵対ではなく話し合いを、敵視ではなく議論を・・・話し合いによる相互理解の道筋を経ない決めつけは、“偏見”になる。 橋元知事の発言は、一面では、心地よい。だけど、なにか釈然としないものも残る。ミイラ取りがミイラになったらアカンけど、民主主義を、とことん、追求して欲しい。古人いはく「もの言わぬは、腹ふくるる技なれば・・・」。確か、「徒然草」の吉田兼好だったでしょうか・・・。町の100人委員会に期待するところ、極めて大なるゆえんです。
【舞台裏】 いつもテンション高いねぇ、と言われますが、そうではござんせん。今年は、プロ野球のロッテが負け続けだし、人様に、ちょっとシカトされると、高齢の孤独・悲哀をことさら感じて寂しい。
寂しいが故に、少し、気にかけて頂くと、すごく嬉しい。ブログへのご訪問者の数が増えて、嬉しい・テンションUP、という次第でございます。
異質・異端は、貴重な教科書
官も民も、組織として動いている。現実には、組織の多くが、自分たちにとって“異質”とか“異端”とか“都合の悪い外部”の意見を排除する傾向がつよい。だけど、“異質”“異端”“外部の意見”から学び、内側に入れてこそ、組織としての膨らみ・柔軟性・可能性が広がっていくのではないだろうか? 指摘に対して、議論して、共通の理解に到達した方が、組織にとっても、意見を言う人にとっても、納得できる未来が開けてくる。
「生活者」「市民・主権者」として共通の課題を持つ者が、共に社会を構成する組織が、話し合い、議論する・・・これこそ、民主主義であり、話し合い、議論することによって、国民(住民)も、行政組織(公務員組織)も、自分のものの見方の狭さに気づき、より合理的で、より多くの人が納得できる普遍的な考え方に到達できる。
敵対ではなく話し合いを、敵視ではなく議論を・・・話し合いによる相互理解の道筋を経ない決めつけは、“偏見”になる。 橋元知事の発言は、一面では、心地よい。だけど、なにか釈然としないものも残る。ミイラ取りがミイラになったらアカンけど、民主主義を、とことん、追求して欲しい。古人いはく「もの言わぬは、腹ふくるる技なれば・・・」。確か、「徒然草」の吉田兼好だったでしょうか・・・。町の100人委員会に期待するところ、極めて大なるゆえんです。
【舞台裏】 いつもテンション高いねぇ、と言われますが、そうではござんせん。今年は、プロ野球のロッテが負け続けだし、人様に、ちょっとシカトされると、高齢の孤独・悲哀をことさら感じて寂しい。
寂しいが故に、少し、気にかけて頂くと、すごく嬉しい。ブログへのご訪問者の数が増えて、嬉しい・テンションUP、という次第でございます。
このブログの5月18日号では、公務員に厳しいことを言いましたが、一方では・・・。。。。。
エラそうに言うな、とお叱りを受けそうですが、少しでも社会の前進につながれば、という思いで、さらに生意気を申し上げます。本人は、極めてマジメに書いておりますので、単なる「世迷いごと」より、もう少し上のランクにお位置づけくださいますよう・・・
徹底、話し合いのススメ
5月18日号では、公務員に厳しいことを言ったが、一方では公務員も、一生活人であり、一市民であり、一労働者であり一主権者であり、その組織も私企業と同じ、生身の人間の集合体である、という側面を持っている。その意味では、民間企業とか、そこで働く人と変わらない。ただ、大雑把に言えば、民間企業は儲かる・損するというバロメータがあって、世間の経済景気動向に大きく左右され、大もうけ・倒産という浮き沈みがあり、組織も働く人々も、世間の風・影響をモロに受けるという面があるのに対し、官庁は、「親方日の丸」という言葉で揶揄されるような安定感・温室育ちの観がある。最近は、自治体の財政危機でそれも危ういものになってはきているが、それでも民間企業の人から見れば、ダルいものに感じられるようだ。その分、公務員組織には、厳しい眼差しが注がれることになって、私も、現役当時、住民全体からの注目を意識する場面もあって、その不自由さに愚痴をこぼしたこともあった。
今、働いて生計を立て、家庭生活・社会生活を営んでいる「生活人」とその集合体である組織について、官・民の立場の違いによって、やや科学的視点を欠いた感情的な見方が言いやすい・大向こう(世間)に受けやすい風潮が、かなりあるのではないだろうか?
巧妙な政治家は、その辺を煽り立て、ひたすら攻めて非難して、一方は、ひたすら謝って、そして結果的に萎縮してしまっている“図式”があるように、見えて仕方がない。なぜ、組織として、「反論」なり「弁明」をブッチャケ堂々と展開しないのか? それが「説明責任」というものでは、ないだろうか? 例えば、悲しいことだが、虐待で子どもが同居の保護者たるべき大人によって虐待されている可能性や証拠などを、折角、医者や学校や近所の者が児童相談所に通報したのに、児童相談所が適切な手を打ったのか打たなかったのか分からないが、結果的に、子どもが死に追いやられたとき、テレビ画面に出てくる児相の所長は、ひたすら謝っているシーが多い。児相の権限、人手、実情等、国民にもっとその時に訴えていけば、国民の虐待防止への理解も進むのではないか? もちろん別の場では、例えば、広報活動や議会等でその辺もされていると思うけれど、謝るシーンばかりでは、児相に不信感を持ってしまう。例え、記者から詰問されようと、言うべきことは言い、議論すべきは議論する姿勢が、次なる虐待防止の施策の質の向上に繋がり、それが再発防止につながってくるのではないだろうか?
学校と親の関係も、言うべきは言い、聞くべきは聞き、共通の理解に到達することによって、結果的には、子どもの権利条約に言うところの、子どもにとっての「最善の利益」の実現につながっていくのではないか?
役所と住民の関係も、お互いに言うべきは言い、聞くべきは聞くことによって、共に成長できるのでは、ないでしょうか?
(長くなりますので、明日につづけます)
エラそうに言うな、とお叱りを受けそうですが、少しでも社会の前進につながれば、という思いで、さらに生意気を申し上げます。本人は、極めてマジメに書いておりますので、単なる「世迷いごと」より、もう少し上のランクにお位置づけくださいますよう・・・
徹底、話し合いのススメ
5月18日号では、公務員に厳しいことを言ったが、一方では公務員も、一生活人であり、一市民であり、一労働者であり一主権者であり、その組織も私企業と同じ、生身の人間の集合体である、という側面を持っている。その意味では、民間企業とか、そこで働く人と変わらない。ただ、大雑把に言えば、民間企業は儲かる・損するというバロメータがあって、世間の経済景気動向に大きく左右され、大もうけ・倒産という浮き沈みがあり、組織も働く人々も、世間の風・影響をモロに受けるという面があるのに対し、官庁は、「親方日の丸」という言葉で揶揄されるような安定感・温室育ちの観がある。最近は、自治体の財政危機でそれも危ういものになってはきているが、それでも民間企業の人から見れば、ダルいものに感じられるようだ。その分、公務員組織には、厳しい眼差しが注がれることになって、私も、現役当時、住民全体からの注目を意識する場面もあって、その不自由さに愚痴をこぼしたこともあった。
今、働いて生計を立て、家庭生活・社会生活を営んでいる「生活人」とその集合体である組織について、官・民の立場の違いによって、やや科学的視点を欠いた感情的な見方が言いやすい・大向こう(世間)に受けやすい風潮が、かなりあるのではないだろうか?
巧妙な政治家は、その辺を煽り立て、ひたすら攻めて非難して、一方は、ひたすら謝って、そして結果的に萎縮してしまっている“図式”があるように、見えて仕方がない。なぜ、組織として、「反論」なり「弁明」をブッチャケ堂々と展開しないのか? それが「説明責任」というものでは、ないだろうか? 例えば、悲しいことだが、虐待で子どもが同居の保護者たるべき大人によって虐待されている可能性や証拠などを、折角、医者や学校や近所の者が児童相談所に通報したのに、児童相談所が適切な手を打ったのか打たなかったのか分からないが、結果的に、子どもが死に追いやられたとき、テレビ画面に出てくる児相の所長は、ひたすら謝っているシーが多い。児相の権限、人手、実情等、国民にもっとその時に訴えていけば、国民の虐待防止への理解も進むのではないか? もちろん別の場では、例えば、広報活動や議会等でその辺もされていると思うけれど、謝るシーンばかりでは、児相に不信感を持ってしまう。例え、記者から詰問されようと、言うべきことは言い、議論すべきは議論する姿勢が、次なる虐待防止の施策の質の向上に繋がり、それが再発防止につながってくるのではないだろうか?
学校と親の関係も、言うべきは言い、聞くべきは聞き、共通の理解に到達することによって、結果的には、子どもの権利条約に言うところの、子どもにとっての「最善の利益」の実現につながっていくのではないか?
役所と住民の関係も、お互いに言うべきは言い、聞くべきは聞くことによって、共に成長できるのでは、ないでしょうか?
(長くなりますので、明日につづけます)