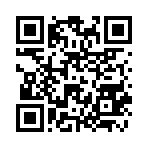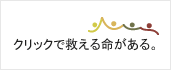ほんの30分ほど前に投稿した記事の続きを、今、お送りするのは、いささjか気が引けますが、aH 研究のプラス面も強調したくて、UPします。
aH その2
 一方、プラス的な、笑いの量の計測化の効用を考えると、番組の中でもあったが、笑いの量の大小が商業的価値につながる可能性、さらに医療的には、免疫力向上との関連性を科学的に追求できるだろう。
一方、プラス的な、笑いの量の計測化の効用を考えると、番組の中でもあったが、笑いの量の大小が商業的価値につながる可能性、さらに医療的には、免疫力向上との関連性を科学的に追求できるだろう。
また、笑いの「普遍化」というか、誰でも笑える 「価値ある笑い」も数値化できる効用もあるだろう。しばしばこのブログでも触れているように、今のお笑い芸やテレビ等での笑いの中には、高齢や容貌をネタにして、誰もが笑えない笑い(?)が笑いと勘違いされ振りまかれていることが、しばしばある。
「価値ある笑い」も数値化できる効用もあるだろう。しばしばこのブログでも触れているように、今のお笑い芸やテレビ等での笑いの中には、高齢や容貌をネタにして、誰もが笑えない笑い(?)が笑いと勘違いされ振りまかれていることが、しばしばある。

 観客や聴衆の誰
観客や聴衆の誰
 もが傷つく
もが傷つく ことなく、一様に、抵抗感なく笑える、普遍的価値を持つ「良質な笑い」の実証にも役立つだろう。「良質」とか言えば、それだけで、道徳的管理的だとのそしりがあるかも知れないが、現実に、エセ的な笑いによって傷つけられる人にとっては、笑いの質は深刻な課題であること、あることである。また、それがイジメのテクニックにつながりかねない状況にあることも、笑いの量を計測することへの期待をふくらませる
ことなく、一様に、抵抗感なく笑える、普遍的価値を持つ「良質な笑い」の実証にも役立つだろう。「良質」とか言えば、それだけで、道徳的管理的だとのそしりがあるかも知れないが、現実に、エセ的な笑いによって傷つけられる人にとっては、笑いの質は深刻な課題であること、あることである。また、それがイジメのテクニックにつながりかねない状況にあることも、笑いの量を計測することへの期待をふくらませる
 。
。
さまざまな思いを乗せて、私の aH への思いは、高まっていく。木村教授、期待してます。
※ 前回と今回の記事の「笑い」については、昨年の大晦日12月31日と今年の2月6日と7日に載せていますので、ご参照ください。
aH その2
 一方、プラス的な、笑いの量の計測化の効用を考えると、番組の中でもあったが、笑いの量の大小が商業的価値につながる可能性、さらに医療的には、免疫力向上との関連性を科学的に追求できるだろう。
一方、プラス的な、笑いの量の計測化の効用を考えると、番組の中でもあったが、笑いの量の大小が商業的価値につながる可能性、さらに医療的には、免疫力向上との関連性を科学的に追求できるだろう。また、笑いの「普遍化」というか、誰でも笑える
 「価値ある笑い」も数値化できる効用もあるだろう。しばしばこのブログでも触れているように、今のお笑い芸やテレビ等での笑いの中には、高齢や容貌をネタにして、誰もが笑えない笑い(?)が笑いと勘違いされ振りまかれていることが、しばしばある。
「価値ある笑い」も数値化できる効用もあるだろう。しばしばこのブログでも触れているように、今のお笑い芸やテレビ等での笑いの中には、高齢や容貌をネタにして、誰もが笑えない笑い(?)が笑いと勘違いされ振りまかれていることが、しばしばある。
 観客や聴衆の誰
観客や聴衆の誰
 もが傷つく
もが傷つく ことなく、一様に、抵抗感なく笑える、普遍的価値を持つ「良質な笑い」の実証にも役立つだろう。「良質」とか言えば、それだけで、道徳的管理的だとのそしりがあるかも知れないが、現実に、エセ的な笑いによって傷つけられる人にとっては、笑いの質は深刻な課題であること、あることである。また、それがイジメのテクニックにつながりかねない状況にあることも、笑いの量を計測することへの期待をふくらませる
ことなく、一様に、抵抗感なく笑える、普遍的価値を持つ「良質な笑い」の実証にも役立つだろう。「良質」とか言えば、それだけで、道徳的管理的だとのそしりがあるかも知れないが、現実に、エセ的な笑いによって傷つけられる人にとっては、笑いの質は深刻な課題であること、あることである。また、それがイジメのテクニックにつながりかねない状況にあることも、笑いの量を計測することへの期待をふくらませる
 。
。さまざまな思いを乗せて、私の aH への思いは、高まっていく。木村教授、期待してます。
※ 前回と今回の記事の「笑い」については、昨年の大晦日12月31日と今年の2月6日と7日に載せていますので、ご参照ください。